共有持分に抵当権を設定しても大丈夫?5つの注意点をわかりやすく解説
共有持分の基礎知識
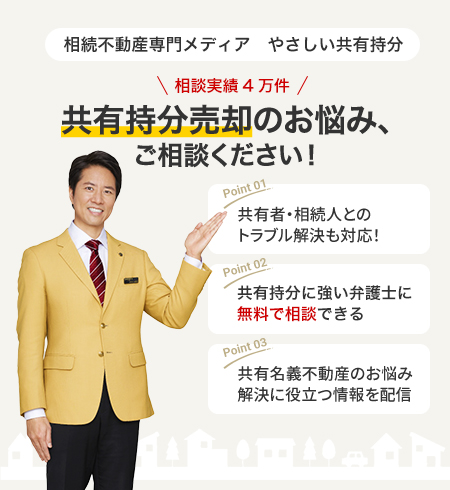
共有持分は、通常の不動産と異なる点が多くあります。 共有者同士の権利関係、民法上のルール、リスクなど、共有名義不動産を所有する上で、押さえておきたい基礎知識に関する記事をまとめています。
「共有持分を売却したい」「共有状態を解消したい」そんな方のために、売却方法や売却時の注意点についてまとめました。 共有持分の売却で失敗しないための業者選びについてもまとめています。
共有持分の放棄は、慎重に検討する必要があります。 間違いやすい相続放棄と持分放棄の違いや放棄しない方がいいパターンについても共有持分の専門家がわかりやすく解説します。
不動産の相続時に注意しておきやいポイントや遺産分割協議の流れについても、専門家監修のもと、わかりやすく解説しています。 共有名義不動産がトラブルになりやすい理由やトラブル回避方法についてもぜひご覧ください。