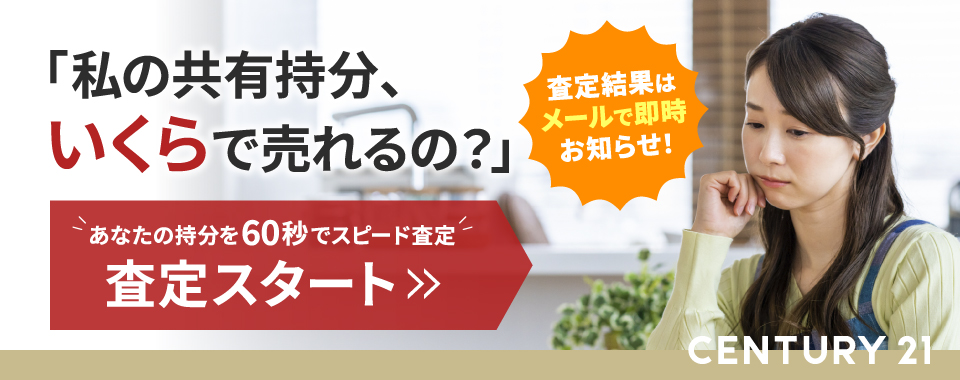共有持分売却の完全ガイド|売却戦略から具体的な方法まで解説
共有持分売却の完全ガイド|売却戦略から具体的な方法まで解説

目次
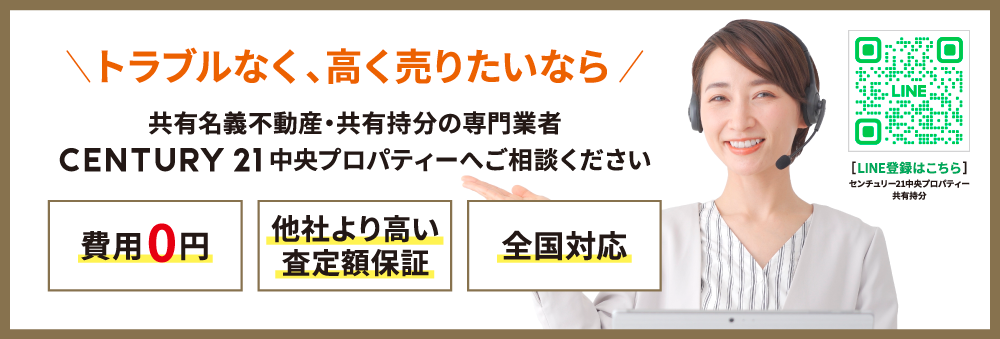
共有持分売却の基礎知識
まずは、共有持分の売却に関する基礎知識を解説します。
共有名義の不動産とは何か
共有名義の不動産とは、1つの不動産に対し、所有者が複数人いる不動産のことです。
共有持分とは、複数人が所有権を共有している状態を指します。
共有持分が発生する主なきっかけは、2つあります。
- 複数人で不動産を相続したケース
- 不動産を共同購入したケース
例えば、兄弟で実家を相続したケースや夫婦でマイホームを購入したケースなどが具体例としてあげられます。
共有持分と持分割合の基本
持分割合とは、1つの不動産を複数人で所有する際の各自の所有権割合を指します。
例えば、実家を兄弟二人で相続した場合、兄と弟で持分割合は2分の1ずつになります。
持分割合は、相続の場合は遺言書や当事者間での決まりがなければ、法定相続分で決まります。
夫婦でペアローンを組むなどして、家やマンションを購入した場合は、出資割合に準じて持分割合が定められます。
共有者の法的権利と義務
共有名義不動産は、単独所有の不動産のように自由に扱うことができません。
各共有者の同意が必要となる行為は、法律で次のように決められています。
| 行為 | 具体例 | 行為の制限 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 共有物の修繕 不法占拠者への明渡請求 | 各共有者が 一人で対応可能 |
| 管理行為 | 賃貸借契約の締結 短期間の賃貸借 | 共有者の持分価格の 過半数で決定 |
| 変更行為(軽微なもの) | 外壁や屋根の修繕 植樹伐採 | 共有者の持分価格の 過半数で決定 |
| 変更行為(軽微以外) | 共有物全体の売却 増改築・建て替え | 共有者の全員の同意が必要 |
行為の内容によって、他の共有者の同意が必要になります。
また、共有持分の義務として、共有名義不動産にかかる固定資産税や維持管理費用は、原則持分割合に応じて各共有者が負担することとされています。
民法第253条第1項
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
共有持分の売却方法と戦略
共有持分の売却を検討されている方向けに、売却方法と賢く売却するための戦略を解説します。
共有者全員の同意を得る売却
最も理想的な方法は、共有者全員の同意を得て、共有名義不動産全体を売却する方法です。
買い手からすると、通常の所有権の不動産と何ら変わりないため、需要も高く、売買価格も高額になりやすいためおすすめです。
次は、一人でも売却に反対する共有者がいる場合の売却方法について解説します。
自己の持分のみ売却
共有者の中に、売却を反対する人がいる場合は、自己持分のみを売却する方法があります。
共有名義不動産全体の売却には、共有者全員の同意が必要ですが、自己持分のみの売却であれば、本人の意思のみで売却可能です。(民法第206条)
土地分筆による売却
共有名義の不動産が土地の場合は、分筆という方法があります。
土地の分筆とは、登記簿上は1つになっている土地を複数の土地に分けて登記し直すことです。
分筆された土地は、それぞれの単独名義になります。
単独名義になれば、共有名義特有の活用制限等がなくなり、共有者間でのトラブルからも逃れることができます。
共有物分割請求の実施
共有物分割請求とは、不動産の共有状態を解消するためにおこなう請求です。
当事者間での話し合いが難しい場合は、共有物分割請求訴訟にて、共有状態の解消方法について裁判所に判断を委ねることができます。
共有持分売却の法律について
共有持分の売却時には、正しく法律を理解しておく必要があります。
売却後のトラブルを防ぐために、共有持分売却の法律について解説します。
民法上の共有名義不動産の取扱い
民法上、共有名義不動産の売却には、共有者全員の同意が必要です。
一人でも反対する人や意思確認ができない人がいる場合、共有名義不動産全体の売却はできません。
但し、共有持分の売却は、他の共有者の同意なしで売却が可能です。(民法206条)
他の共有者に黙って、自己持分を売却しても法律違反ではありません。
共有持分の買取請求権
共有持分の買取請求権とは、とは「民法上の強制力を持って他の共有者の持分を買い取る権利」のことです。(民法第253条2項)
例えば、本来は持分割合に応じて負担しなければならない税金を、共有者のAさんが滞納していたとします。
あなたは、Aさんの代わりに税金を支払い、何度もAさんに税金を払うように催促しましたが、1年以上応じてもらえない状況が続いています。
このような場合に、共有持分の買取請求権を行使して、Aさんの持分をあなたが強制的に買い取ることができます。
共有持分売却時のリスクとトラブル
共有持分は単独の意思で売却できますが、次のようなリスクがあります。
- 他の共有者との関係性が悪化する
- 持分を購入した第三者と他の共有者がトラブルになる
- 共有物分割請求訴訟に発展する可能性がある
詳しくは、以下の動画をご覧ください。
共有持分売却時のリスクと対策
リスクに対する対策として、以下の3つが挙げられます。
- 他の共有者に事前に相談しておく
- 共有持分専門の業者に持分を売却する
- 売却後のトラブルにも対処してもらえる業者を選ぶ
他の共有者に事前に相談してから売れば、「勝手に売った!」と非難されることはないでしょう。
また、共有持分を専門に取り扱う不動産会社であれば、共有者への交渉スキルや権利調整に長けているため、購入後のトラブルリスクを軽減することができます。
また、「売却して終わり」ではなく、売却後もトラブルが起きた際には、弁護士のフォローを受けられる不動産会社を選ぶことも重要なポイントです。
共有持分売却時の価格トラブルの解決策
共有持分の売却先は、主に共有者か共有者以外の第三者になります。
共有者間での持分売買が成立しない最も多い理由は、売買価格で合意できないからです。
持分を売る側としては、当然ながら、市場相場と同等の価格を希望したいところですが、持分を買い取る共有者に資金力がなければ、その要望は叶いません。
第三者に売却する場合、共有持分専門の不動産会社に相談するのが一般的です。
同じ共有持分を専門に扱う不動産会社でも、査定額や売却にかかる費用は、大きく変わります。
必ず複数社を比較し、トラブルなく高く売却できる業者を選びましょう。
第三者に売却する際に高額売却するための方法は、以下の4つです。
- 共有持分専門の不動産会社に依頼する
- 買取業者ではなく仲介業者を選ぶ
- 不動産鑑定士に査定を依頼する
- 売却にかかる費用を抑える
共有者の同意が得られない場合の対応
売却に際して、共有者の同意が得られない場合や話し合いが成立しない場合は、無理に自分で交渉を進めようとせず、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
共有者との権利調整や交渉などは、法律問題に精通した弁護士の見解をもとに進めることで円滑に進みます。
弁護士に直接相談する、または共有持分を専門に扱う不動産会社では、ほとんどが弁護士と提携していますので、売却前提であれば、不動産会社を通じて弁護士を紹介してもらうのも良いでしょう。
共有持分の売却手続きと必要書類
売却の意思が固まれば、売却手続きに入ります。共有持分の売却プロセスや必要書類を解説します。
売却プロセスの詳細
共有持分の売却プロセスは以下の通りです。
- 共有者に持分を売却することを伝える
- 市場価格を調べる
- 各社に査定を依頼する
- 最低売却価格を決める
- 販売活動開始
- 売買契約締結
- 決済・移転登記
共有持分の売却は、他の共有者の同意なしで可能ですが、後々のトラブルを避けるために可能であれば、事前に共有者に通知しておくことがおすすめです。
また、不動産会社へ査定を依頼する前に不動産の市場相場を確認しておくことで、不動産会社の言いなりにならずに済みます。
但し、共有持分の購入希望者は少ないため、自分の希望する額での売却が難しい場合も大いにあります。
最低限いくらであれば妥協できるかも、自分の中で想定しておくと良いでしょう。
共有持分売却時の必要書類
共有持分の売却には、主に以下の書類が必要です。
- 登記識別情報
- (持分を売却する人の)身分証明書、印鑑証明書、住民票、実印
- 固定資産税評価額の証明書
土地の場合は、土地測量図及び境界確認書が必要になります。
詳しくは、共有持分専門の不動産会社に確認しましょう。
弁護士や専門家の活用
共有持分を売却する際は、基本的に相続登記が必要になります。
相続登記がまだの場合は、弁護士や司法書士へ依頼しましょう。
不動産会社によっては、相続登記の代行まで請け負ってくれるところもありますので、相談してみましょう。
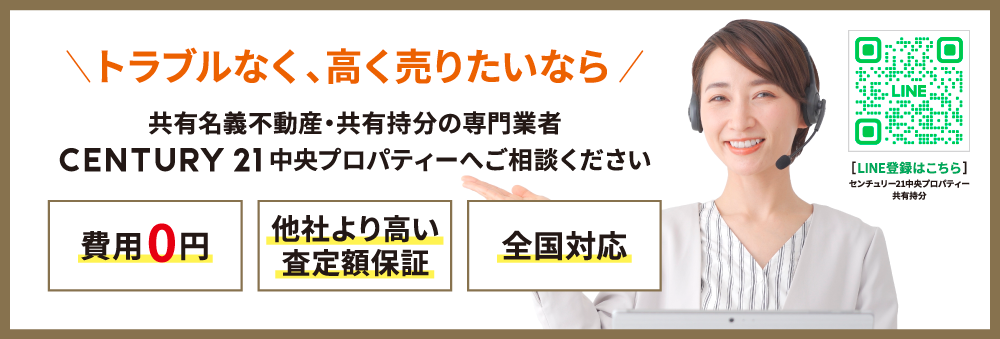
共有持分売却に伴う費用と税金
共有持分の売却時にかかる費用や税金についても解説します。
印紙税、登記費用、仲介手数料
仲介手数料は、不動産仲介会社に支払う費用です。
仲介手数料は、買主と売主が折半の業者もあれば、買主がすべて負担する会社もありますので、確認してみましょう。
相続登記が未了の場合は、まず登記の変更が必要になります。
その際、司法書士や弁護士に依頼すれば、報酬料が発生します。
印紙税は、売買価格に応じて金額が決まります。
| 売却価格 | 収入印紙の金額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円※ |
| ~50万円以下 | 200円 |
| ~100万円以下 | 500円 |
| ~500万円以下 | 1,000円 |
| ~1,000万円以下 | 5,000円 |
| ~5,000万円以下 | 10,000円 |
| ~1億円以下 | 30,000円 |
譲渡所得税と復興特別所得税
共有持分の売却によって譲渡所得(譲渡益)が出た場合は、譲渡所得税を納付します。
- 譲渡所得=不動産の売却額-取得費-譲渡費用
課税所得税は不動産の保有期間によって税率が変わります。
保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以内では「短期譲渡所得」が適用されます。
復興特別所得税とは、所得税額に対する付加税で、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付するものです。
共有持分 売却のメリットとデメリット
共有持分を売却するメリット・デメリットについて解説します。
共有持分売却のメリット
共有持分を売却する主なメリットは、以下の4つです。
- 共有者間のトラブルから解放される
- 現金化できる
- 税金の負担から解放される
- 子や孫の相続トラブルを回避できる
共有持分売却の最大のメリットは、煩わしい共有者同士のトラブルから解放されることです。
共有持分を売却し、共有関係から抜け出すことで、相続トラブルや離婚トラブルのストレスから解放され、更には現金(売却益)を手にすることができます。
また、共有持分は相続の対象になるため、共有者であるあなたに相続が発生した場合、あなたの後世である子や孫が新たな共有者になります。
複雑な権利関係による相続トラブルを回避できる点も、共有持分売却のメリットと言えるでしょう。
共有持分売却のデメリット
共有持分を売却する主なデメリットは、以下の2つです。
- 他の共有者との関係性が悪化する
- 持分の購入者と他の共有者との間でトラブルに発展する
共有持分の売却は、単独の意思で可能ですが、登記簿上の情報が変更になるため、いずれあなたが持分を売却したことは、他の共有者に知られることになります。
その際に、「なぜ勝手に売ったんだ!」とトラブルになるケースもあります。
また、自分の持分のみを売却した場合、第三者が共有者の中に加わることで不動産に対する意思決定が困難になる、購入後の第三者が他の共有者に対して持分を売り渡すように迫るといったトラブルに発展するケースも珍しくありません。
不動産の共有状態を解消する方法
共有持分の売却以外にも、共有状態を解消する方法はあります。
遺産分割時に共有名義を避ける
そもそも、遺産に不動産が含まれる場合、共有名義で相続することは避けましょう。
遺言書で誰か一人を不動産の相続人として指定しておく、遺産分割協議で単独名義になるように調整するなどして、後にトラブルの元になる「とりあえず共有名義」は絶対にやめましょう。
共有物分割請求による共有名義の解消
当事者間で話し合いができない、まとまらない場合は、共有物分割請求訴訟にて、裁判所に判断を委ねるのも一つの方法です。
共有物分割請求訴訟を提起すると、必ず共有状態は解消されます。
しかしどのように分割するかは、裁判所が判断するため、必ずしも思い通りの結果にならない点は留意しておきましょう。
共有状態維持のリスクと解消の必要性
共有状態を継続することの主なリスクは、以下の通りです。
- 不動産の活用に制限がかかる
- 共有者間でトラブルになりやすい
- 相続や売買により権利関係が複雑になる
- 離婚時にトラブルになりやすい
共有名義不動産の活用には、他の共有者の同意が必要ですが、共有者の人数が増えれば、各自に連絡を取って、意思確認を行うだけでも一苦労です。
なかなか、不動産を活用する権利を活かすことは難しいでしょう。
さらに、持分は各共有者の単独の意思で売買可能なため、「知らない人といつの間にか共有状態になっている」といったケースも珍しくありません。
共有持分売却後の手続き
共有持分が無事に売却できた後の手続きについて解説します。
売却後の法的手続き
売却後に必要な手続きは、持分の所有権移転登記手続きです。
この登記手続きは、原則、登記権利者(持分の買主)と登記義務者(持分の売主)が共同で申請します。
このあたりの手続きは、共有持分を専門に扱う不動産会社の指示に従い動くのが良いでしょう。
司法書士や弁護士に代行しても、問題ありませんが報酬料が発生する点に留意しましょう。
確定申告と税務処理
共有持分の売却によって、譲渡益が出た場合は、確定申告の対象になります。
譲渡益が0円の場合やマイナス(譲渡損失)になる場合は、確定申告は任意となります。
また、固定資産税の負担は、その年の1月1日時点で、登記簿に所有者として登記されている人が負担することになっています。
売却しても、固定資産税の負担が発生する場合がありますので注意しましょう。
まとめ
CENTURY21 中央プロパティーは、共有名義不動産を専門に取り扱う不動産仲介業者です。
共有名義不動産でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
共有持分のよくある質問
共有持分を高く売るにはどうしたらいいですか?
共有持分を高く売るには、共有持分専門の不動産業者に依頼することが大切です。
不動産会社の中でも、買取業者ではなく、仲介業者へ依頼する方が、高値で売却できる可能性が高いです。
また、不動産鑑定士の鑑定書付きがあれば、買い手が見つかりやすく高額売却ができます。
自分の持分のみを売却することは可能でしょうか?
自己持分は、共有者の同意なく売却可能です。(民法206条)
共有名義不動産全体の売却が難しい場合、自己持分のみの売却を検討するとよいでしょう。
共有者とのトラブルを解決する方法はありますか?
結論から申し上げますと、共有状態を解消することです。
共有状態を解消する方法として、自己持分を売却する、または共有物分割請求訴訟によって、不動産を分割する方法があります。
どのような方法が最適かわからない方は、当社へご相談ください。
共有持分はいくらで売れますか?
共有持分の売却価格は、不動産全体の売却と比べると低くなります。
また他の共有者が住んでいるなど、利用状況や立地条件によっても大きく変動します。
少しでも高値で売却したい場合は、当社の不動産鑑定士による無料査定サービスをご利用ください。
共有持分を売却した後、他の共有者はどうなりますか?
持分の売却後は、持分の購入者と他の共有者が、共有状態になります。
購入者によっては、他の共有者に持分の売買に関する交渉を持ちかけることがあります。無理な交渉は、共有者間でのトラブルに発展します。
売却後のトラブルを防ぐためにも、売却先は慎重に選ぶことが大切です。
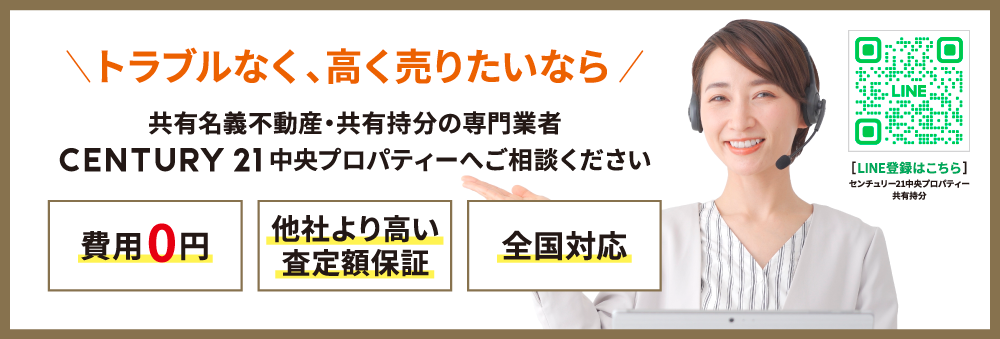
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。