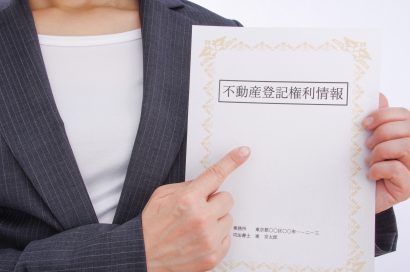相続した不動産が共有名義だと危険?よくあるトラブルと解決策を徹底解説
相続した不動産が共有名義だと危険?よくあるトラブルと解決策を徹底解説

目次
不動産の相続において、相続人同士で意見がまとまらず「とりあえず共有名義」にしてしまうケースは珍しくありません。 しかし、共有名義不動産は後々トラブルになりやすい側面があります。
本記事では、相続がきっかけで共有名義不動産を所有している方に向けて、トラブル解決の方法を詳しく解説します。

共有名義での不動産相続を避けるべき理由
不動産を相続する際、複数の相続人で「共有名義」とすることは、一見公平な解決策に見えるかもしれません。しかし、安易に共有名義を選択すると、将来的に多くのトラブルや不都合が生じる可能性があります。
たとえば、不動産を売却したり、リフォームをしたりする際には、原則として共有者全員の同意が必要です。たった一人でも反対する共有者がいれば、これらの行為は実現できません。また、固定資産税などの税金は共有者全員で負担するものですが、連絡が取れない共有者がいたり、支払いを拒否する共有者がいたりすると、誰かが立て替え払いをする義務を負うことになります。
さらに、共有者に相続が発生するたびに共有者の数は増え続け、権利関係はより複雑化していきます。これにより、将来的に不動産の活用や処分がさらに困難になるケースも少なくありません。
知っておきたい!共有名義不動産のリスクと注意点
遺産分割協議にて、「とりあえず共有名義にしておこう」という考えは、絶対にやめましょう。
相続人が知っておきたい共有名義不動産のリスクと注意点は、以下の通りです。
- 売却や増改築には共有者全員の同意が必要
- 持分割合に応じて税金の負担が発生
- 相続により共有者が増え続ける
- 共有者に連絡が取れない、または行方不明になるリスクがある
売却や増改築には共有者全員の同意が必要
共有名義不動産を売却したり、増改築(リフォーム)したりするには、共有者(相続人)全員の同意が必要です。増改築(変更)に同意が必要なことは、民法第251条からも明らかといえます。
(共有物の変更)各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
仮に自分の持分割合が売却に反対する他の共有者(相続人)の持分割合より多くても、不動産全体の売却はできません。これは、不動産全体を処分するには共有者全員の合意が原則として必要となるためです。
このように、共有名義不動産には他の共有者(相続人)の同意がなければ売却や増改築ができないといった不便さがあります。
相続した不動産を分割せず共有名義のままにすることは、結局のところ、他の共有者(相続人)との話し合いを先送りしているに過ぎません。
持分割合に応じて税金の負担が発生
遺産分割協議がまとまらず不動産が共有名義のままだと、持分割合に応じた税金負担が発生します。通常、固定資産税の納付書は共有者の代表者に届き、代表者が一度全額を立て替えるのが一般的です。その後、各共有者が自身の持分に応じた税金を代表者に支払う流れとなります。
しかし、この支払いが行われず、一部の共有者が税金を負担しないことでトラブルになるケースが少なくありません。不動産の共有者には、固定資産税全額に対して連帯納付義務があります(地方税法第10条の2)。これは、他の共有者が支払わない場合、自分が代わりに全額を納める義務があるという意味です。たとえ自分の持分割合が少なくても、他の共有者が支払わなければ、あなたが代わりに全額を支払う責任が生じます(民法第253条第1項)。
そのため、「税金を払わない人がいる」「自分は住んでいないのに税金だけ負担している」といった、税金負担を巡るトラブルが共有名義不動産では頻繁に発生します。
相続により共有者が増え続ける
共有名義不動産は、共有者に相続が発生するたびに、さらに共有者が増え続けてしまいます。
共有者の数が増えれば増えるほど、不動産の売却や増改築といった全員の同意が必要な重要事項の決定は非常に難しくなります。また、持分の過半数で決められる管理行為(民法第252条)ですら、意見の集約が困難になるでしょう。例えば、固定資産税を代表者が立て替えた場合でも、請求先が1、2人ではなく、5人以上にもなると回収がさらに大変になります。
このように、相続時の遺産分割協議で安易に「とりあえず共有名義」にしてしまうと、将来的に子や孫の代にまで、この不動産がトラブルの火種として残ってしまうことになります。遺産分割協議をまとめるのは骨が折れる作業かもしれませんが、ご自身だけでなく、将来の世代のためにも、できる限り早めに共有状態を解消することが賢明です。
共有者に連絡が取れない、または行方不明になるリスクがある
共有名義不動産では、相続発生時に共有者の中に連絡が取れなくなる人や、最終的に行方不明になってしまう人が出てくるリスクがあります。このような状況に陥ると、不動産の管理や売却に重大な支障が生じます。
例えば、建物の修繕が必要になった際、共有者全員の同意が得られなければ工事を進めることができません。また、不動産を売却しようとしても、行方不明の共有者がいると売却手続きが非常に困難になります。最悪の場合、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうなど、時間も費用もかかる法的手続きが必要となり、その間に不動産の価値が下落する可能性も考えられます。共有者が多いほど、このようなリスクは高まるため、共有名義の解消は早めに検討するべきです。
共有名義不動産のよくあるトラブル
共有名義不動産は、多くのトラブルを引き起こす可能性があります。
特に、以下の点が問題になりがちです。
- 共有者と意見が合わず売却や活用が進まない
- 維持費や税金の負担割合で揉める
- 1人の共有者が占拠している
- 長期間放置されることによる問題
共有者と意見が合わず売却や活用が進まない
共有名義の不動産は、売却や長期間の賃貸といった重要な決定に共有者全員の同意が必要です。このため、共有者間で意見が分かれると合意形成が難しく、行動が進まないケースがよくあります。
例えば「売りたい派」と「持ち続けたい派」が対立した場合、売却が数年単位で進まないことも珍しくありません。この状況が続くと、結果的に不動産の資産価値が下がるリスクもあります。
維持費や税金の負担割合で揉める
共有名義の不動産では、固定資産税や修繕費などの維持費用を、持分割合に応じて共有者全員で負担するのが原則です。
しかし、一部の共有者が支払いを拒否する場合もあるでしょう。また、「自分は使っていない」と主張されることもあり、代表者が全額負担を余儀なくされることも珍しくありません。
1人の共有者が占拠している
共有不動産では、1人の共有者が勝手に占拠し、家賃を払わないケースもあり得ます。
この場合、他の共有者の権利が侵害されることになり、法的措置が必要になる場合もあります。占拠者との対立が激化すれば、訴訟に発展してしまう場合があります。
長期間放置されることによる問題
遠方の不動産を相続した場合や空き家の場合、長期間活用されずに放置されてしまう可能性があります。
空き家をそのまま放置すると、防犯上の危険や近隣からの苦情など、大きなトラブルになりかねません。
また、共有名義の不動産では、共有者に相続が発生すると、共有者の数が増え、権利関係が更に複雑化します。合意形成がますます困難になり、不動産が「活用も処分もできない状態」に陥ることもあり得るでしょう。
不動産の共有状態を解消する方法
共有状態を解消する方法には、主に次の4つがあります。
- 共有名義不動産全体を売却する
- 共有物分割請求で不動産を分割する
- 共有者間で持分を売買する
- 第三者に自己持分を売却する
それぞれ、どのような解消方法かを解説していきます。どの方法を選ぶか検討するにあたって、ぜひ参考にしてください。
共有名義不動産全体を売却する
共有名義不動産全体を売却すれば、共有状態は解消されます。これは、自分の持分だけを売るよりも高値で売却できる可能性が高く、共有者全員の合意が得られるなら最も良い方法と言えるでしょう。
例えば、2,000万円で不動産全体を売却し、持分が半分なら1,000万円を受け取れます。一方で、自分の持分だけを売る場合、全体で売るよりも2割程度安くなるのが一般的です。これは、持分だけの購入では不動産の活用に制限が多く、買い手が少ないためです。
不動産全体を売却する方法は、持分の評価が不要でトラブルが起きにくく、実際の売却額に基づいて分配されるため、公平性も高いと言えます。
共有物分割請求で不動産を分割する
共有名義不動産の分割方法は、主に次の3つです。
- 現物分割:
不動産を物理的に分け、それぞれの共有者が単独で所有する方法です。例えば、60坪の土地を2人で分けるなら、30坪ずつに分筆します。ただし、場所や形によって土地の価値が異なる場合があるため、公平な分割が難しいこともあります。 - 代償分割:
共有者のうち1人が不動産を単独で所有し、他の共有者にはその持分に応じた金銭(代償金)を支払う方法です。例えば3,000万円の不動産を2人で半分ずつ所有している場合、1人が1,500万円を支払って単独所有にします。代償金を支払う側に十分な資金があること、そして持分の評価額について共有者間で合意できることが前提となります。 - 換価分割:
不動産全体を売却し、その売却代金を持分割合に応じて共有者全員で分け合う方法です。これは、すでに説明した「共有名義不動産全体を売却する」方法と同じで、公平性が高く、トラブルになりにくい傾向があります。
いずれも、専門的な知識が必要となるため、共有名義不動産に詳しい不動産会社に相談し、あなたに最適な方法を相談することをお勧めします。
共有者間で持分を売買する
共有状態を解消する方法の一つに、共有者同士で持分を売買するという手段があります。これは、ある共有者が他の共有者からその持分を買い取ることで、不動産を単独所有にするものです。遺産分割協議の前でも、共有者であれば自分の持分を他の共有者に売却できます。
ただし、持分を買い取る側の共有者に十分な資金力があること、そして売却する持分の価格について双方で合意できることが前提となります。もし価格で揉めたり、購入希望の共有者に資金がなければ、この方法は難しくなります。
第三者に自己持分を売却する
他の共有者の同意なしに共有状態を解消する方法として、あなたの持分のみを第三者に売却するという選択肢があります。
これは、あなたの持分を売却する行為であり、他の共有者の権利には影響しないため、彼らの同意は不要です。(民法第206条)
確かに、不動産全体を売却する方がより高値で売れる傾向にあります。しかし、他の共有者が売却に反対している場合や、全員の同意を得るのが難しい、あるいは時間や手間がかかる場合には、ご自身の持分だけを売却することを検討すると良いでしょう。

相続した共有名義不動産を売却する流れ
共有名義不動産の売却は、単独名義の場合と異なり、共有者全員の合意が必要となるため、手続きが複雑になることが多いです。
1. 遺産分割協議と共有名義登記
まず、相続が発生したら、遺産分割協議を行い、不動産を共有名義で相続するか、特定の相続人が単独で相続するかを決定します。共有名義で相続する場合は、その旨を記した遺産分割協議書を作成し、法務局で共有名義での相続登記を行います。
遺産分割協議書は、後々のトラブルを防ぐためにも、具体的に誰がどれだけの持分を持つのかを明記することが重要です。
2. 共有者全員の合意形成
共有名義不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する共有者がいると、原則として売却はできません。
まずは共有者全員で集まり、売却の意思があるか、売却価格の目安、売却にかかる費用負担などを話し合います。話し合いがまとまらない場合や、共有者間に意見の相違がある場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家を交えて話し合うことも有効です。
3. 不動産会社との媒介契約
共有者全員の売却意思が固まったら、不動産会社に売却を依頼します。この際、以下の点に注意が必要です。
- 共有者全員が媒介契約書に署名・捺印:
不動産会社との媒介契約は、共有者全員が当事者として署名・捺印する必要があります。 - 売却価格の決定:
複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な売却価格を共有者全員で合意形成します。 - 媒介契約の種類:
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のいずれかを選択します。共有名義の場合は、共有者間の連絡を密にし、情報共有を徹底することが重要です。
4. 購入希望者の募集と交渉
不動産会社が購入希望者を募り、内覧などの対応を行います。購入希望者が現れたら、価格や引き渡し時期などの条件交渉を行います。
不動産会社からの報告を共有者全員で共有し、交渉内容についても全員で合意形成を行います。
5. 売買契約の締結
購入希望者と条件がまとまったら、売買契約を締結します。
- 共有者全員が売買契約書に署名・捺印:
売買契約書も、共有者全員が当事者として署名・捺印する必要があります。 - 手付金の受領:
通常、買主から売主に対して手付金が支払われます。この手付金の配分についても、共有者間で事前に取り決めておく必要があります。
6. 決済と所有権移転登記
売買契約書に定めた決済日に、買主から残代金が支払われ、同時に所有権移転登記の手続きを行います。
所有権移転登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、売主・買主双方の本人確認を行い、必要な書類を確認して登記申請を行います。
登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知書」(権利証)が発行されます。
7. 税金の支払い
不動産を売却すると、譲渡所得税(所得税・住民税)や印紙税、登録免許税(司法書士報酬を含む)などの税金が発生します。
譲渡所得税は、各共有者の持分に応じて計算され、それぞれが納税義務を負います。
一定の要件を満たす場合は、居住用財産の3,000万円特別控除などの特例が適用される可能性があります。税理士に相談することをお勧めします。

共有持分のみを売却する流れ
相続した不動産が共有名義であり、その共有持分のみを売却する場合について解説します。不動産全体を売却する場合とは異なり、他の共有者の同意は原則不要ですが、買い手が限られるなどの特徴があります。
1. 共有者への意思表示(推奨)
法的には、ご自身の共有持分を売却するのに他の共有者の同意や通知は不要です。しかし、後々のトラブルを避けるためにも、他の共有者に、ご自身の持分を売却する意向があることを伝えておくことを強くお勧めします。
他の共有者が買主となる場合は、単独名義になるメリットや、競売になる可能性を回避できるメリットなどを伝えて交渉を進めましょう。
まずは、ご自身の希望売却価格を提示し、他の共有者との間で価格交渉を行います。必要であれば、不動産鑑定士に査定を依頼し、客観的な価格を提示することも有効です。
2. 売却先の選定と査定依頼
他の共有者への売却が難しい場合や、高く売りたい場合は、共有持分専門の不動産業者を検討します。複数の業者に査定を依頼し、比較検討することが重要です。
インターネットなどで「共有持分 売却」などと検索し、共有持分の専門業者を探します。通常の不動産会社では、共有持分の取り扱いを断られるケースも多いため注意が必要です。
共有持分の査定依頼時には、以下の書類が必要になる場合があります。
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 固定資産税評価証明書
- 公図、地積測量図(土地の場合)
- 本人確認書類
- 印鑑証明書

3. 売買条件の交渉と決定
査定額に納得できたら、具体的な売買条件(売却価格、引き渡し時期、支払い方法など)について交渉を進めます。
共有持分の売却価格は、不動産全体の市場価格に持分割合を乗じた額よりも低くなることが一般的です。これは、買い手が自由に不動産を利用できないリスクを負うためです。
提示された売買契約書の内容を十分に確認し、不明な点や疑問点があれば、必ず売却先に確認するか、弁護士などの専門家に相談しましょう。
4. 売買契約の締結
売買条件が合意に至ったら、売買契約を締結します。
- 契約書への署名・捺印: 売買契約書に署名・捺印します。
- 手付金の受領: 通常、契約時に買主から手付金が支払われます。
5. 決済と持分移転登記
売買契約書に定めた決済日に、残代金の受領と同時に共有持分の所有権移転登記手続きを行います。
所有権移転登記は、司法書士に依頼して行います。司法書士が売主と買主の本人確認を行い、必要書類を確認の上、法務局へ登記申請を行います。以下の書類などが必要になります。
- 登記済権利証または登記識別情報通知
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 住民票
- 固定資産税評価証明書
- 身分証明書(運転免許証など)
6. 税金の支払い
共有持分を売却した場合、売却益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)が発生します。
売却価格から、取得費(購入時の費用など)と譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いた額が譲渡所得となります。
譲渡所得があった場合は、翌年の確定申告期間中に税務署に申告・納税が必要です。
税金の計算や特例の適用(居住用財産の3,000万円特別控除など)について不明な点があれば、税理士に相談することをお勧めします。

まとめ
誰が不動産を相続するか決まらず、「とりあえず共有名義」にしてしまうことで、後々トラブルに発展するリスクがあります。
当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。
当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。
センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。
また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。
共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒。東京弁護士会所属。テレビ朝日「シルシルミシル」の法律解説でもおなじみの敏腕弁護士。相続や共有不動産トラブル、離婚等の家事事件、交通事故、労災など一般の社会人に起こりうるであろう案件を中心に、その解決へ尽力する。