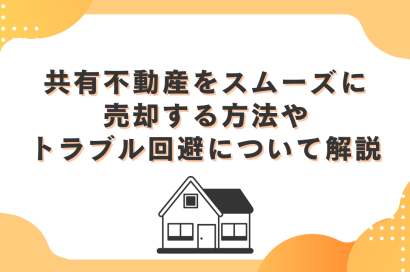共有不動産を現金化する方法は?売却の流れやポイント、注意点を解説

目次
相続や共同購入などをきっかけに、一つの不動産を複数人で共有するケースは少なくありません。
しかし、共有不動産のままでは活用や処分が難しく、現金化を検討する際には共有者間の合意が必要になることもあります。
そのため、共有者間で意見が対立すると、売却が円滑に進まないなどの問題も起こり得ます。
この記事では、共有不動産を現金化するための代表的な方法や手続きの流れ、注意すべきポイントについて解説します。
共有不動産を現金化する6つの方法
共有不動産を現金化する方法としては、以下の6つが代表的です。
- 共有者全員の合意のもと、共有不動産全体を売却する
- 自分の共有持分のみを第三者に売却する
- 他の共有者に自分の共有持分を売却する
- 全員分の共有持分を買い取り、単独名義にして売却する
- 共有物分割請求により共有状態を解消したうえで現金化する
- 不動産全体または持分を担保に借り入れ、現金を調達する
1.共有者全員の合意のもと、共有不動産全体を売却する
共有者全員が同意した上で、共有不動産全体を売却する方法です。
売却によって得られた代金は、原則として各共有者の持分に応じて分配されます。
共有者全員の合意のもとで不動産全体を売却する場合、単独所有の不動産と同様に市場で売却活動を行うことができます。
そのため、共有持分のみを売却する場合(通常、市場価格よりも大幅に安い価格での取引となることが多い)とは異なり、市場価格での売却が可能となります。
ただし、共有不動産全体の売却は、民法第251条で定められた共有物に対する「変更行為」に該当します。
したがって、売却には共有者全員の合意が必要です。
一人でも反対する共有者がいると全体売却は実行できないため、事前に共有者間で十分に話し合い、合意形成を図る必要があります。
全員が不動産の売却に合意できる場合は、共有不動産の全体売却は、一般的に最も好条件で現金化できる手段と言えます。
2.自分の共有持分のみを第三者に売却する
共有者全員の合意が得られない場合には、自分の共有持分のみを第三者に売却することも可能です。
前述の通り、共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要ですが、自己持分のみの処分(売却)は、民法第206条により、原則として他の共有者の同意なしに単独の意思で行うことが認められています。
そのため、他の共有者と連絡が取れない場合や、関係性が悪化している場合は、この方法が有効な解決策となり得ます。
しかし、共有持分のみを購入しても不動産全体の利用には制限があるため、一般的な不動産市場での買主探しは難航する傾向があります。
共有持分のみを売却する場合は、専門の買取業者や、専門仲介業者にマッチングしてもらった投資家などが主な買主となるでしょう。
共有持分の売却相場としては、「不動産全体の市場価格 × 持分割合」で算出される単純な持分価格から、共有持分の買い手が限定される点(流動性の低さ)や利用制限などを理由に、大幅に割り引かれることが一般的です。
場合によっては、市場価格を基にした持分評価額の半額以下になる可能性も考慮しておく必要があります。
ただし、共有持分の売却相場は売却先によっても異なります。
3.他の共有者に自分の共有持分を売却する
他の共有者に資金的余裕がある場合は、自分の共有持分を他の共有者に売却する方法も有効です。
この方法であれば、新たな第三者が共有関係に加わることがないため、権利関係の複雑化を防げる点がメリットと言えます。
また、買主となる共有者にとっては、持分割合が増加し、不動産に対して行使できる権利(例えば、民法第252条に基づく管理に関する決定権など)が強まる可能性もあります。
特に、持分割合が過半数を超えることで、共有物の管理に関する事項(軽微な変更を含む)を単独で決定できるようになります。
他の共有者へ持分を売却する場合の価格は、当事者間の交渉によって決まりますが、一般的には「不動産全体の市場価格 × 売却する持分割合」が一つの目安とされます。
ただし、これはあくまで交渉の基準であり、実際の取引価格は双方の合意によって決まります。
| (例)市場価格5,000万円の共有不動産を所有していて、持分割合が1/4だった場合交渉の目安となる価格▼ 5000万円×1/4 = 1250万円 |
※売却価格が市場価格から著しく低い場合、税務上「みなし贈与」と判断され、買主に贈与税が課される可能性もあるため注意が必要です。
4.全員分の共有持分を買い取り、単独名義にして売却する
共有不動産の価値を最大限に引き出して売却したい、かつ自身に資金的な余裕がある場合には、他の共有者の持分をすべて買い取り、不動産を単独所有にしてから売却する方法も考えられます。
単独所有の不動産は、共有持分のみの売却に比べて需要が高いため、市場価格での売却が可能です。
不動産を単独所有にすることで、共有状態のときのような利用や収益、処分に関する制限がなくなり、通常の不動産として扱えるようになります。
これにより、共有持分のみを売却する場合と比べて制約が少なく、市場価格での売却がしやすくなります。
ただし、他の共有者からの持分買取コストが発生する点に注意が必要です。
5.共有物分割請求により共有状態を解消したうえで現金化する
他の共有者との間で、共有不動産の分割や売却に関する協議がどうしてもまとまらない場合、地方裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起し、裁判所の判決によって共有状態の解消を求める方法があります。
訴訟には時間と費用がかかりますが、共有関係を強制的に解消できるため、膠着状態を打開する最終手段となり得ます。
裁判所が共有物分割を命じる場合、主な分割方法は以下の3つです。
| 詳細 | |
| 現物分割 | 共有不動産そのものを、持分割合に応じて物理的に分割し、各共有者が単独名義で所有する方法。建物など、物理的に分割が困難な場合は適用されにくい。 |
| 代償分割 | 共有者の1人が不動産全体を取得し、他の共有者はその見返りに持分相当額に見合う代償金を取得することで共有状態を解消する方法。不動産を取得する共有者に代償金を支払うための資金力が求められる。 |
| 換価分割 | 共有不動産全体を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法。裁判所の判決による場合は競売が命じられる。 ただし、訴訟上の和解が成立した場合などは別で、当事者の合意に基づき任意売却(市場での売却)を行うことも可能。 一般的に任意売却は、競売より高値で売却できる可能性がある。 |
なお、共有物分割請求を終えてから不動産を売却する場合は、既に共有関係が解消された単独所有の不動産、または共有関係が整理された状態となっているため、市場価格がそのまま売買価格の目安になります。
6.不動産全体または持分を担保に借り入れ現金を調達する
共有不動産全体、または自己の持分を担保として融資を受ける方法もあります。
「不動産担保ローン」が代表的です。
この方法のメリットは、不動産を手放さずに資金を調達できることです。
ただし、当然ながら借入金であり、利息を含めた返済義務が生じるため、綿密な返済計画が不可欠です。
不動産全体を担保にする場合は共有者全員の同意が必要ですが、自己の持分のみを担保にする場合は他の共有者の同意は不要です。
なお、共有持分のみを担保とする融資は、担保評価や換金性の問題から、取り扱う金融機関が少ない、あるいは融資条件が厳しくなる(融資限度額が低い、金利が高いなど)可能性がある点に留意が必要です。
共有不動産を高く売却する3つの方法
共有不動産や共有持分を高く売却するポイントは、以下の3つです。
- 無料査定を複数社に依頼する
- 買取業者よりも仲介業者を選ぶ
- 売却のタイミングを見極める
無料査定を複数社に依頼する
共有不動産や共有持分を売却する際に、自分の不動産の価値について正しく把握しておくことが大切です。
中には明確な理由なく安い査定額を提示し、買い叩こうとする悪徳業者も存在するのが現実です。
不動産会社の言いなりにならないよう、複数社に無料査定を依頼し、市場相場を理解しておきましょう。
不動産の査定方法は会社によって異なります。
どのように査定を行ったのか、査定額の根拠についても、納得できるまで担当者にしっかりと確認しましょう。
特に、共有持分の売却には、専門的な知識や経験が必要です。
持分売却後に他の共有者とトラブルになってしまうことを防ぐためにも、複数の担当者と話すことで、信頼できる担当者を見極めることができます。
また、査定額だけでなく、販売戦略、仲介手数料、対象エリアの土地柄を理解しているかなど、各社の提案内容を比較検討することで、自分にとって最も有利な条件で売却できる会社を選ぶことができます。
不動産会社の査定結果だけでなく、国土交通省の「不動産取引価格情報検索」も活用してみましょう。
買取業者よりも仲介業者を選ぶ
共有不動産や共有持分の売却において、一般的には買取業者よりも仲介業者を選ぶ方が、より高い価格で売却できる可能性が高いと言えます。
なぜなら、買取業者は買い取った不動産を転売し、その差額で利益を得るビジネスモデルです。
そのため、市場価格よりも低い価格で買い取って、高く転売したいというのが買取業者の本音なのです。
買取業者が提示した査定額がそのまま売却価格になることが多く、価格交渉できる余地が少ない傾向があります。
共有持分のみの買取となると、さらに価格が低くなる可能性が高いです。
一方で仲介業者は、インターネット広告やポータルサイト、独自のネットワークを活用して、物件情報を公開し、購入希望者を探す活動を行います。
仲介業者は、売買契約が成立した際に、売主・買主双方(または一方)から受け取る仲介手数料を収益源としています。
仲介手数料は、不動産の売買価格に比例するため、「より高値で売却したい」という売主の意向と合致します。
そのため、購入希望者との価格交渉にも積極的に対応してくれる可能性が高いです。
持分のみの売却においても、仲介業者に依頼したほうが高値での売却が期待できます。
売却のタイミングを見極める
共有不動産・共有持分に限らず、不動産の売却価格は、市場の需給バランスや景気動向などによって変動します。
適切なタイミングを見計らうことで、高値売却につながる可能性もあります。
また、税金の控除や特例が使える条件も売却時期によって異なります。
例えば、「相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別控除の特例」(通称:相続空き家の3,000万円特別控除)は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋(一定の要件を満たすもの)を相続した方が、その家屋または敷地などを売却した際に、譲渡所得から最大3000万円まで控除できる特例措置です。
この控除が使える期間は、相続の開始があった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限(現行法では2027年12月31日まで)となります。
相続がきっかけで共有不動産を所有している方は、この特例の適用期間内に売却を検討することで、譲渡所得税を節税できる可能性があります。
共有不動産を現金化する流れ【仲介業者を利用する場合】
仲介業者に依頼して、共有不動産(または共有持分)を売却する場合の一般的な流れは以下の通りです。
- 共有者間で協議する
- 仲介業者に売却を依頼する
- 販売活動を行う
- 売買契約を締結する
- 決済と所有権移転登記を行う
Step1.共有者間で協議する
最初に、共有者全員での話し合いを行います。
特に、共有不動産全体を売却する場合は、共有者全員の合意が不可欠です。
この段階で、売却の意思、希望する売却価格、売却時期、諸費用(仲介手数料、税金など)の負担割合、売却代金の分配方法など、具体的な条件について認識を共有し、合意形成を目指します。
意見がまとまらない場合や、交渉が難しい場合は、この段階から弁護士などの専門家に相談することも有効です。
自身の共有持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意は不要ですが、売却を進める旨を事前に伝えておく方が、後のトラブル防止に繋がる場合もあります。
Step2.仲介業者に売却を依頼する
売却の方針が決まったら、不動産仲介業者に売却活動の依頼(媒介契約の締結)を行います。
複数の業者に査定を依頼し、提示された査定価格や売却戦略、担当者の対応などを比較検討した上で、信頼できる業者を選びましょう。
業者の担当者と面談を行い、売却したい背景や物件の状況、希望する売却条件(価格、時期など)などを伝えます。
この面談には弁護士が同席する場合もあり、売却によって起こり得るリスクについて、法的な視点から助言を受けられます。
Step3.販売活動を行う
媒介契約を締結すると、仲介業者は販売活動を開始します。
仲介業者が持つ買い手ネットワークの活用や不動産ポータルサイトへの掲載、広告媒体、チラシ配布、既存顧客への紹介など、様々な方法で買主を探します。
共有持分の場合は、不動産投資家や専門の買取業者などが主なターゲットとなることもあります。
内覧希望者があれば対応し、購入希望者が見つかれば価格や引き渡し条件などの交渉を行います。
売却活動の状況は定期的に報告を受け、必要に応じて売却価格などの条件を見直すこともあります。
Step4.売買契約を締結する
買主が見つかり、売却条件について合意に至ったら、売買契約の締結に進みます。
共有不動産の売買契約の場合、売主として共有者全員が契約に関与する必要があります(代表者を立てることも可能ですが、他の共有者からの委任状などが必要です)。
一方、共有持分のみの売買の場合は、その持分の所有者(売主)と買主との間で契約します。
契約書には、物件の特定、売買代金、手付金の額、支払い条件、所有権移転と引き渡しの時期、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)など、通常の不動産売買と同様の事項が記載されます。
共有不動産特有の事項として、売買対象が共有持分であること、持分割合などを明確に記載します。
契約内容に不明な点や不安な点があれば、署名・捺印する前に必ず仲介業者や弁護士に確認しましょう。
Step5.決済と所有権移転登記を行う
売買契約書で定められた決済日に、買主から売主へ売買代金の残金が支払われます。
同時に、所有権移転登記の申請手続きを行います。
共有不動産全体を売却する場合、所有権移転登記には共有者全員が売主として手続きに関与する必要があります。
登記申請に必要な書類(登記済権利証または登記識別情報通知、印鑑証明書など)を事前に準備し、司法書士に登記手続きを依頼します。
一方、自分の共有持分のみを第三者に売却する場合には、他の共有者の関与は不要であり、売主と買主のみで登記手続きが可能です。
登記が完了すると、不動産の所有権(または持分)が正式に買主へ移転します。
売却代金から諸費用(仲介手数料、登記費用、印紙税、譲渡所得税をはじめとした税金など)を差し引いた額が、最終的な手取り額となります。
また、固定資産税・都市計画税などの清算もこのタイミングで行われます。
共有不動産を現金化する際のポイント
共有者との連携や事前準備を工夫すれば、取引条件が良くなったり、売却期間を短縮できたりする可能性もあります。
共有不動産を現金化する際のポイントは以下の通りです。
- 共有不動産の全体売却を目指す
- 共有不動産や共有持分の取り扱いを専門とした不動産会社を選ぶ
- なるべく共有者同士の個人間売買は避ける
- 売却以外の選択肢も検討する
共有不動産の全体売却を目指す
先述の通り、持分のみの売却よりも共有不動産全体を売却する方が、市場での需要が高く(買い手の選択肢と利用価値が大きく広がるため)、一般的な高値で売れやすくなります。
持分のみの場合、買い手は他の共有者との関係性や将来的な利用方法に不確実性を感じ、購入を躊躇しがちです。
一方、全体売却であれば、買い手は単独で自由に利用・処分できるため、市場の幅広い層にアプローチでき、競争原理が働きやすいです。
共有不動産の現金化にあたっては、共有者全員で協力し、全体売却を目指すことが、より多くの現金を手に入れる可能性が高い手段と言えます。
共有不動産や共有持分の取り扱いを専門とした不動産会社を選ぶ
共有不動産、特に一部の共有持分のみの売買は、権利関係の複雑さや買主探しの難しさなどから、専門的な知識と経験が求められます。
そのため、共有不動産や共有持分の取り扱いを専門とした不動産会社を選ぶことが重要です。
専門業者であれば、適切な価格査定、独自の販売ルートの活用、そして共有者間の調整や法的な手続きに関するノウハウも期待できます。
そして、弁護士などとの協力体制が整っているかどうかもチェックポイントの一つです。
共有不動産の売却では、権利関係の調整や相続問題、税務申告など、法的なサポートが必要となる場面が多くあります。
センチュリー21中央プロパティーのように専門家が常駐している不動産会社であれば、安心して取引を任せることができます。
なるべく共有者同士の個人間売買は避ける
共有者同士の共有持分の個人間売買は、売却条件や代金の分配方法を巡ってトラブルになる可能性が高いです。
お互いに十分な知識がない状態で取引を進めると、後々トラブルになりかねない不備のある契約を結んでしまったり、適正価格から大きく外れた金額で取引してしまったりするおそれがあります。
また、仮に適正価格より大幅に安い価格で売却した場合、税務署から贈与とみなされて、買主に贈与税が課される可能性もあります(みなし贈与)。
したがって、たとえ共有者間で売買の合意が得られたとしても、安全かつ確実に取引を行うためには、不動産会社(仲介業者)や司法書士などの専門家に依頼し、適切な売買契約書の作成や登記手続きを行ってもらうことを強く推奨します。
専門家が間に入ることで、客観的な立場から適正な取引をサポートし、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
売却以外の選択肢も検討する
現金化=売却、というイメージが大きいですが、先述した通り融資(借入れ)の選択肢もあります。
また、状況によっては賃貸に出して賃料収益を得るという方法も考えられます。
融資の最大のメリットは、不動産を手放すことなく、現金化できる点です。
現金化したい理由が一時的な資金確保の場合や、将来的にその共有不動産を活用・所有し続けたい意向がある場合などは、融資や賃貸運用の選択肢も柔軟に検討してみると良いでしょう。
共有不動産を現金化ならセンチュリー21中央プロパティー
この記事では、共有不動産を現金化するための様々な方法や流れ、注意点について解説しました。
共有不動産の売却や現金化には、共有者間の合意形成や手続きの調整、税務対応など、単独所有の不動産売却に比べて多くの課題が伴います。
どの現金化方法を選択するにしても、専門的な知識が不可欠となる場面が多くあります。
共有不動産や共有持分の取り扱いに精通した不動産会社に相談することで、手続きの負担を軽減できるだけでなく、適正な価格での売却や、予期せぬトラブルの回避に繋がります。
また、必要に応じて弁護士や司法書士、税理士といった専門家のサポートを得ることも、円満な解決のためには非常に重要です。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。
一般市場での売却が難しいとされる共有持分につきましても、不動産鑑定士による厳密な査定と、独自の買い手ネットワークを活用することで、お客様にとってよりより良い条件での売却を目指しています。
共有不動産や共有持分の現金化・売却に関するお悩みやご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
不動産鑑定士
不動産鑑定士・株式会社大村不動産鑑定事務所 代表・宅地建物取引士
1995年に宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)登録(第37393号)。2001年には不動産鑑定士登録(第6786号)を行い、20年以上にわたり不動産鑑定評価の最前線で活躍している。2018年からは東京不動産鑑定士会会長を務め、業界を牽引する権威として知られる。
株式会社大村不動産鑑定事務所の代表として、不動産鑑定評価業務をはじめ、価格査定、意見書作成など、不動産の価格に関するあらゆる業務に精通。
特に、業者間で査定額に大きな差が生じやすい共有持分の不動産鑑定において、市場動向を考慮した精度の高い査定には定評がある。その豊富な経験と専門知識は、お客様の不動産に関する疑問や不安を解消し、適切な意思決定を強力にサポートする。