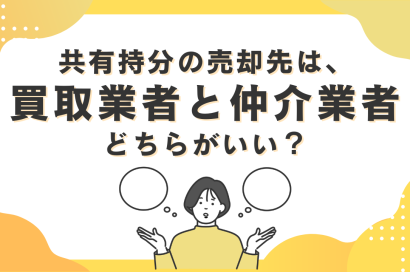共有持分の売却先は、買取業者と仲介業者どちらがいい?買取業者の目的は何?
共有持分の売却先は、買取業者と仲介業者どちらがいい?買取業者の目的は何?
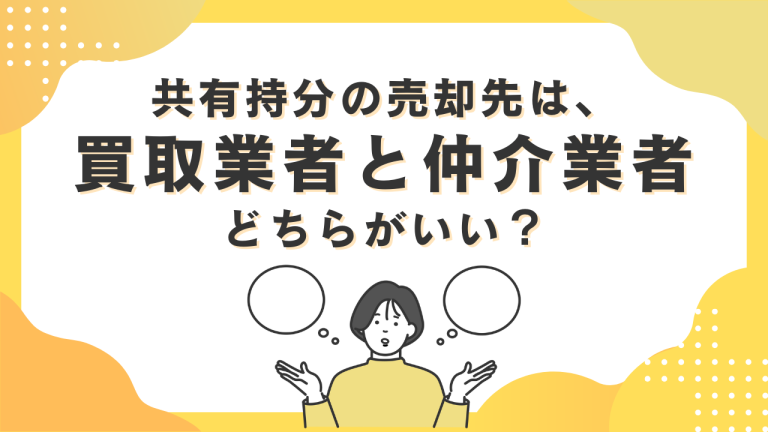
目次
共有持分の売却を検討しているところで、「買取業者に売却すべきか、当面業者に依頼すべきか」で悩んでいませんか? どちらを選ぶべきかは、売却を急ぐか、少しでも高く売りたいかによって変わってきます。
本記事では、共有持分の売却先として「買取業者」と「仲介業者」の違いや、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。各業者の目的についても掘り下げていきます。

共有持分は売却可能
共有持分とは、複数人の共同名義で保有している不動産のうち、各共有者が持っている所有権割合のことです。
共有不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要ですが、自己持分のみであれば、単独の意思で売却可能です。(民法第206条)
売却に反対する共有者がいる場合や共有者とのトラブルから解放されたいとお悩みの方は、自己持分の売却を検討してみましょう。
共有持分の売却の相談先
共有者以外の第三者に、共有持分を売却したいと考えた際の相談先は、以下の2つです。
- 共有持分専門の買取業者
- 共有持分専門の仲介業者
選択肢は多くないですが、買取業者、仲介業者それぞれの特徴を理解し、自身の条件に合う選択をしましょう。
共有持分の買取業者とは
共有持分の買取業者の目的は、持分を低価格で買い取り、再販売(転売)することで利益を上げることです。
持分の買取業者の場合は、持分を買い取った後、対象不動産の他の共有者に対して、持分の買取交渉を行います。一人の持分だけを所有していても、不動産を自由に活用することはできないため、買取後は、他の共有者に持分を売却して貰えないか交渉を行うのが一般的です。
他の共有者の持分もすべて買い取ることで、単独名義の不動産になります。単独名義の不動産にすることで、不動産としての価値が高くなり市場で高く取引できる状態になります。
このようにして、バリューアップを行い、利益を出すのが共有持分の買取業者です。
まとめると、共有持分の買取業者の流れは、主に以下の通りです。
- 持分を買い取る
- 他の共有者にも持分の買取を交渉する
- 全員分の持分を買い取り、単独名義の不動産にする
- 単独名義の不動産として転売し利益を得る
買取業者のメリット
共有持分の買取業者を利用するメリットは、以下の通りです。
- 仲介手数料がかからない
- 早く売却できる
- 契約不適合責任がない
買取業者のメリットは、何といっても仲介手数料が不要な点です。
買取業者が自ら買い取ってくれるため、仲介手数料は発生しません。ただし、事務手数料などの名目で費用を取ってくる業者もいるので注意が必要です。
また、買取業者が直接買い取るため、最短3日など、短期間で売却できるのも特徴です。
見落としがちですが、売却後のトラブルを防ぐためにも、契約不適合責任についても確認しておく必要があります。
契約不適合責任とは、売却する不動産の品質や酒類、数量が契約の内容に適合しない場合、売主は買主に対して責任を負わなければなりません。これを「契約不適合責任」と言います。2020年4月の民法改正前までに「瑕疵担保責任」と言われていたのがこれです。
不動産取引において個人が買主の場合、契約不適合責任がありますが、買取業者が買主の場合は、売主の契約不適合責任が免除されます。
参考までに以下は、契約不適合責任の範囲内で、売主が責任を負うべき項目の一例です。
- 土壌汚染
- 地盤沈下
- 建物の傾き
- 地中埋設物
- 雨漏り
- シロアリ など
買取業者のデメリット
共有持分の買取業者を利用するデメリットは、以下の通りです。
- 買取価格が安くなる
- 持分の売却後に共有者とトラブルになる可能性がある
- 売主に不利な契約条件になっている可能性がある
買取業者のビジネスモデルは物件を安く買い、高く売ることです。その差額が利益になるため、当然安く買いたいというのが買取業者の本音です。
少しでも高い価格で売却したいという売主の考えとは、相反する部分になるため、注意が必要です。
買取業者は、持分の買取後、他の共有者に対し、持分を売って欲しいと交渉を行います。買取業者の無理な交渉により、トラブルに発展するケースがあります。
せっかく売却したにも関わらず、買取業者の立ち回り次第では、売却後もトラブルが付きまとうことになるため、買取業者の選定は慎重におこないましょう。
また、買取業者と直接取引する場合、重要な売買契約書などは買主である買取業者が作成することになります。不動産のプロである買取業者は自分たちに不利な契約書を作るはずがありませんので、契約書の案文は事前に専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
特に、契約書内に記載されている特約条項に注意が必要です。
特約条項とは、通常契約の他に当事者間に特別の条件や利益を伴う契約条項を付する際の、追加項目のことです。この特約条項に売主に不利な内容や条件が追加されていないか確認しましょう。

共有持分の仲介業者とは
共有持分の仲介業者は、売主と買主、またはどちらか一方から「仲介手数料」を貰うことで利益を得ています。仲介業者は、買取業者と違って、自ら物件を購入せず、持分の買主候補を探してくれます。
共有持分の場合、買主候補となるのは、投資家や投資法人になるケースが多いです。
この投資家や投資法人は、持分を購入した後、法的な権利に則って、共有者に家賃分配を請求したり、共有者の意向を汲み取りながら、不動産の活用方法について協議を行います。
そのため、買取業者と比べて、融通が利きやすく、持分売却後の共有者とのトラブルが少ない傾向にあります。
仲介業者のメリット
共有持分の仲介業者を利用する主なメリットは、以下の3つです。
- 適正価格で売却できる
- 法的手続きや契約関連の手間がない
- 持分売却後の共有者とのトラブルが少ない
共有持分専門の仲介業者は、独自のネットワークを使って、「最高値」で持分を買ってくれる人を探してくれます。
仲介業者の利益である仲介手数料は、売買価格に比例します。少しでも高く売りたい売主との利害関係が一致するため、買取業者よりも売却額が高額になるのです。
また、共有持分の売買には、様々な法的手続きや契約の締結が必要です。仲介業者では、基本的に手続きや契約締結に必要な書類作成等、すべて丸投げで請け負ってくれるため、自身で調べながら動く手間が省けます。
仲介業者はあくまでも売主と買主の中立的な立場です。不動産や法律に関することなど、中立的な立場でアドバイスや選択肢を提示してもらえる可能性が高いです。
不動産や法律の知識が乏しい方や共有者同士でのトラブルを抱えている場合は、仲介業者の方がおすすめです。
さらに、先述の通り、持分購入後、他の共有者に無理な交渉が行われることがないため、売却後のトラブルが少ない点もメリットと言えます。
仲介業者のデメリット
一方、仲介業者のデメリットは下記となります。
- 仲介手数料が発生する
- 売却までに時間がかかることがある
複雑な契約書作成や法律関係の手続きを代行してもらえる分、手数料が発生します。但し、業者によっては売主側からは手数料をいただいていない場合もあります。
中央プロパティーは、仲介手数料が無料で持分を高額売却できます! ≫
また、仲介業者のデメリットとして、良い条件で購入してくれる購入希望者を探したり、買主が購入資金の準備したりと、買取業者と比較すると売却までに時間がかかることがあります。平均的には、売却まで1週間ほどかかるケースが多いようです。

買取業者と仲介業者どちらがいいの?
ここまで両社の特徴について解説してきましたが、どちらがいいのでしょうか。
| 買取業者 | 仲介業者 | |
| メリット | ・仲介手数料がかからない ・早く売却できる ・契約不適合責任がない | ・適正価格で売却できる ・法的手続きや契約関連の手間がない ・持分売却後の共有者とのトラブルが少ない |
| デメリット | ・買取価格が安くなる ・持分の売却後に共有者とトラブルになる可能性がある ・売主に不利な契約条件になっている可能性がある | ・仲介手数料が発生する ・売却までに時間がかかることがある |
ネットで調べてみても、買取業者のサイトでは買取業者を推し、仲介会社のサイトでは仲介会社を推していて何を信用すればいいかわからないですよね。
結論、買取業者でも仲介業者でもどちらでもよいというのが、当社の見解です。どちらがいいと一概に言うのは難しく、お客様が何を一番に求めているか、によってどの業者に依頼するかは変わります。
大事なのは、高く売る(買い取ってくれる)ためのノウハウや鑑定査定精度の高さ、トラブル解決・未然に防ぐノウハウなど「共有持分に特化」しているかどうかです。
また、メールなどのやり取りだけではなく、直接その業者の会社にお足を運んでみて、会社の雰囲気や規模、対応スタッフの印象をくみ取るのも判断要素の一つになるのではないでしょうか。
とにもかくにも、納得する形で共有不動産の取り扱い実績が豊富な業者を必ず選ぶようにしましょう。

共有持分を売却する流れ
共有持分を売却する流れは、以下の通りです。
- 複数社比較する
- 売却に必要書類を準備する
- 売買契約締結
1.複数社比較する
共有持分の売却で不動産会社を選ぶ際の比較のポイントは、専門性の高さと査定額です。
先述した通り、共有持分の売却は通常の不動産と比べて権利関係が複雑であることから、弁護士と連携しながら、慎重に対応する必要があります。
初回の問い合わせの段階で、担当者の知識レベルや信用できる会社がどうか口コミを確認し、業者は慎重に選びましょう。
また、共有持分の査定額については、買取業者と仲介業者で大きく変わるケースもあります。不動産会社の言いなりにならないために、自身の不動産価値の相場を知ることは重要です。
- 周辺の相場を調べる
- 買取業者、仲介業者それぞれに査定を依頼する
- 会社の実績や口コミを調べる
2.売却に必要書類を準備する
共有持分の売却に必要な書類は、主に下記となります。必要書類は、市区町村役場の窓口等で取得し手元に準備しましょう。
- 権利証(登記識別情報)
- 土地測量図及び境界確認書(土地の場合)
- 身分証明書(顔写真付き)
- 印鑑証明書
- 実印
- 住民票(登記簿上の住所から転居している場合)
- 固定資産税評価額の証明書
- 委任状(必要に応じて)
3.売買契約締結
売買契約書には、普段見慣れない用語が並んでおり、難しく感じる方も多いでしょう。
ただし、内容を理解せずに契約を締結することで、売却後にトラブルになってしまう可能性もあります。弁護士と提携している不動産会社であれば、売買契約時に弁護士に同席してもらえないか交渉してみると良いでしょう。
その場で弁護士に、不明点や不安なことを確認し、クリアにしておくことが大切です。
中央プロパティーでは、売買契約時に必ず弁護士が同席します。売買契約の内容も、事前に弁護士がリーガルチェックを行い、売主に不利な内容がないかどうかも確認します。
共有持分の買取相場はいくら?
共有持分は、一般的な不動産と比較して、相場が低くなります。
また、単純に不動産の全体価格×持分割合ではなく、そこから減価される点、留意しておきましょう。
例えば、不動産の全体価格が6,000万円で、持分割合が2分の1の場合、持分価格は約1,500万円が相場です。単純に考えると、3,000万が持分価格になりますが、持分という特殊な不動産の性質上、約半分ほどの評価になってしまいます。
減価される割合は、不動産の価値や共有者との関係性によって、変わります。
あなたの持分価格がすぐに分かる!共有持分の査定サービスはこちら ≫

共有持分の売却は中央プロパティーへ
センチュリ-21中央プロパティーは、共有持分の売却に特化した不動産仲介業者です。これまでに、4万件以上共有名義不動産のトラブルを解決してきた実績があります。
社内弁護士が常駐しているため、トラブルになりやすい持分の売却も、安心安全に取引をサポートできる体制が整っています。仲介業者でありながら、売却に掛かる諸費用はすべて買主負担のため、売主様は諸費用0円で当社サポートをご利用いただけます。
以下に当てはまる方は、ぜひ当社へご相談ください。
- 持分売却の流れが具体的に知りたい
- 他社で査定してもらったが安価にしかならず、売却を思いとどまっている
- 共有者同士の関係性がさらに悪化しそうで売却を諦めている
- 売却にともなう諸手続きや相続登記などの費用がネックで動けていない
- 他の共有者とのトラブルを避けたい
共有持分の専門家集団が、ご状況に応じた最適なご提案であなたのお悩みを解決します。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。