共有不動産をスムーズに売却する方法とは?トラブル回避のコツも解説
共有不動産をスムーズに売却する方法とは?トラブル回避のコツも解説
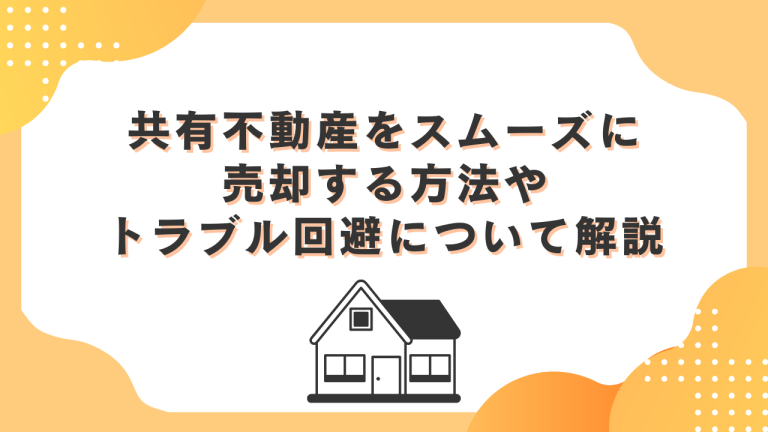
目次
- 1 共有不動産とは?
- 2 共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要
- 3 共有不動産を売却する人が急増している理由
- 4 共有名義不動産を売却する方法
- 5 共有不動産売却にかかる費用と必要書類
- 6 共有不動産売却のトラブルを避けるには?
- 7 共有持分を売却した後の注意点
- 8 勝手に共有持分が売却されてしまった場合の対処法
- 9 共有不動産を賢く売るためのポイント
- 10 共有名義のトラブルを未然に防ぐ方法
- 11 共有名義不動産売却のよくある質問
- 11.1 Q. 共有名義の不動産は全員の同意が必要ですか?
- 11.2 Q. 共有者が売却に反対している場合、どうすればよいですか?
- 11.3 Q. 共有持分の売却に他の共有者の同意は必要ですか?
- 11.4 Q. 共有名義の不動産を売却するときの税金はどうなりますか?
- 11.5 Q. 他の共有者が行方不明の場合でも売却できますか?
- 11.6 Q. 他の共有者が物件に住んでいても売却できますか?
- 11.7 Q. 他の所有者に共有持分を売却されたらどうしたら良いですか?
- 11.8 Q. 売却代金の分配はどのように決定しますか?
- 11.9 Q. 共有名義の不動産の売却を進める際、必要な書類は何ですか?
- 11.10 Q. 共有名義不動産を売却する際の注意点を教えてください。
- 11.11 Q. 離婚前に共有持分を売却することはできますか?
- 12 まとめ
「共有名義の不動産は売却が難しい」「共有者との意見がまとまらない」とお悩みではありませんか? 共有不動産の売却は、確かに通常の不動産売却とは異なる特有の課題があります。特に、家族間で共有している実家や土地などでは、それぞれの立場や感情が絡み合い、話が複雑になることも少なくありません。
しかし、適切な知識と方法を知っていれば、共有不動産の売却をスムーズに進め、不要なトラブルを回避することは十分に可能です。
この記事では、なぜ共有名義になるのかという根本的な理由から、共有者全員の同意を得て売却する方法、あるいは自分の持分のみを売却する方法、さらには法的な手続きまで、具体的な売却方法を詳しく解説します。

共有不動産とは?
共有不動産とは、一つの不動産を複数人で所有している不動産を指し、正式には「共有名義不動産」と呼ばれます。
例えば、夫婦で不動産を購入する際に、住宅ローン控除や売却時の特別控除を二重に受けられるという理由から、夫婦の共有名義にしているケースは少なくありません。
また、不動産の相続が発生した場合、誰が代表して相続するのか決まっていない、あるいは売却に適した状況ではないなどの理由から、相続人の共有名義にしているケースも多く見られます。
共有名義となる主な原因と問題点
共有名義の不動産になる主な原因は相続です。現金と違って均等に分けにくい不動産は、相続人全員が「とりあえず」共有名義で相続してしまうケースが多くあります。
しかし、共有名義の不動産は、特定の共有者が独占して利用し、他の共有者は自分の権利を活かせないことがほとんどです。さらに、使っていないのに修繕費や固定資産税といった維持費を負担し続けることになり、不満が募りやすいのが実情です。
共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要
一つの不動産を複数人で所有している場合、不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意を得なければなりません。
例えば、兄弟3人で実家を相続したとします。2人が売却に賛成していても、1人が売却に反対すれば、共有名義の不動産を売却することはできません。
共有持分のみの売却は単独で可能
自分の持分のみを売却する場合は、他の共有者の同意なしで売却することが可能です。
これは民法第206条で認められている権利です。
ただし、全体売却と比較して、売却価格が大幅に安くなる点には注意が必要です。
共有不動産を売却する人が急増している理由
共有不動産の売却を考える人が増えている背景には、共有者とのトラブル増加があります。
例えば、共有不動産のトラブルには、以下のようなものがあります。
- 一人の共有者が住み続けていて、他の共有者が権利を活かせない
- 売却に反対する共有者がいて、不動産を処分できない
- 自分は住んでいないのに、税金だけ払わされている
- 共有者が多すぎて、どうしたら良いか分からない
共有名義の不動産を持つようになる一番の原因は、「相続」です。相続時に「とりあえず」という形で共有名義にしてしまうと、後々の不動産管理や活用、そして売却をめぐって、さまざまなトラブルに発展することが少なくありません。
特に注意したいのは、共有者がねずみ算式に増えていくことです。たとえば、元々兄弟2人で共有していた不動産も、どちらか一方に相続が発生すれば、その子や孫までが新たな共有者となる可能性があります。このように相続人が増えるたびに権利関係は複雑になり、トラブルが起きやすくなるのが実情です。
自分だけでなく、大切な子や孫までを将来のトラブルに巻き込んでしまうリスクがあるため、共有名義不動産を売却してこの関係を解消しようと考える人が急増しています。
共有名義不動産を売却する方法
共有名義不動産は、売却が難しいと言われることがありますが、以下の方法で売却することが可能です。
共有名義不動産を売却する方法は、大きく以下の5つです。
不動産全体を売却する場合
1. 共有者全員の合意を得て不動産全体を売却する
共有者全員が売却に同意している場合は、不動産全体を売却する「全体売却」を検討しましょう。
この方法は、最も高く共有名義不動産を売却できる方法です。
ただし、共有者の中に売却を反対する者がいる場合や、共有者が多すぎて全員の意思確認ができない場合は、この方法は難しいでしょう。
自分の持分のみを売却する場合
2. 自分の持分のみを第三者に売却する
共有名義不動産のうち、自己持分のみであれば、他の共有者の同意なしで売却することが可能です。
持分とは、共有不動産に占めている自分の権利の割合のことを指します。
例えば、兄弟3人で実家を相続した場合、3分の1ずつ持分を所有していることになります。この持分については、他の共有者の同意を得ることなく自由に売却することが可能です(民法第206条)。
ただし、不動産の全体売却よりも、大幅に売却価格が安くなる点に注意が必要です。
3. 他の共有者へ持分を売却する
自分の持分を第三者に売却するのではなく、他の共有者に買い取ってもらう方法です。この場合、他の共有者が不動産の持分を増やすことができるため、交渉がスムーズに進む可能性があります。
また、第三者が介入しないため、プライバシーの面でも安心感があるでしょう。
ただし、他の共有者に購入資金がない場合や、買い取りに前向きでない場合は難しい選択肢となります。
共有名義を解消して売却する場合
4. 共有物分割請求訴訟による売却
共有者間で話し合いがまとまらず、全体売却も持分売却も難しい場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起し、裁判所の判断で共有状態を解消して売却する方法です。
裁判所は、現物分割(土地を物理的に分けるなど)が困難な場合、競売による売却を命じ、その売却代金を各共有者の持分割合に応じて分配する「換価分割」を命じることが多いです。
この方法は最終手段となりますが、共有関係を法的に解消し、売却を強制的に進めることが可能です。
5. 土地を分筆して単独名義にする(土地のみ)
共有名義の不動産が土地の場合、「分筆」することも検討できます。
共有名義の土地における分筆とは、複数人で所有していた土地を物理的に分け、それぞれを単独名義で登記し直すことを指します。
分筆した後の土地は各自の単独名義の土地となるため、自由に売却できるだけでなく、共有持分として売却するよりも高く売却できる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、この方法を選択できるのは、共有名義の不動産が土地の場合に限られる点に注意が必要です。
また、いびつな形の土地や土地が小さい場合、分筆したことによって不動産の価値が下がるケースもあるため、専門家と十分に相談し、慎重に検討する必要があります。

共有不動産売却にかかる費用と必要書類
共有名義不動産を売却する際には、以下のような費用と書類が必要になります。
売却にかかる費用
- 仲介手数料:
不動産会社に仲介を依頼した場合に発生する費用です。 - 印紙税:
売買契約書に貼付する印紙代です。 - 測量費用:
土地の境界が不明確な場合などに必要となることがあります。 - 各種税金:
- 譲渡所得税: 不動産を売却して利益が出た場合に課される税金です。所得税、復興特別所得税、住民税が含まれます。所有期間によって税率が異なります。
- 登録免許税: 所有権移転登記を行う際に発生する税金です。
- 消費税: 建物部分の売却には消費税がかかります(個人間売買は非課税)。
- 司法書士報酬:
登記手続きを司法書士に依頼した場合に発生します。 - その他:
抵当権抹消費用、残置物撤去費用など、状況に応じて発生する費用があります。
売却に必要な書類
共有不動産を売却する際には、共有者全員が協力して書類を準備する必要があります。
- 登記識別情報通知書または登記済権利証:
不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。 - 土地測量図及び境界確認書(土地の場合):
土地の境界が明確であることを示す書類です。 - 固定資産税評価証明書:
固定資産税の評価額が記載されており、譲渡所得税の計算などに使用します。 - 共有者全員の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)と住民票:
本人確認と住所確認のために必要です。 - 共有者全員の印鑑・印鑑登録証明書:
売買契約書や登記申請書に押印する実印とその証明書です。 - 委任状:
共有者のうち誰かが代表して手続きを行う場合や、専門家に依頼する場合に必要です。 - 物件に関する資料:
建築確認済証、検査済証、設計図書、修繕履歴など、物件の状況を説明するための書類です。
これらの書類は、売却方法や個別の状況によって追加・変更となる場合があります。事前に不動産会社や司法書士に確認し、漏れがないように準備を進めましょう。
共有不動産売却のトラブルを避けるには?
共有名義の不動産の売却に関するトラブルを避けるには、当事者間での話し合いだけでなく、専門家の力をうまく借りることが大切です。
共有不動産の売却で、何かしらお悩みを抱えている場合、ほとんどのケースで当事者同士での解決は困難です。
「不動産の活用方針をめぐって意見が割れている」「そもそも共有者が多すぎてどう話しを進めたらよいかわからない」このようなケースでは、無理に当事者同士で話し合いを進めようとせず、共有名義不動産に詳しい不動産会社や弁護士に相談するのが賢明です。
また、法律上は共有者の同意なしで、持分を売却できるとは言え、「売却した後に他の共有者とトラブルにならないだろうか…」とご不安に思う方も多いでしょう。
共有名義不動産に詳しい不動産会社であれば、トラブルなく持分を売却するためのノウハウや共有者とのトラブル解決について、サポートを受けることができます。
さらに、共有名義不動産を売却する際の税金や確定申告についても、専門的なアドバイスを貰えるため安心です。
共有持分の買取業者とのトラブルに注意
共有不動産を売却することになった場合、買取業者に買取を依頼する、あるいは仲介業者に仲介を依頼して購入希望者を探すといういずれかの方法を選択することになります。
仲介の場合、購入希望者が現れるのに時間がかかる可能性があります。
そのため、速やかに共有不動産を現金化したいと考えている人には、買取業者がおすすめです。
買取業者に依頼した場合は、買取業者がすぐに買い取ってくれるため、現金化までの時間を短縮できるというメリットが得られます。
しかし、買取業者は、不動産を安く買い取って高く売却することによって利益を得ているため、相場よりも買取価格が低いのが一般的です。
実際に共有持分の買取業者では、以下のようなトラブルが起きる可能性があります。
- 買取価格が相場よりも著しく低い
- 査定額の根拠が薄く、納得できない
- 担当者の専門性が低く、不動産取引を任せるのが不安
- 売却後、買取業者と共有者がトラブルになる
全ての買取業者が危険というわけではありませんが、悪質な買取業者に依頼した場合には損失を被ってしまうので注意しましょう。
買取業者が持分を買い取る目的は、安く買い取って高く転売するためです。買取業者の言いなりにならないために、自身の不動産や持分の相場がいくらか把握しておくのが良いでしょう。
また、共有持分を高く売りたい場合は、買取業者よりも仲介業者を選ぶのも一つの方法です。仲介業者は、高く買ってくれる購入希望者と売りたい人をマッチングさせてくれます。
共有持分を売却した後の注意点
共有持分を売却した後は、以下のようなリスクがあることを事前に理解しておくことが大切です。
新しい共有者との関係性
共有持分を購入した買取業者などが、他の共有者に対して持分の売却や買取交渉を行う可能性があります。
この場合、提示された金額に納得できれば売却を検討するのも一つの手です。
また、逆に自分が相手の持分を買い取って、完全な所有権を得る方法もあります。金額交渉は可能なので、希望額を提示して相手に検討してもらうことが大切です。
ただし、不動産会社は低価格で買い取ろうとする傾向があるため、納得できない条件には安易に妥協しないよう注意が必要です。
共有不動産の持分が第三者に売却されると、新たな所有者にはその物件に出入りする権利が発生します。場合によっては購入者が敷地内に入ってきて、物件の使用を始めることもあります。
不動産を活用する権利があるとは言え、見知らぬ人が急に共有者になるのは、トラブルの火種になり得ます。
突然の家賃請求や税金負担の問題
自分が共有不動産に住んでいる場合などは、持分の購入者から家賃分配の請求を受ける可能性があります。
また、法律上、共有名義不動産の固定資産税は、持分割合に応じて負担する必要があります。
今まで請求されなかった家賃や固定資産税を請求される可能性がありますが、これは法律上の決まりですので、持分割合に応じて支払うのが原則となります。
共有物分割請求のリスク
買取交渉が折り合わない場合、業者が「共有物分割請求」を提訴してくる可能性があります。この請求では、共有不動産を持分割合に応じて分割する手続きを進めます。
話し合いで解決できない場合、裁判(共有物分割訴訟)に発展することもあります。裁判では、物件の分割方法を裁判所が決定し、代償金を支払うか、強制的に物件を売却して現金で分配するケースが多いです。
このような場合は、早めに共有不動産に詳しい専門家に相談し、対応方法についてアドバイスを貰いましょう。
勝手に共有持分が売却されてしまった場合の対処法
もし他の共有者があなたの知らない間に持分を売却してしまった場合、すぐに状況を把握し、対応を検討する必要があります。
共有持分の買取業者や第三者が持分を取得している場合、権利関係が複雑になっている可能性があります。
場合によっては、新たな共有者から共有物分割請求訴訟を起こされる可能性もあります。
この事態に直面したら、早めに共有名義不動産に詳しい不動産会社や弁護士に相談しましょう。専門家は、今後のリスクを評価し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。
共有不動産を賢く売るためのポイント
相続発生時の「換価分割」
相続により不動産が共有名義になるのを避ける有効な方法の一つに「換価分割」があります。
これは、相続した不動産を売却し、その売却代金を各相続人の持分割合に応じて現金で分配する方法です。
これにより、不動産を共有名義にすることなく、公平に遺産を分割することができます。
居住者がいる場合のリースバック
もし共有不動産に他の共有者が居住している場合で、かつその共有者が売却後も住み続けたいと希望している場合は、「リースバック」を提案することも一つの方法です。
リースバックとは、不動産を売却した後も、その不動産を賃貸して住み続けることができるサービスです。
これにより、売却による現金化と、既存の居住者の居住継続という、両方のニーズを満たせる可能性があります。
共有名義のトラブルを未然に防ぐ方法
共有不動産に関する将来的なトラブルを避けるためには、事前に適切な対策を講じることが重要です。
遺産分割時に共有名義を避ける
相続によって不動産を取得する際、安易に共有名義にせず、遺産分割協議で単独所有者を決める、または「換価分割」を選択するなどの対策を検討しましょう。
これにより、将来的な意見の相違や管理の煩雑さを避けることができます。
共有物分割で共有状態を解消する
すでに共有名義となっている不動産がある場合でも、「共有物分割」によって共有状態を解消することが可能です。
話し合いによる分割(協議分割)がまとまれば、現物分割や代償分割(特定の共有者が不動産を取得し、他の共有者に金銭を支払う)といった方法で、共有関係を解消できます。
協議が困難な場合は、前述の「共有物分割請求訴訟」を検討することになります。
専門家への相談を検討する
不動産の共有に関する問題は、法律や税金、不動産取引の知識が複雑に絡み合います。
そのため、不動産の専門家(不動産会社、弁護士、司法書士、税理士など)に早期に相談することが、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな解決へと導くための最も効果的な方法です。
共有名義不動産売却のよくある質問
Q. 共有名義の不動産は全員の同意が必要ですか?
A. 共有名義不動産を全体売却する場合は、共有者全員の同意が必要です。
Q. 共有者が売却に反対している場合、どうすればよいですか?
A. まずは当事者同士で話し合いをすることが理想ですが、難しい場合は、専門家に相談の上、自己持分のみを売却する方法や、共有物分割請求訴訟を検討するのがおすすめです。
Q. 共有持分の売却に他の共有者の同意は必要ですか?
A. 不要です。自己持分の売却は、自分の意思のみで可能です(民法第206条)。
Q. 共有名義の不動産を売却するときの税金はどうなりますか?
A. 共有名義不動産や共有持分を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。これは、所得税、復興特別所得税、住民税の総称です。税率は不動産の所有期間によって異なります。詳しくは専門家にご相談いただくか、関連する税務情報を確認してください。
Q. 他の共有者が行方不明の場合でも売却できますか?
A. 共有持分のみであれば、行方不明の共有者がいる場合も売却可能です。全体売却の場合は、不在者財産管理人選任の申し立てなど、法的な手続きが必要となります。
Q. 他の共有者が物件に住んでいても売却できますか?
A. 他の共有者が居住中でも、自己の共有持分の売却は可能です。ただし、新たな共有者が住み込みを開始するなど、トラブルの原因となる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
Q. 他の所有者に共有持分を売却されたらどうしたら良いですか?
A. 共有持分の買取業者や第三者が持分を取得している場合、権利関係が複雑になっている可能性があります。場合によっては、新たな共有者から共有物分割請求訴訟を起こされる可能性もあります。早めに共有名義不動産に詳しい不動産会社や弁護士に相談しましょう。
Q. 売却代金の分配はどのように決定しますか?
A. 原則として、各共有者の持分割合に応じて按分します。共有者間で揉めないように、売却前に書面で取り決めをしておくのが良いでしょう。
Q. 共有名義の不動産の売却を進める際、必要な書類は何ですか?
A. 一般的には、登記済権利証(または登記識別情報通知書)、土地測量図及び境界確認書(土地の場合)、共有者全員の身分証明書と住民票、共有者全員の印鑑・印鑑登録証明書などが必要です。具体的な状況によって追加書類が必要になる場合がありますので、事前に専門家にご確認ください。
Q. 共有名義不動産を売却する際の注意点を教えてください。
A. 共有名義不動産を売却する場合、共有者との慎重な連携が不可欠です。途中で共有者間で意見が割れたり、売却代金の分配を巡ってトラブルになる可能性があります。共有不動産や共有持分の売却に詳しい不動産会社に仲介を依頼するなど、専門家のサポートを得ることを強くおすすめします。
Q. 離婚前に共有持分を売却することはできますか?
A. 可能ではありますが、住宅ローンの残債や離婚協議の進捗状況によっては、新たなトラブルの原因となる可能性があるため、おすすめではありません。まずは弁護士などの専門家に相談し、状況に応じた最適な解決策を検討することをお勧めします。
まとめ
共有不動産の売却は、共有者間の複雑な関係性や、法的な手続きが伴うため、単独での解決は困難な場合がほとんどです。
特に、以下の点に留意することが重要です。
- 全体売却には共有者全員の同意が不可欠であること。
- 自分の持分のみであれば、他の共有者の同意なしに売却が可能であること。
- 共有者が増えることで、将来的なトラブルのリスクが高まること。
- 共有持分を売却した後には、新たな共有者との関係性や、家賃・税金の負担、共有物分割請求といったリスクが潜んでいること。
- トラブルを避けるためにも、売却前に専門家へ相談することの重要性。
不仲で話し合いができない、一人の共有者が勝手に住み続けている、売却に断固反対する共有者がいる、家賃収入の分配が不透明で納得できない、自分は住んでいないのに税金を払わされている、何年も相続手続きが進まないなど、共有不動産に関するトラブルは多岐にわたります。
このようなお悩みを抱えている場合は、自己の持分のみを売却し、共有関係から離脱することも有効な解決策の一つです。
当社センチュリー21中央プロパティーは、あなたの共有持分をトラブルなく高く売却するサポート体制を整えています。
当社の最大の強みは、共有持分の高額売却を実現できる点です。他の共有者との意見の対立や、連絡が取れないといった理由で不動産全体の売却が難しい場合でも、ご自身の共有持分のみを売却することで、共有状態を解消することが可能です。
センチュリー21の広範なネットワークにより、約900名の購入希望者(投資家)を募ります。一斉入札により、競争原理が働き、あなたの共有持分を最高値で購入してくれる買主様とのマッチングを可能にします。
さらに、仲介手数料、相続登記費用、弁護士相談費用など、売却に伴うお客様の費用負担は一切ございません。
また、共有不動産に強い弁護士が社内に在籍しているため、共有者とのトラブルでお困りの方や、売却後のトラブルがご不安な方も安心してご相談いただけます。初回の面談から弁護士が同席し、売買契約書の内容確認、そして契約時の立ち会いまで、専門家が売却プロセスを徹底的にサポートします。
共有名義不動産のトラブル・共有持分のご売却でお困りでしたら、ぜひ一度、センチュリー21中央プロパティーにご相談ください。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。







