【2023年民法改正】相続と不動産の新ルールをわかりやすく解説
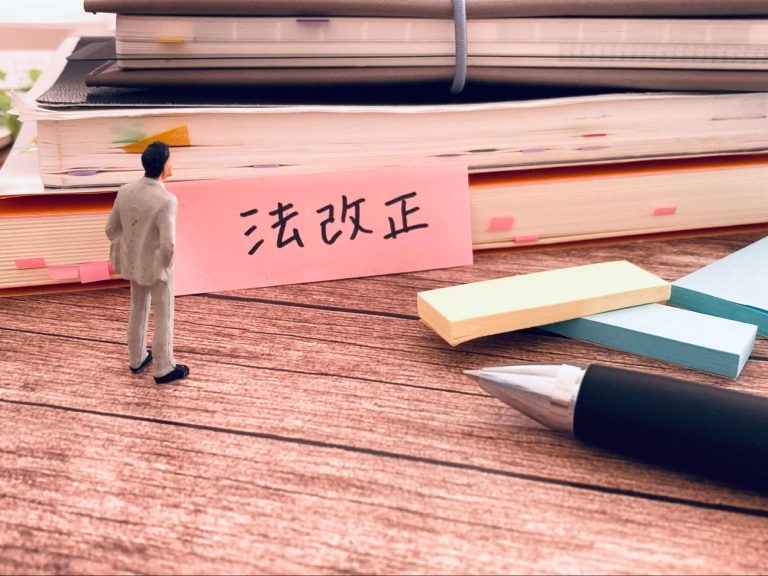
目次
2023年4月1日、私たちの生活に深く関わる民法のルールが改正され、特に相続と不動産に関する法律は大きく変わりました。
「親から相続した不動産が、他の兄弟との共有名義になっている」
「共有者と連絡が取れず、不動産の管理や売却ができずに困っている」
このようなお悩みは、決して他人事ではありません。
この記事では、2023年の民法改正で何が、どのように変わったのか、相続・不動産に関する重要な改正点をわかりやすく解説します。
遺産分割のルール見直しなど、あなたの資産に影響の大きい改正ポイントもありますので、ぜひ最後までご覧ください。
【なぜ変わった?】2023年民法改正の目的・背景
2023年の民法改正における最大の目的は、年々深刻化する「所有者不明の土地問題」の解決です。
所有者不明土地とは、登記簿を見ても所有者がわからなかったり、わかっても連絡がつかなかったりする土地を指します。
なぜ、このような土地が増えてしまったのでしょうか。
背景には、土地を相続しても活用予定がないなどの理由で、費用や手間のかかる相続登記(不動産の名義変更)が行われないまま放置されてしまうケースが多くあったことが挙げられます。
これまでは相続登記が義務ではなかったため、所有者が不明な土地が全国で増え続け、公共事業や災害復旧の妨げになるなど、大きな社会問題となっていました。
そこで、不動産関連の制度を見直し、所有者不明の土地を利活用しやすくすること、そして不動産の管理不全を予防・改善することを目指して、今回の改正が行われたのです。
また、相続関連の制度では、遺産分割に「10年」という一つの区切りを設ける仕組みが導入されました。
これにより、遺産が長期間放置され、所有者不明となる事態を防ぐ狙いがあります。
【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫
【いつから始まった?】新しいルールの施行日
2023年の民法改正の公布日と施行日は以下のとおりです。
- 公布日:2021年4月28日
- 施行日:2023年4月1日
公布日とは、新しい法律が成立し、国民に周知される日です。
そして、実際に法律の効力が生じるのは施行日である2023年4月1日以降となります。
ただし、改正内容によっては、過去に発生した相続にも影響するケースがあるため注意が必要です(詳しくは後述します)。
【ここが変わった!】各制度の改正ポイントを具体例で解説
2023年の民法改正では、主に以下の4つの制度や規定が見直されました。
- 共有制度
- 財産管理制度
- 相隣関係規定
- 遺産分割制度
これらは私たちの不動産や相続に直接関わる重要なポイントです。
それでは、これらの制度・規定ごとに、具体的に何が変わったのか、主な改正ポイントを確認していきましょう。
ポイント①:共有不動産の管理がしやすくなる?(共有制度の見直し)
共有制度とは、一つの不動産などを複数の人が共同で所有し、利用や管理を行うことです。相続によって、意図せず不動産が共有状態になるケースも少なくありません。
今回の改正では、この共有物の管理・処分に関するルールがより明確になりました。
具体的には、これまで共有者全員の同意が必要だった行為の一部が緩和されたのです。
例えば、共有物に対する軽微な変更(形状または効用の著しい変更を伴わないもの)を管理行為と明示し、持分の価格の過半数で決定できるようになりました。
また、これまで対応が難しかった、所在不明の共有者や賛否の判断をしない共有者がいた際の運用ルールが新たに定められ、共有物の利用や管理が円滑に進められるようになっています。
しかし、共有不動産の管理や処分をめぐっては、共有者同士の意見が対立し、依然として根深いトラブルに発展しやすいのが現実です。
【社内弁護士が常駐】共有不動産のトラブル解決はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫
ポイント②:所有者不明の土地問題はどうなる?(財産管理制度の見直し)
次に、財産管理制度の見直しについてです。
これは、所有者不明土地問題の解決に向けた重要な改正といえます。
これまでの財産管理制度は、行方不明になった所有者本人の全財産を管理するという、「人」を軸とした制度でした。
そのため、管理人の負担が大きく、また不動産に特化した管理がしにくいという課題がありました。
今回の民法改正では、新たに不動産(土地・建物)に特化した「所有者不明土地等管理制度」を創設しました。
これは、問題となっている特定の「不動産」を軸として管理を行う制度です。
これにより、財産すべてを管理するのではなく、必要な不動産のみを効率的に管理できるようになり、管理人の負担が軽減されます。
また、共有不動産の場合、これまでは所在不明の共有者ごとに管理人を選任する必要がありましたが、新制度では不動産に対して一人の管理人を選任すればよいため、より迅速な対応が可能になりました。
【4万件以上の実績】共有不動産のトラブル解決はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫
ポイント③:お隣さんとの境界トラブルが解決しやすく?(相隣関係規定の見直し)
ここでは、相隣関係規定の見直しについて解説します。
相隣関係とは、隣り合った土地の所有者同士の権利関係を調整するためのルールです。
この見直しの背景にも、所有者不明の土地問題が影響しています。
例えば、自宅の壁を修繕するために隣の土地の一部を使いたくても、その土地の所有者が不明では許可を得ることができず、工事が進められないといった問題がありました。
今回の民法改正では、こうした問題を解決するため、主に以下の2点が大きく見直されました。
- 隣地使用権の明確化
- 越境した枝の切除ルールの緩和
変更点1.隣地使用権の明確化
境界付近での建物の建築や修繕、境界標の調査・測量などの目的であれば、隣地所有者の承諾がなくても隣地を使用できることが明確になりました。
もちろん、無断で立ち入ることはできず、目的・日時・場所などを事前に通知する必要があります。
変更点2.越境した枝の切除ルールの緩和
隣の土地から木の枝が伸びてきて困る、というケースはよくあります。
これまでは、自分で枝を切ることはできず、隣地の所有者に切除を求めるしかありませんでした。
改正後は、以下のいずれかの場合には、自分でその枝を切り取ることができるようになります。
- 木の所有者に枝の切除を催告したにも関わらず、相当の期間内に切除しないとき
- 木の所有者が不明、または所在が不明であるとき
- 急迫の事情があるとき
さらに、ライフライン(ガス、水道、電気など)の設備を設置する際にも、必要な範囲で他人の土地を利用できる権利が明確化され、隣地所有者との関係悪化を防ぎながら、生活インフラを整備しやすくなるよう配慮された改正と言えます。
【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫
ポイント④:遺産分割がスムーズに進む?(遺産分割ルールの見直し)
最後に、最も重要な相続制度改正にともなう遺産分割ルールの見直しについて解説していきます。
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人同士で分け合う手続きのことです。
この遺産分割の話し合い(遺産分割協議)がまとまらずに滞ると、不動産の名義変更ができないまま次の相続が発生し、権利関係が複雑化して所有者不明土地を発生させる大きな原因となっていました。
改正前は遺産分割協議に期限がなく、長期間放置しても特定の相続人には不利益がなかったため、話し合いが進まない一因とされていました。
そこで今回の改正では、遺産分割を促進するため、以下の点で非常に大きなルール変更が行われました。
- 具体的相続分による遺産分割に期限を設定(10年ルール)
- 所在不明の相続人がいる場合の手続きを簡略化
変更点1.具体的相続分による遺産分割に期限を設定(10年ルール)
今回の改正で最も大きなポイントは、相続開始から10年を一つの区切りとし、遺産分割を促進する仕組みが導入されたことです。
原則として、相続開始から10年が経過すると、「特別受益(生前贈与など)」や「寄与分(特別な貢献)」を考慮した具体的な相続割合ではなく、民法で定められた法定相続分、または遺言による指定相続分を基準として遺産を分割することになります(民法第904条の3)。
つまり、被相続人から多くの援助を受けていた相続人や、介護などで特別な貢献をした相続人も、10年を過ぎるとそれらの事情が考慮されにくくなる可能性があるのです。
この改正は、施行日(2023年4月1日)より前に発生した相続にも適用されるため、注意が必要です。
ただし、すでに相続開始から時間が経っているケースのために、5年間の猶予期間が設けられています。
変更点2.所在不明の相続人がいる場合の手続きを簡略化
相続人の中に所在不明な者がいると、遺産分割協議が進められません。
そこで、相続開始から10年経過した場合、裁判所の許可を得ることで、所在不明の相続人の持分を取得したり、その持分も含めて共有不動産全体を第三者に売却したりすることが可能になりました。
これにより、売却できずに放置されていた不動産などの管理や活用がしやすくなるでしょう。
相続によって発生した共有持分は、しばしばトラブルの種となります。
今回の法改正を機に、ご自身の権利や不動産の状況を一度見直してみてはいかがでしょうか。
センチュリー21中央プロパティーでは、国家資格者である不動産鑑定士と連携し、複雑な共有持分の価値を客観的かつ適正に評価します。
AIも活用したダブル査定により、24時間以内にあなたの共有持分の査定額を知ることも可能です。
センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫
まとめ
本記事では、2023年4月1日に施行された民法改正の中から、特に相続と不動産に関する重要な新ルールについて解説しました。
- 共有不動産の管理ルールが緩和された
- 所有者不明土地に特化した財産管理制度ができた
- 隣地トラブルに関するルールが明確になった
- 遺産分割に「10年」という期限が設けられた
これらの改正は、長年社会問題となっていた所有者不明土地を減らし、不動産の適正な管理・利用を促進するためのものです。
特に、遺産分割の10年ルールは、過去の相続にも影響する可能性があるため、心当たりのある方は注意が必要です。
当社センチュリー21中央プロパティーは、共有持分を専門に扱う不動産会社です。
共有名義不動産に詳しい社内弁護士が常駐しているため、共有者とトラブルを抱えている場合や売却後のトラブルが不安な方にも、ご安心いただける体制が整備されております。
ご相談から査定、売却にかかる仲介手数料などの諸費用は原則0円です。
- 共有者と不仲で関係を解消したい
- 相続した不動産の活用ができていない
- 共有者が多すぎて話がまとまらない
- 自分の持分だけでも早く現金化したい
このような共有名義不動産でのお悩みは、4万件以上のトラブル解決実績を誇る当社へ一度ご相談ください。
専門スタッフが、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な解決策をご提案します。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。







