住んでいる家の相続を兄弟が行う場合の注意点
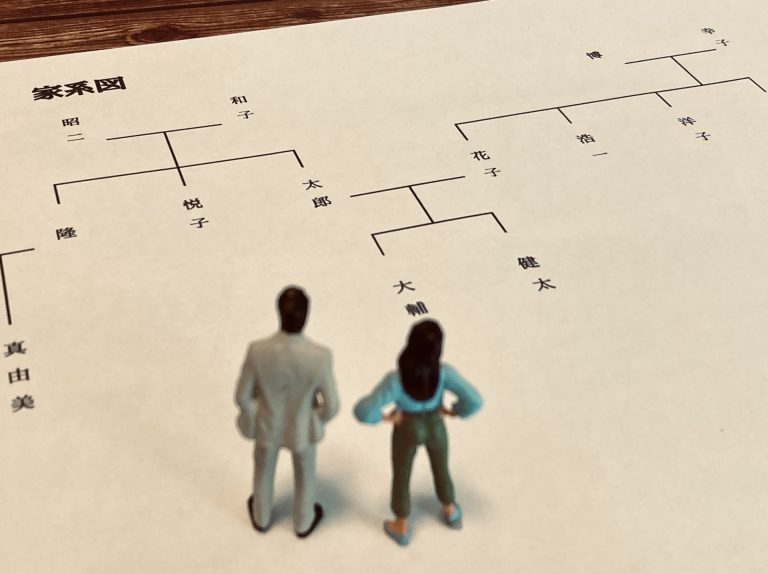
目次
「兄は住み続けたいようだが、自分の権利はどうなるのか」
「家族の思い出が詰まった実家を、どのように分けるべきか」
本記事では、まさにそうした「兄が住む実家を、弟である自分も相続する」というシチュエーションを想定し、住んでいる家の相続を兄弟姉妹で行う際の注意点や選択肢、起こり得るトラブルとその対策について、わかりやすく解説します。
まずは押さえておきたい相続の基礎知識
住んでいる家の相続を考える前に、まずは兄弟姉妹で相続を行う際の基本的な知識を押さえておくことが重要です。
法定相続分の考え方
法定相続人である兄弟が相続する場合、遺産を分ける割合は民法で定められています。
誰が相続人になるか(法定相続人)と、その割合(法定相続分)には優先順位があります。
| 相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
| 第1順位 (子がいる) | 配偶者 → 1/2 | 子供 → 1/2 ※人数で分割 |
| 第2順位 (子がいない) | 配偶者 → 2/3 | 親 → 1/3 ※人数で分割 |
| 第3順位 (子がいない) | 配偶者 → 3/4 | 兄弟姉妹 → 1/4 ※人数で分割 |
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、まずは配偶者が全体の2分の1を相続します。
兄弟が分けるのは、残った2分の1の遺産です。
この残りを兄弟の人数分で等分します。
ちなみに、被相続人の配偶者が既に亡くなっている場合は、兄弟が全財産を人数で等分して相続します。
被相続人に子供がいないとき(第一順位の相続人がいない場合)は、まず被相続人の両親(直系尊属)が相続人になりますが、その両親も既に亡くなっている場合は、第三順位である被相続人の兄弟が相続人になります。
遺言書の効力
民法では相続人の順位や法定相続分が定められていますが、被相続人が遺した遺言書がある場合はその内容が原則として優先されます。
つまり、兄弟が相続するときも、遺言書の内容次第では法定相続分通りに等分しないこともあり得るのです。
ただし、遺言書があっても、被相続人の配偶者、子、親には、法律上最低限保障された遺産の取り分である「遺留分」があります。
一方で、重要な点として、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。
そのため、「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書があれば、他の兄弟姉妹は基本的に遺産を受け取ることができないのです。
また、遺言書の効力を認めるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
自筆証書遺言で日付や署名の不備があったり、被相続人が正常な判断能力のない状態で作成したことが疑われたりすると、その遺言書は無効となる可能性があります。
相続登記の義務化と手続き
相続登記とは、被相続人の名義になっている不動産を相続人の名義に変えるための手続きです。
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。
この改正により、原則として、相続の開始があったことを知ってから3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
もし正当な理由なく期限を過ぎたうえに法務局からの催告にも応じない場合は、10万円以下の過料が科されることになります。
相続登記の手続きは複雑で専門知識が必要なため、司法書士などの専門家に相談して行うのが一般的です。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
住んでいる家を兄弟で相続する場合に選択できる4つの方法
家は現金と違って簡単に等分することができません。
そのため、相続にあたっては不動産を分割するいくつかの方法が用いられています。
相続した不動産を兄弟で分割する方法は、主に以下の4つです。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
共有分割それぞれメリットとデメリットがあるため、よく検討してから決めることが大切です。
分割方法①:現物分割
現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法です。
例えば、土地100坪を兄弟2人の相続対象とした場合、その土地を50坪ずつに分筆してそれぞれが取得するパターンなどです。
ただし、建物のように物理的に分割できないものや、分筆することで著しく価値が下がるような土地は、現物分割が難しい場合があります。
遺産の分け方がシンプルになりやすい点が、現物分割のメリットです。
分割方法②:換価分割
換価分割は、家を売却して得た現金を相続人同士で分配する方法です。
換価分割のメリットは、分割する対象が現金に変わるため、公平な分割がしやすい点です。
しかし、家を売却するには手間と諸経費(仲介手数料、税金など)がかかるため、相続手続きに時間を要する可能性がある点がデメリットとなります。
さらに、換価分割は家を手放すため、誰も住み続けることはできなくなります。
家族の思い出の詰まった家を売却することに、抵抗を感じる相続人もいるかもしれません。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
分割方法③:代償分割
代償分割は、特定の相続人が家を単独で引き継ぎ、その人が他の相続人に対して、自己の資産から代償金(法定相続分に相当する現金)を支払う方法です。
例えば、6,000万円の価値がある家を長男が相続し、その代わりとして次男は長男から現金3,000万円を受け取るといった形です。
このようにして、結果的に3,000万円ずつの遺産を分け合うことになります。
代償分割のメリットは、公平に遺産を分けられ、なおかつ家を売らずに済む点です。
家に住み続けたい相続人がいる場合や、思い出の詰まった家を手放したくない場合に適しています。
しかし、代償分割は家を引き継ぐ相続人が代償金を支払える十分な経済力を持っていることが前提の方法です。
もし代償金を用意できない場合、代償分割を行うのは難しいでしょう。
分割方法④:共有分割
共有分割は、一つの家を兄弟で分け合い、共有名義の形で所有する方法です。例えば、3人兄弟で相続する場合、家を所有する権利(持分)を3分の1ずつ分け合います。
共有分割のメリットは、家を売却することなく一見公平に分けられる点です。
しかし、共有分割にはデメリットも多く存在します。
共有分割は家の権利を分けるため、権利関係が複雑になりやすいです。
さらに、固定資産税などの費用負担や、家の維持管理についても共有者間で意見が分かれることがあります。
こうした理由から、共有分割はトラブルのリスクが非常に大きい方法と言えます。
共有分割を選択する際は、将来的なリスクも含めて慎重に検討するべきでしょう。
住んでいる家を兄弟で相続する際に起こり得るトラブル
住んでいる家を兄弟で相続する際に起こり得るトラブルとしては、以下の3つがあります。
- 遺産分割の方法に納得できず対立する
- 相続手続きが思うように進まない
- 共有分割を選んで身動きが取りづらくなる
トラブル①:遺産分割の方法に納得できず対立する
遺産分割協議において、相続人同士で遺産分割の方法や割合について意見が合わず、対立が生じることがあります。
例えば、家にそのまま住み続けたい相続人と、売却して現金化したい相続人の間で意見が割れるのはよくあるケースです。
それぞれの家庭の事情や家に対する想いが異なるため、簡単には合意に至らず、関係がこじれてしまうことがあります。
トラブル②:相続手続きが思うように進まない
相続手続きが円滑に進まないケースも多く見られます。
その主な原因は、相続人間のコミュニケーション不足です。
相続人全員が集まって話し合う機会が少ないと、情報の行き違いや誤解が生じやすくなります。
あるいは、家を売却して遺産を分割しようとしたものの、不動産市場の状況により家がすぐに売れないといった事態も起こり得ます。
このような場合、相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)との兼ね合いで焦りが生じ、相続人同士の関係が悪化する可能性もあります。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
トラブル③:共有分割を選んで身動きが取りづらくなる
先述した共有分割の方法を選択した場合、他の方法では起こらない深刻なトラブルに注意する必要があります。
共有名義の家は、共有者全員の同意がないと家全体を売却したり処分したりすることができません。
つまり、一人でも反対する人がいれば、売却や処分などは実行できないのです。
例えば、ある共有者が経済的理由で不動産全体を売却したいと考えても、他の共有者の同意が得られなければ実行できません。
さらに、もし共有者の一人が亡くなった場合、その持分がさらに枝分かれし、その人の相続人に引き継がれます。
共有持分が相続されるたびに、ねずみ算式に名義人が増えていく可能性があるため、権利関係が一層複雑になるのです。
相続時に兄弟同士で争いにならないために今からできること
住んでいる家の相続をめぐり兄弟間で争いになると、家族関係の悪化にもつながりかねません。
しかし、事前の準備や対策によって、多くのトラブルは回避できます。
相続時に兄弟同士で争いにならないために、親が元気なうちにできる具体的な対策としては、以下のものがあります。
- 遺言書を残してもらう
- 専門家に相続の相談をする
- 共有分割は絶対に避ける
トラブル対策①:遺言書を残してもらう
先述したように、相続では遺言書の内容が優先されます。
したがって、相続トラブルを防ぐ最も有効な手段の一つが、親に遺言書を作成してもらうことです。
相続内容を遺言書で細かく定めておけば、いざ相続するときに分け方で揉めるリスクも少なくなります。
ただし、遺言書にはいくつか種類があり、それぞれに決められたルールがあります。
適切な形式で作成されていないと遺言書が無効になるため、注意しましょう。
後のトラブルを避けるためには、専門家が関与し、原本が公証役場で保管される公正証書遺言が最も確実です。
遺言書の作成を検討する際は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の種類と特徴を、以下の表にまとめました。
【遺言書の種類とそれぞれの特徴】
| 種類 | 特徴 |
| 自筆証書遺言 | 被相続人が全文(※)、氏名、作成日付を自筆で書く遺言。 遺言には押印をする。 代筆や印刷は無効となる。※財産目録のみPC等の使用が可能 |
| 秘密証書遺言 | 被相続人が自分で作成する遺言。 公証役場や家庭裁判所で存在の証明を受ける。 遺言書は作成した本人以外は中身が見られない形で保管される。 |
| 公正証書遺言 | 公証人に作成してもらう遺言。 公証役場にて、2人以上の証人の立ち会いのもと作成される。 専門家が作成するため内容の不備が起きにくく、信頼性が高い。 |
トラブル対策②:専門家に相続の相談をする
相続をきっかけにトラブルが起き、兄弟仲が悪化してしまうケースは珍しくありません。
遺産の分け方や管理・処分方法について事前に十分な話し合いをしないと、相続時に揉めるきっかけになってしまいます。
トラブルを防ぐためにも、相続が発生する前に専門家に相談しましょう。
理想は、親が元気なうちに、子である兄弟姉妹も交えて、弁護士や税理士、司法書士のような相続に詳しい専門家に相談することです。
専門家に相談する際は、被相続人となる親の財産目録、相続人の関係図、遺言書の有無などの情報を事前に整理しておくと良いでしょう。
こうした情報があれば、より具体的で効果的なアドバイスを受けられます。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
トラブル対策③:共有分割は絶対に避ける
先述したとおり、共有分割にはデメリットが多く存在します。
共有名義の不動産は、相続人全員の同意がなければ不動産全体を売却できません。
したがって、不動産全体を処分したくても誰か一人でも反対すれば、それは実行できなくなってしまいます。
そして、もしも共有者の誰かと音信不通になれば、不動産全体の処分や活用に関する意思決定はほぼ不可能です。
連絡が取れない共有者がいる場合、法的手続き(不在者財産管理人の選任など)が必要になることもあり、さらに時間と費用がかかります。
一見平等に分割できるような方法にも見えますが、後々大きなトラブルのもとになる可能性が高いのが共有分割です。
トラブルを避けるためにも、不動産は単独名義で相続することをおすすめします。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
住んでいる家の相続を円滑に進めよう
今回は、兄弟で家の相続をする際の注意点を解説しました。
相続する遺産を兄弟で分けるときも、基本的な考え方は従来の相続とあまり変わりません。
しかし、住んでいる家は現金のように等分できないため、現物分割や換価分割、代償分割、そして共有分割のような方法で分けることになります。
不動産を共有名義で相続すると、活用や処分をめぐって将来的にトラブルになるリスクがあります。
センチュリー21中央プロパティーは、共有不動産の持分のみの売却を専門的にサポートしています。
一般市場での売却が難しいとされる共有持分も、不動産鑑定士による厳密な査定と、独自の買い手ネットワークを活用することで、お客様にとってより良い条件での売却を目指せいます。
共有不動産のトラブルや共有持分の売却に関するお悩み・ご不明な点がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。







