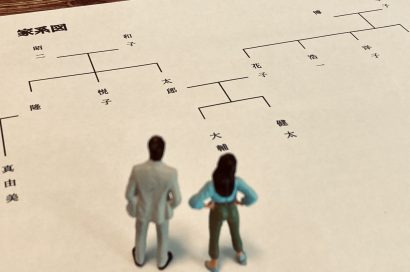相続税、兄弟でどう払う?個別申告と共同申告を税理士が解説
相続税、兄弟でどう払う?個別申告と共同申告を税理士が解説
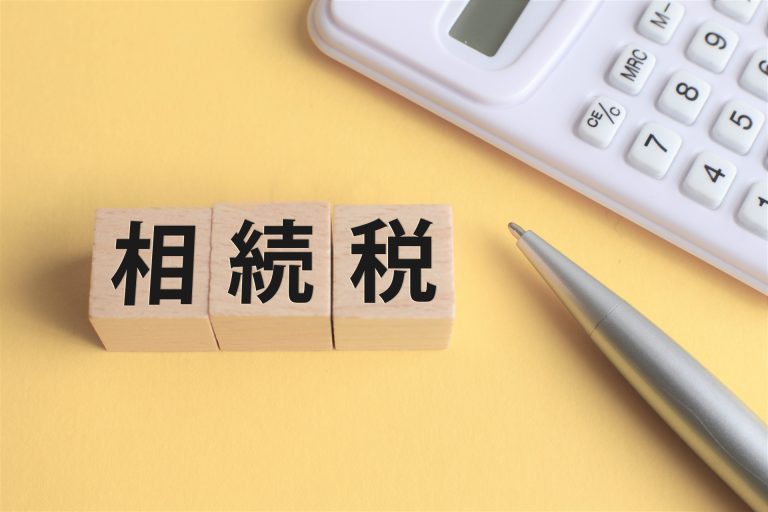
目次
複数人で不動産を相続することになった時、「相続税ってどうなるの?」「税金はそれぞれで払うの?」「共有名義にすると何か問題があるの?」といった疑問を抱く方は少なくありません。
相続は人生でそう何度も経験するものではなく、いざ直面すると専門知識が求められる場面が多々あります。特に、不動産が絡む相続や、兄弟など複数人で財産を共有するケースでは、税金や将来のトラブルを未然に防ぐための知識が不可欠です。
この記事では、税理士が、相続税の基礎控除から、兄弟で別々に相続税を支払う方法、共有名義で相続する際の注意点、そして相続税の共同申告について、わかりやすく解説します。

相続税の基礎控除とは?
相続税には、全ての相続人が恩恵を受けられる「基礎控除」という非課税枠が設けられています。この基礎控除額以下の相続財産であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が兄弟2人の場合、基礎控除額は 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円 となります。亡くなった方(被相続人)の遺産総額がこの4,200万円以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。
しかし、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。
相続税を兄弟で「別々に」払う方法
固定資産税とは異なり、相続税は連帯納付義務ではありません。これは、相続税が「各自の取得財産」に対して課される税金だからです。
相続税は、故人(被相続人)の遺産を、各相続人がどれだけ相続したか(取得した財産の価額)に応じて計算され、各自が納税義務を負います。
相続税を兄弟で「別々に」払う場合の流れ
- 遺産総額の確定: 故人の全ての財産(預貯金、不動産、有価証券など)の評価額を合計し、借金などの債務を差し引いて、課税対象となる遺産総額を確定します。
- 遺産分割協議: 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰がどれだけ相続するかを決めます。不動産を兄弟で共有する場合は、それぞれの持分割合もここで決定します。
- 各自の相続税額の計算:遺産総額から基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額となります。
この課税遺産総額を、法定相続分(または遺産分割協議で定めた具体的な相続割合)で仮に分けたものとみなし、これに相続税率を適用して「相続税の総額」を計算します。 - 各自が個別に納税: 算出された相続税額を、各相続人がそれぞれ期限内に税務署に申告し、納税します。兄弟がそれぞれ個別の納税義務を負うため、一方の兄弟が税金を滞納しても、もう一方の兄弟がその滞納分を肩代わりする義務はありません。
このように、相続税は兄弟がそれぞれ取得した財産に応じて計算され、各自が責任を持って納税する仕組みになっています。
共有で相続した際の注意点
相続財産に不動産がある場合、兄弟で「共有名義」にすることは珍しくありません。しかし、安易に共有名義にしてしまうと、将来的に思わぬトラブルに発展する可能性があります。
- 不動産の処分・管理における全員同意の原則:
- 売却には全員の同意: 共有名義の不動産を売却する際、共有者全員の同意が不可欠です。一人でも反対すれば、その不動産全体を売却することはできません。
- 大規模な修繕・管理の困難さ: 建物の大規模な修繕やリフォーム、賃貸に出すかどうかの判断など、不動産の管理に関する重要な決定も、原則として共有者全員の同意が必要となります。意見が対立すると、適切な管理ができず、不動産の価値が下がるリスクもあります。
- 税金・費用の負担をめぐるトラブル:
- 固定資産税の連帯納付義務: 先に述べた通り、固定資産税には連帯納付義務があります。もし一方の共有者が固定資産税を支払わない場合、もう一方の共有者が全額を支払う責任を負います。
- 経費負担の不公平感: 修繕費や管理費、火災保険料などの経費負担をめぐって、公平感がないと感じ、兄弟関係が悪化するケースも少なくありません。
- 将来の権利関係の複雑化:
- 共有者の一人に相続が発生すると、その持分がさらに次の世代(子供など)に相続され、共有者が増え、権利関係がより複雑になります。これにより、将来的に不動産を処分することが極めて困難になる可能性があります。
- 共有物分割請求のリスク:
- 共有者間の関係が悪化し、話し合いでの解決が困難になった場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起される可能性があります。裁判所の判断で、不動産を売却して代金を共有者で分ける(換価分割)ことになったり、特定の共有者が他の共有者の持分を買い取る(代償分割)ことになったりします。
こうしたリスクを避けるためには、相続時に安易に共有名義にするのではなく、「誰か一人が単独で相続し、他の兄弟には現金を渡す(代償分割)」、あるいは「不動産を売却して現金を分割する」といった選択肢も検討すべきです。
相続税の共同申告について
相続税の申告書は、相続人それぞれが作成し、個別に提出するのが原則です。これは、相続税が各自の取得財産に応じて課税されるためです。
しかし、実務上は、相続人全員が連名で一つの申告書を作成し、提出する「共同申告」という形が取られることが一般的です。
共同申告のメリット
- 手間と費用の削減: 各自がバラバラに申告するよりも、税理士への依頼費用や手続きの手間を削減できます。
- 計算ミスの防止: 複数の相続人で協力して計算を行うため、計算ミスや記載漏れを防ぎやすくなります。
- 整合性の確保: 相続人全員の情報を一つの書類にまとめるため、税務署側での確認作業もスムーズに進み、相続人全員の申告内容に矛盾が生じることを防げます。
- スムーズな税務調査対応: 万が一税務調査が入った場合でも、申告内容に統一性があるため、個別に調査されるよりも対応がスムーズになる可能性があります。
相続税の共同申告の流れ
相続税の共同申告は、複数の相続人が協力して一つの相続税申告書を作成し、提出する方法です。個別に申告書を作成するよりも、手間や計算ミスを減らせるメリットがあります。
共同申告の一般的な流れは以下の通りです。
- 遺産総額の確定と評価:
まず、亡くなった方(被相続人)が遺したすべての財産(プラスの財産・マイナスの財産)を正確に把握します。預貯金、不動産、株式、自動車、借金、未払金などをリストアップし、相続税評価額に基づいてそれぞれの財産を評価します。特に不動産の評価は複雑なので、税理士に相談することをおすすめします。 - 遺産分割協議と分割内容の決定:
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。誰がどの財産を、どの割合で相続するかを具体的に話し合い、遺産分割協議書を作成します。この協議書は、共同申告だけでなく、不動産の名義変更(相続登記)などにも必要となる重要な書類です。 - 相続税額の計算:
確定した遺産総額から基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を差し引き、課税遺産総額を算出します。この課税遺産総額を法定相続分で仮に分割したものとみなし、相続税率を適用して「相続税の総額」を計算します。 - 必要書類の収集:
相続税申告には、多くの添付書類が必要です。主な書類には、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、各財産の評価証明書(不動産の固定資産評価証明書、残高証明書など)があります。 - 相続税申告書の作成:
収集した情報と計算結果に基づき、相続人全員で相続税申告書を作成します。共同申告では、相続人全員の取得財産や税額が1つの申告書にまとめられます。 - 申告書の提出:
作成した相続税申告書と必要書類一式を、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。提出期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税などが課される可能性があるため注意が必要です。 - 相続税の納税:
各相続人は、算出した自身の納税額を、申告書の提出期限と同じ10ヶ月以内に、銀行や郵便局、またはe-Taxなどを利用して納税します。共同申告であっても、納税は各相続人が個別に行います。
相続税の申告は専門的な知識が求められるため、多くの場合、税理士のサポートを受けることで、正確かつスムーズに進めることができます。
共同申告を行う場合でも、納税自体は各自が個別に行います。共同申告は、あくまで申告書作成・提出の手間を軽減するための実務上の方法と理解しておきましょう。

まとめ:共有不動産のお悩みはセンチュリー21中央プロパティー
相続は、財産の承継だけでなく、家族間の関係性にも深く関わるデリケートな問題です。特に不動産が絡む場合や、兄弟など複数人で共有するケースでは、税金や将来のトラブルを避けるために専門的な知識が不可欠です。
当社センチュリー21中央プロパティーは、共有不動産に関するお悩みやトラブル解決をサポートしています。兄弟で相続した不動産を売却したい、自分の持分だけ売ったらいくらになるのか知りたい、といった方は、ぜひご相談ください。

この記事の監修者
税理士
税理士。東京税理士会品川支部所属。日本税務会計学会訴訟部門所属。福島健太税理士事務所代表。不動産デベロッパーから税理士に転身した経歴をもつ不動産と税のスペシャリスト。共有持分で不動産を相続される方が相続税を相談する税理士として多くの顧客を得る。趣味は釣り。