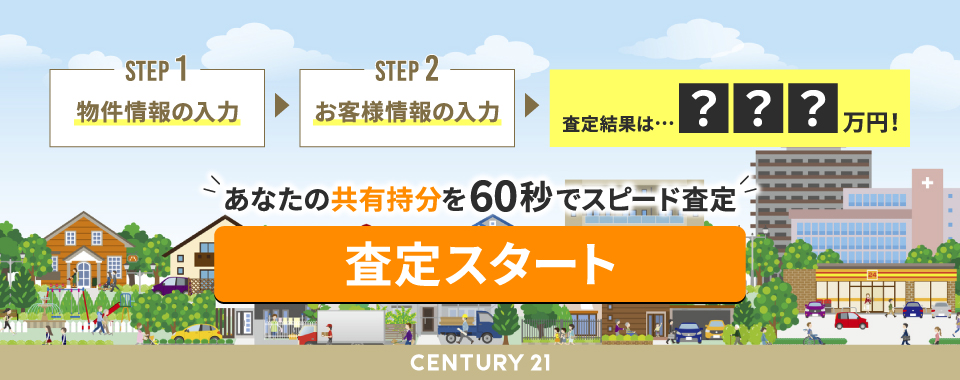離婚時の財産分与と不動産の売却をどう考えるべきか|共有持分の売却・買取
離婚時の財産分与と不動産の売却をどう考えるべきか
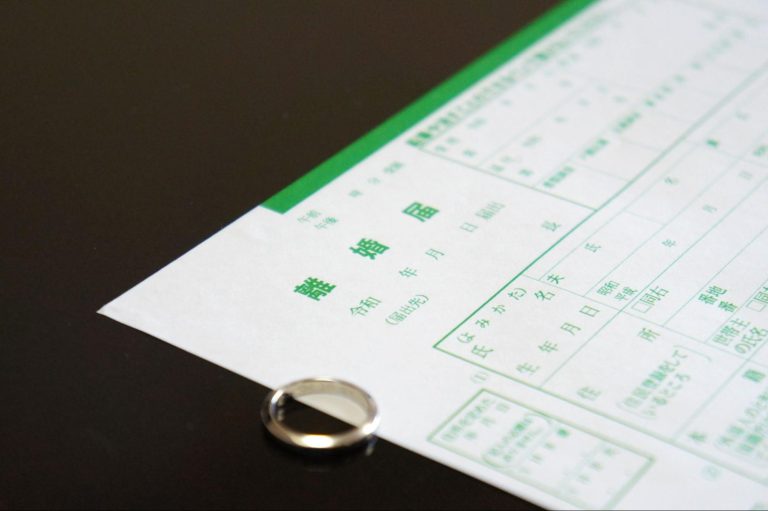
不動産売却時に多いのは、離婚が原因のトラブルです。
離婚時の不動産の扱いは、単独名義で購入した場合でも、原則財産分与で2分の1ずつに分ける必要があります。
しかし、不動産は簡単に分割できないため、お互いの主張がまとまらずトラブルに発展する傾向にあります。
そこでこの記事では、離婚時の財産分与、特に不動産の分与と売却について詳しく解説します。
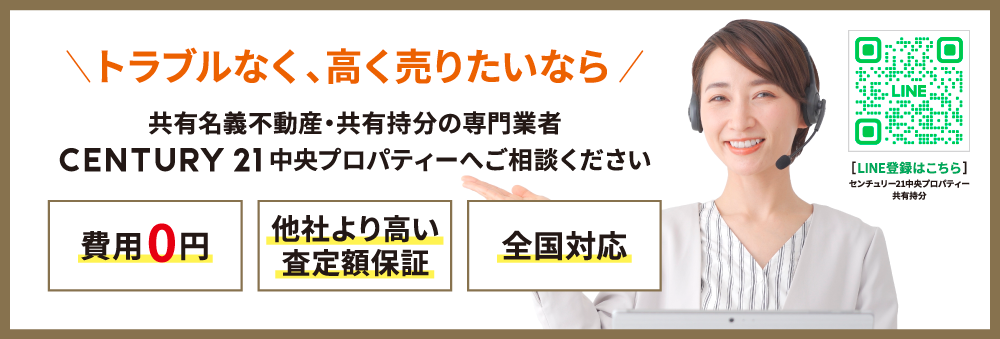
1.財産分与とは
財産分与とは、離婚した夫婦のそれぞれが、財産の分割を請求できる制度のことです。
財産分与の請求は民法第768条1項で定められ、双方でしっかりと取り決めをする権利があるため、うやむやにはできません。
財産分与の請求では、以下の3つの状況を考慮して決定します。
- 夫婦が共に築いた財産を公平に分配すること
- 離婚後の相手方の生活を保障すること
- 離婚の原因を作った相手への損害賠償の性質があること
財産分与の割合は原則2分の1とされており、上記の内容をもとにまずは当事者間の協議によって決めるのが通常です。当事者間で協議が進められない場合は、家庭裁判所に対して申し立てて決めます。
ただし、離婚から2年以内に財産分与をする必要があります。
1-1 財産分与の種類と対象
財産分与は、図1のように3種類に分けられます。
一般的に財産分与と言えば、清算的財産分与を指します。たとえ専業主婦であっても、家庭内の家事や育児などの労働をして貢献しているため、清算的財産分与が受けられます。
また、財産分与には対象となる財産とならない財産があります。
住宅ローンやそのほかの借金なども、マイナス財産として財産分与の対象になりますが、どちらかが個人的に作った借金は共有の財産には含まれません。
それぞれが個人で所有する財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象外です。そのため、個人的に作った借入などの負債も共有財産にはならず、特有財産になります。
1-2 不動産の財産分与方法
不動産は、清算的財産分与に該当します。
婚姻中に購入した土地や住宅は、お互いの協力によって得た資産です。そのため、離婚時には不動産を財産分与で2分の1に分割する必要があるのです。
2.離婚時の共有名義不動産はどうなるのか
離婚が原因で共有名義の不動産を売却する際に注意すべきなのが、離婚前と離婚後で対応が変わることです。
離婚前の共有持分の処分は、売却に相手の同意も必要なことを踏まえて確認してください。
2-1.離婚時に最も多い不動産売却の悩みとは
離婚時の不動産売却で、当社へ相談にこられた方43名へアンケート調査を行ったところ、一番の悩みが「相手方が売却を認めず居座る」という回答でした。
離婚すると、どちらか一方はそのまま家に住み続けるケースが多いのが現状です。
そして、共有持分の全体売却の場合は、お互いの同意がないと売却できないため、相手方が同意しない限り売却に踏み出せません。
共有持分で不動産を所有している方は、相手を説得する必要があると覚えておきましょう。
2-2.離婚前に自己持分のみ売却できないのか
離婚前の持分売却は、相手の合意が必要になります。
勝手に自分の持分を売却すると、権利濫用で大きなトラブルに発展します。
離婚前に売却するか離婚後に売却するかは、お互いの考えも考慮したうえで慎重に決めなければなりません。
例えば、離婚前に不動産を売却して現金化すると、財産分与でのお互いの取り分がはっきりします。売却までには時間がかかることも多いため、売却が完了するまでは婚姻関係を続けなければなりません。
また離婚後に売却する場合で住宅ローンが残っていると、売却までの住宅ローンを払い続けなければなりません。また、住宅は年数が経つほど価値が減少するので、なるべく高く売りたいなら、早めに売却するのが鉄則です。
但し、離婚協議が終盤を迎えている場合、持分のみの売却ができる可能があります。共有持分の売却を専門に扱う当社へ一度ご相談ください。
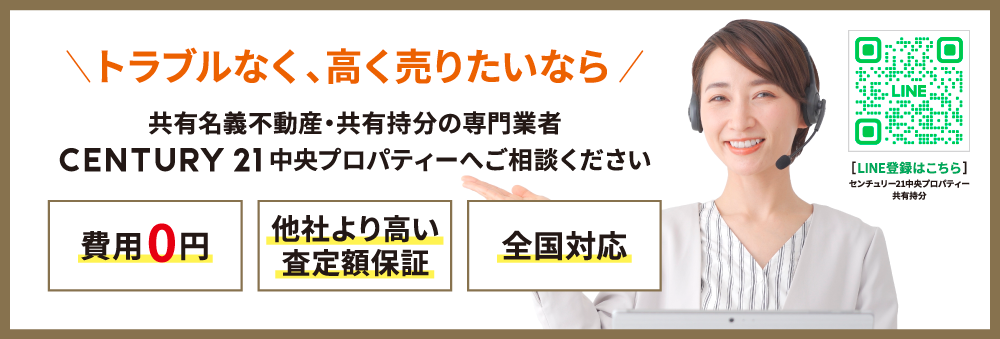
2-3.離婚時の不動産の扱いは4つ
家(住宅)の財産分与は、夫婦で2分の1ずつに分けるのが原則です。
ただし、現金のように簡単に2分の1にできないため、分けるには以下の4つの方法から選択します。
- 代償金で清算する
- 共有名義で所有し続ける
- 分筆して単独名義にする
- 売却して現金化する
それぞれ詳しく解説します。
①代償金で清算する
夫婦のどちらかが不動産を取得して、相手に不動産価値の半額を代わりに「代償金」として支払うことで財産分与を成立させる方法です。
不動産をどちらか一方が取得するだけでは不公平になります。そのため、一方が不動産を取得するのであれば、不動産価値の半額分を現金で支払い、公平な財産分与を可能にします。しかし、不動産を受け取る方が代償金を支払うだけの手持ち金を保有しているのが前提です。
②共有名義で所有し続ける
共有名義とは、不動産をどちらか一方が所有するのではなく、二人で一緒に所有することです。不動産を共有で所有するのは、家族や身内でなくてもできるため、離婚後も二人で一つの不動産を所有できます。
共有名義のメリットは、代償金を支払うお金がなくても財産分与ができ、それぞれが2分の1ずつ公平に財産を所有できることです。
注意点として、売却や増改築などの不動産の管理や処分が困難になります。例えば、共有不動産全体を売却する際には、共有者全員の同意が必要です。
売却したいと考えても単独の意思では売却できず、相手の同意を得る必要があります。
共有名義にする場合は、離婚後にも不動産管理のリスクがあることと、何よりも離婚手続きを終えた他人同士が引き続き共有関係になってしまうことのリスクを考慮しておきましょう。
③分筆して単独名義にする
分筆とは1つの土地を2つ以上に分割することで、「土地」を所有している場合に有効な方法です。そのため、分割できない戸建て住宅やマンションでは使えません。
分筆して夫婦それぞれが土地を所有すると、共有名義にならずにお互いが単独で不動産を所有できます。また、代償金を支払うだけのお金がない場合にも活用できる方法です。
しかし、土地は必ずしも綺麗な正方形をしているわけではありません。そのため、おおむね均等に分筆しても、多少の大きさの違いが現れます。
また、元々の土地の形によっては、分筆後の土地形状がいびつになり、不動産価値が下がる可能性も考えられるでしょう。
地域によっては、住宅建築の際に最低敷地面積が設けられている場合もあります。分筆した結果、最低敷地面積を下回ると、今後建物が建てられない土地になり不動産の利用価値が大きく下がってしまいます。
分筆する場合は、不動産価値が下がるリスクを考慮し、元の土地形状や大きさから、分筆後にも価値があるかを事前に確認しましょう。
④売却して現金化する
不動産の財産分与で、最も選択されるのが売却して現金化する方法です。
現金であればその場で綺麗に分割でき、トラブルが発生する可能性が低いからです。また、売却してしまえば、代償金の支払いもなく共有持分によるトラブルもありません。
売却する際は不動産会社に依頼する必要があるため、仲介手数料や登記費用などの初期費用がかかると覚えておきましょう。売却時の経費を差し引いた現金を、それぞれで分割します。
3.離婚時の不動産の財産分与の進め方
不動産の財産分与では、次の4つのステップで進めます。
- ローンの有無と残債の確認
- 各名義人の確認
- 不動産の評価額調査
- 財産分与の合意書(離婚協議書)の作成
流れを詳しく解説します。
3-1 ローン有無と残債の確認
まずは、住宅ローンの残債を確認します。なぜなら、住宅ローンが残っていると、不動産の所有権を移転できず売却できないからです。
また住宅ローンは負債になるため、ローン自体もお互いの財産という考え方になります。
住宅ローンの残債を確認するには、ローンの返済計画書や残高証明書を確認してみましょう。
固定金利の場合は、ローン借入時に返済計画書をまとめて受け取っている可能性があります。変動金利の場合は半年ごとに金利の見直しが行われ、見直し後に返済表が届くので、手元にある書類で確認してみましょう。
ネット銀行であれば、インターネット上で住宅ローンの返済状況を確認できます。
ローンの残債額によって、アンダーローンまたはオーバーローンという状態になります。
アンダーローンとは、ローンの残債額よりも売却額の方が大きく、ローンを完済できる状態のことです。
一方でオーバーローンは、売却額よりも住宅ローンの残債額が大きく、完済できない状態を指します。
アンダーローンであれば、不動産を売却でき、さらに手元に残ったお金は財産分与できます。
オーバーローンの場合は、「自己資金で清算する」または「任意売却で家を手放す」という方法で対応可能です。
3-2 名義人の確認
続いて、名義人の確認を行います。
名義人を確認する理由は、もしも売却になった場合に不動産の名義人しか売却手続きを進められないからです。
名義人は単独、あるいは夫婦共有の場合があります。夫婦の共有名義であれば、お互いの同意がなければ売却できないため、あらかじめ確認しておく必要があります。
勘違いされやすいのが、住宅ローンが共有名義の場合に、家自体の持分も共有名義であると思われるケースです。実際には、住宅ローンの名義人と家自体の名義人は同一とは限らないので注意しましょう。
3-3 不動産の評価額調査
続いて、不動産の価値を確認します。財産分与で2分の1にするには、所有する不動産の価値を把握する必要があります。
不動産の評価額を調べるには、不動産会社に査定依頼するのがおすすめです。
査定金額は不動産会社によって異なることが多いため、数社で査定額を比較しましょう。たとえ査定額が高くても、買主が見つからず売れなければ意味がありません。そのため、不動産査定では、金額だけで判断するのではなく、査定金額の理由を確認し、複数社を比較するのが大切です。
また、現在では評価額調査にAI査定を導入し、過去の事例などから素早く価格を把握することも可能です。当社もAI査定を活用した不動産査定を導入しておりますので、興味がある方は、ぜひ活用してください。
3-4 財産分与の合意書(離婚協議書)作成
最後は、財産分与の合意書の作成を行います。
例えば、どちらが家に住むのかを決めたり、相手方は代償金の支払いが可能なのかを確認したりします。
双方が家を手放したい場合や、代償金を支払うだけのお金を所有していない場合には、家を売却する方法を検討しましょう。
話し合いの結果、財産分与の方法について合意できたら、離婚協議書などの合意書を作成し、その書類の内容に従って家の財産分与を進めます。
4.名義変更と売却の流れ
名義変更を含めた不動産売却の流れは、以下の通りです。
- 不動産会社へ売却を依頼する
- 媒介契約の締結
- 売却活動(買い手探し)開始
- 売買契約を締結
- 不動産所有者の名義変更
- 決済(売却額のお支払い)
- 物件の引き渡し
それぞれ詳しく解説します。
①不動産会社へ売却を依頼する
不動産を売却するには、最初に不動産仲介会社に依頼する必要があります。
売却依頼をすると、不動産の査定金額が提示されます。ただし、不動産会社によって査定額に差が出ることも少なくないため、複数社に査定依頼して、金額と査定ポイントなどを比較しましょう。
②媒介契約の締結
売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。
媒介契約とは売主と不動産会社との間で取り交わす契約のことで、売却活動の報告や売却成功時の報酬に関する取り決めを行います。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があるため、所有不動産に適した媒介契約を結ぶようにしましょう。
媒介契約を締結しても、買主との売買が成立しなければ報酬を支払う必要はありません。
③売却活動(買い手探し)開始
売却活動では不動産会社がチラシを配布したり、ネット広告を打ち出したりと売却のための活動を行います。
売主が行うのは、購入希望者が現れた際の内覧対応や物件の説明などですが、ほとんどの場合、不動産仲介会社がそれらを代行しておこないます。
④売買契約を締結
買主が決まれば、売買契約を締結します。
売買契約は買主と売主だけではなく、買主側仲介会社と売主側仲介会社がそろい契約を進めます。契約書関係は売主側の仲介会社が準備することが多く、売主は出来上がった契約書の内容に事前に目を通し不備がないか確認しましょう。
当日は、売主と買主で読み合わせを行い、問題なければ署名・捺印します。
⑤不動産所有者の名義変更
不動産を買主に引き渡す時には、所有権移転登記(名義変更)をする必要があります。原則的には、売買代金を決済する当日に司法書士立ち会いのもと名義変更を行います。
名義変更には、住民票や印鑑証明書、登記簿謄本、固定資産評価証明書などの書類が必要です。書類を集めるのに時間がかかる場合もあるので、決済当日に慌てずに済むように前もって準備しておきましょう。
必要書類に関しては、あらためて不動産仲介会社に確認してください。
⑥決済(売却額のお支払い)
決済では、買主から売主に対して売買代金を支払います。
基本的には売主・買主・不動産会社・司法書士・金融機関担当者で金融機関に集まり、決済を行います。もしも売主側の住宅ローンが完済できていない場合は、同時に融資先の金融機関を通して、返済を行うことを覚えておきましょう。
⑦物件の引き渡し
基本的には決済当日に売主と買主の双方で物件に向かい、引き渡し(住宅の場合は鍵の受け渡し)を行います。
ここまで完了すると、売主と買主はそれぞれの不動産仲介会社へ報酬として仲介手数料を支払います。
まとめ
この記事では、財産分与について詳しく解説しました。
なるべく離婚前に話し合いを行い、離婚後はトラブルに発展しないように財産分与の方法を決めておくことをおすすめします。
センチュリー21中央プロパティーでは、離婚した後であれば持分の売却も可能です。独自の高額売却システムがあるため、持分売却をご検討の方は、ぜひご相談ください。
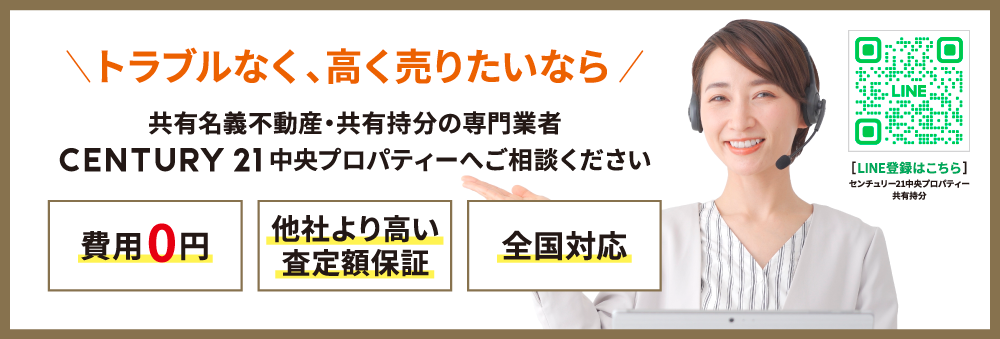
この記事の監修者
社内弁護士
当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。