共有持分のメリット・デメリットから売却方法まで解説
共有持分とは?共有持分のメリット・デメリットを徹底解説

目次
不動産を兄弟で相続した場合や夫婦でマイホームを購入する場合、安易に共有名義にすると後々大きなトラブルに繋がる可能性があります。
この記事では、共有持分のメリットデメリットやよくあるトラブルについて解説します。
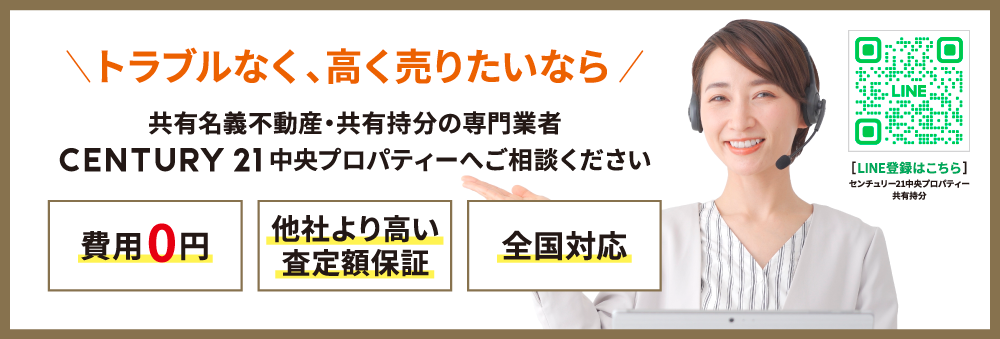
共有持分とは?
共有持分とは、一つの不動産を複数人で所有する際の所有権割合のことです。
所有権割合は、不動産購入時であれば出資額、相続による取得であれば、法定相続分や遺産分割協議等によって決まります。
注意したいのはあくまで共有持分は権利の割合であり、実際の不動産における面積などではないということです。
権利自体は、割合に関係なく不動産全体に及びます。
そのため、不動産を売却するなどといった場合は、所有権を持っている全員の同意を得る必要があるのです。
共有持分の売却に共有者の同意は不要!
先述した通り、共有名義不動産を全体売却するには、共有者全員の同意が必要です。(民法第206条)
そのため、一人でも売却に賛同しない者がいると、売却できないということです。
しかし、自己持分のみであれば、他の共有者の同意や承諾なく売却できます。
不動産全体の売却に反対する共有者がいる場合は、自己持分の売却を検討してみると良いでしょう。
あなたの持分はいくらで売れる?今すぐ査定結果をメールで受け取る ≫
共有持分のメリット・デメリット
ここでは、共有持分におけるメリットとデメリットについて解説します。共有持分におけるメリットとデメリットをしっかり理解して、共有持分とすることが自分にとって果たして良いのかよく考えてみましょう。
共有持分のメリット
共有持分のメリットは、主に3つです。
- ローンが組みやすくなる
- 相続税の節税になる
- 税金の控除が受けられる
①ローンが組みやすくなる
不動産は高い買い物ですから、通常の場合はローンを組んで購入します。ローン審査が通るかは、契約者の収入や資産などにより決定。そのため、ある程度安定した収入がないとローン審査は通りません。
そこで登場するのが、共有名義による購入です。分かりやすい例が、夫婦で家を買う場合。共働きで夫も妻も働いているのであれば、ペアローンなどを活用することで審査が通りやすくなります。
②相続税の節税になる
不動産の所有権を持つ人が死亡した場合、相続税が発生します。相続税は不動産の評価額に対して計算が行われるのですが、共有名義であれば共有持分の割合が課税対象となるのです。例えば評価額5000万円の不動産を夫婦で50%ずつ共有持分として持っていたとします。このとき夫が死亡すると妻に相続され相続税がかかってきますが、夫の共有持分は50%ですから2500万円が課税対象となるのです。
③税金の控除が受けられる
確定申告ではいろいろな控除が用意されていますが、注目したいのは住宅ローン控除です。年末の住宅ローン残高から0.7%の金額を控除できるという制度で、例えば共働き夫婦が共有名義で住宅ローンを組んでいれば夫婦の両方が住宅ローン控除を受けられることになります。
また、居住用財産を売却する場合3000万円の控除ができるのもポイント。住宅ローン控除同様、夫婦の共有名義で所持している不動産であれば双方3000万円の控除を受けられるため、合計で6000万円も控除できるわけです。
共有持分のデメリット
共有持分のデメリットは、主に以下の2つです。
- 自由に売却できない
- 共有者とトラブルになる可能性がある
①自由に売却できない
共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員が売却に同意する必要があります。そのため、すぐに手放したいと思っていても、全員の承諾を得られない限り売ることはできません。ただし、自身の共有持分そのものは個人の判断で売却することが可能です。その場合、共有持分に応じた金額になるので、不動産全体を売るよりも低くなってしまうことに注意しなければなりません。
②共有者とトラブルになる可能性がある
共有持分は、相続の対象になります。
しかし、長年共有状態が続き、相続が複数回発生すると、誰と共有状態なのか分からなくなってしまう恐れがあるので注意しなければなりません。
また、共有者と連絡が取れないケースも多く、その場合は共有者の同意を得るための意思確認ができず、売却や建て替えなどが難しくなります。
共有持分のトラブル事例
共有名義についてのメリット・デメリットをご紹介しました。共有名義にすることは、価格の高い不動産であってもローンが組みやすくなる可能性があるなど、一見メリットが多いように感じられるかもしれません。
しかし、共有名義人が複数いるということは、所持している不動産に対して人間関係が複雑に絡んでくるかもしれないということでもあります。人間関係が発生してくる以上、何らかのトラブルが絶対に起こらないとは言い切れません。さらに、購入から時間が経っている不動産の場合、権利関係が複雑になってしまうこともあるなど、トラブルの発生する可能性は高くなる可能性があるでしょう。
ここでは、共有持分があることでどのようなトラブルが考えられるのか具体的にご紹介していきます。
①共有持分を持つ1人が不動産を利用しているとき
所有権は共有持分を持つ全員が持っているわけですから、そのうちの誰が不動産を使用しても問題はありません。しかし、ほかの共有者に断りなく住み続けている、家賃を支払っていないといったように、ほかの共有者の権利を害するような場合はトラブルになりやすいです。
②不動産の活用や処分で意見が割れるとき
不動産にはさまざまな活用方法があります。人を住まわせて家賃収入を得たい、別荘として利用したい、売却したいなど、人によって考えは異なるでしょう。ですが共有持分がある場合、その不動産の利用方法を決めるためには共有持分の割合が全体の過半数以上になるように、売却の場合には全員の同意を得なくてはいけません。
例えば、A、B、Cが共有名義で住宅を所持している場合、Aが共有者であるB、Cの同意を得ず住宅を賃貸として第三者に貸し出していたとします。本来同意を得るべきところを無視してAの独断で行っているため、BとCは第三者に退去するように指示できるのです。
例のようなケースでは、Aは第三者から損害賠償を請求される恐れもあります。たとえ解決しても、今後の関係は良くはならないでしょう。
共有持分を売却する方法
共有持分の売却先は、以下の二つです。
- 第三者へ持分を売却する
- 共有者へ持分を売却する
ここでは、共有持分を第三者に売却する場合にフォーカスして解説します。
共有持分の専門業者のちがい
共有持分は、通常の不動産とは異なり、権利関係の把握や共有者との紛争など、慎重に対応しなければなりません。
そのため、共有持分専門の業者に相談するのが一般的です。
共有持分の専門業者には、大きく2つの種類があります。
- 買取業者
- 仲介業者
それぞれの特徴を解説します。
買取業者
その名の通り、業者に共有持分を買い取ってもらう方法です。提示された価格に売主が納得いけば、売買は成立します。売主と業者のやりとりで完結するので、時間や労力はあまりかかりません。ただし、業者もその後売却などで利益を出すために買い取るわけですから、買取価格は低くなることが多いので注意が必要です。そのため業者の提示価格次第では契約が成立せず、いつまで経っても手放せない可能性があることは理解しておきましょう。
仲介業者
個人から個人への売却方法になりますが、自分に代わって業者に買い手を探してもらう方法です。業者が広告などを出して買い手を探してくれるため、労力が軽減されます。業者に支払うのは、仲介手数料です。そして、売却が成功すると売却代金が売主に入ります。買い手は個人になるので、適切な相手が見つかるまで時間はかかってしまうかもしれません。しかし、売却価格は売主が決められるため、うまくいけば買取よりも高い売却金額になるケースが多いのです。
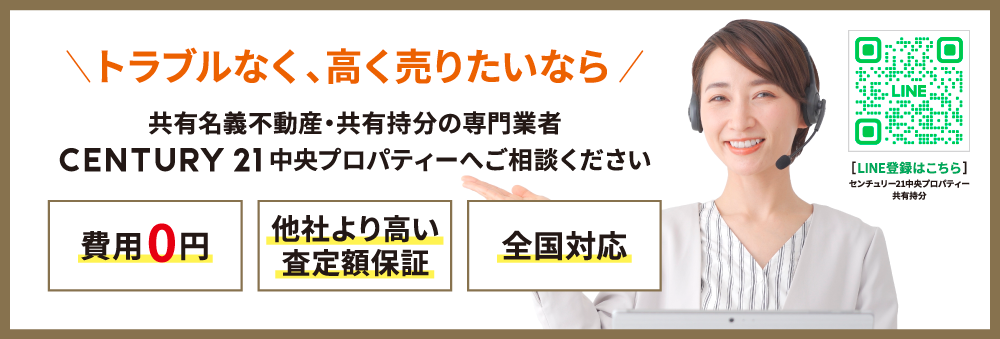
共有持分売却時の注意点
共有持分を売却する際は、以下の点に注意しなければなりません。
残りのローンがないか確認する
ローンを組む際に抵当権などの担保を設定していた場合には、売却時に残りの金額を一括で支払わなくてはいけない可能性があります。売却したのは良いものの、ローンの残金を一括で請求されてしまったといった事態になる可能性も否定できません。こうしたことが起こらないようにするためにも、不動産に対してローンの支払いがまだ残っている場合は、今後どのようにするのか事前に銀行と相談しておくことが大切です。
売却した年の確定申告は必ず行う
共有持分の売却によって得られた代金は、譲渡所得に分類されます。そのため、確定申告で所得を申告する必要があることに注意しなければなりません。申告漏れがあったり、確定申告をそもそもせずにいたりすると、後日税務署の調査が入り、延滞税や無申告加算税など追加で納税を求められるといったペナルティが発生することになります。より多くの税金を払わなくてはいけなくなるので、売却したら忘れずに確定申告を行うことを覚えておきましょう。
まとめ
不動産を共有で所有することは、夫婦で住宅を購入する際や節税などに効果的です。
しかし、相続が発生し共有関係が複雑になることで、トラブルになりやすいデメリットもあります。
共有持分の売却をご検討の方は、中央プロパティーへご相談ください。
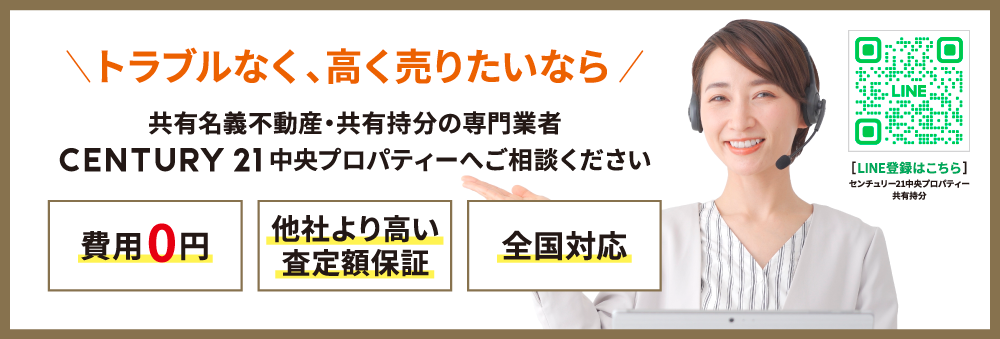
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。







