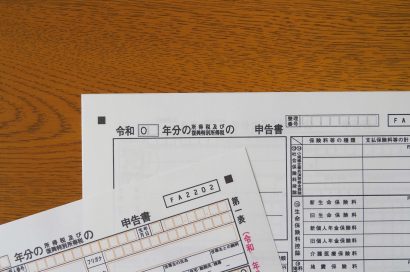共有・総有・合有とは
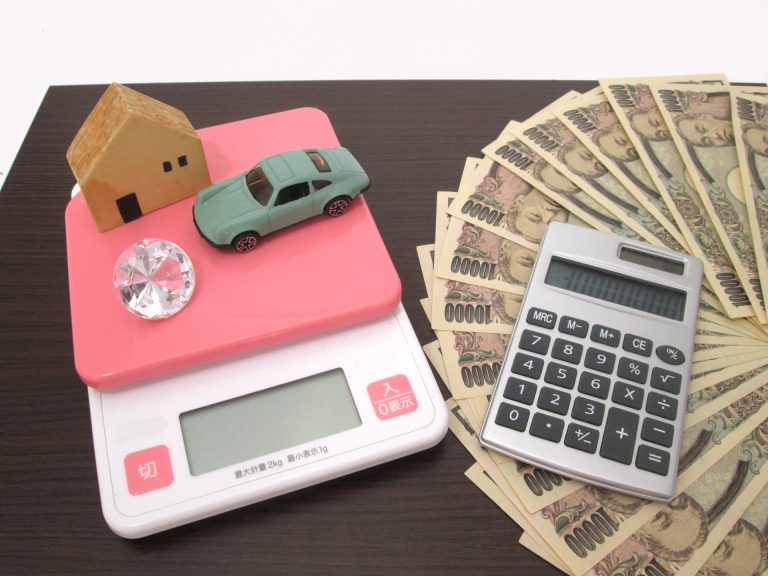
共有とは
共有とは、最も基本的な共同所有の形です。
各共有者は、共同で所有する物(共有物)に対し、それぞれの所有の割合としての「持分」を持ちます。この持分は、お金に換算できる財産的価値です。
また、各共有者は、自分の持分について、他の共有者の同意なしに自由に売ったり、譲ったり、担保に入れたりできます(処分の自由)。これは、持分が個人の財産権として強く保護されているためです。
原則として、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項本文)。例えば、「土地を共有しているが、自分の持分だけ別にしてほしい」と要求できるわけです。
具体例
- 共同相続財産:
親が亡くなった後、兄弟姉妹で遺産(不動産など)をまだ分割せずに共同で所有している状態。 - 夫婦で共同購入した不動産:
持分を決めて共同名義にした家など。
合有とは
合有とは、共同の目的を達成するために団体を形成している場合に現れる共同所有の形態です。
共有よりも団体の拘束力が強いのが特徴です。
合有の特徴は、特定の共同目的(例:事業の遂行)のために、メンバー(組合員)が団体的・有機的な結合を持っています。
また、各メンバーは潜在的な持分は持ちますが、その持分を個人の都合で自由に売ったり、譲ったりすることはできません。
これは、勝手にメンバーが変わってしまうと、団体が目的を達成できなくなる恐れがあるからです(処分の自由の否定)。
注意点として、共同の目的を達成している間は、原則として共有物の分割請求はできません(民法676条2項)。目的が達成されるか、団体が解散するまで、財産は共同で維持されます。
共有物全体の管理権は、個人ではなく団体(組合)に帰属します。
具体例
- 組合財産:
民法上の組合(共同事業を営むための契約を結んだ団体)が所有する財産。共同経営の事業に必要な資金や設備など。
総有とは
総有とは、最も団体の独立性が強く、メンバーの個人的な持分権が前面に出てこない共同所有の形態です。
総有の特徴として、各メンバーは、共有物に対し、利用したり、そこから収益を得たりする権利はありますが、持分という概念自体がありません。そのため、もちろん持ち分の処分や分割請求も認められません。
管理権は、慣習や規約に基づき、代表者や団体(総会など)が行使します。個々のメンバーは利用・収益の範囲でのみ関与します。
個々のメンバーは、団体の構成員として全体に包摂された上で、共同所有に参加しています。
具体例
- 権利能力なき社団の財産:
法人格(権利主体となる資格)を持たない団体(例:設立登記前の会社、町内会、趣味のサークル、同窓会)が所有する備品や資金。 - 入会権(いりあいけん):
古くから集落の住民が、共同で山林や原野を利用(薪の採取、放牧など)する権利。
比較表:共有・合有・総有の違い
| 共同所有の形態 | 個々の結合関係 | 管理権と収益権の関係 | 持分の譲渡と分割請求 |
| 共有 | 目的を共有する偶然的な関係(団体ではない) | 管理権・収益権は各個人に帰属 | 自由(譲渡・分割請求ともに可能) |
| 合有 | 共同目的達成のため団体的結合を作る | 管理権は団体に、収益権は各個人に帰属 | 強い制限(譲渡・分割請求ともに不可または制限あり) |
| 総有 | 各人は団体に包摂される | 管理権は団体に、利用・収益権は各個人に帰属 | 認められない(そもそも持ち分がない) |
CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。