共有名義不動産を勝手に単独名義で登記された場合どうなる?
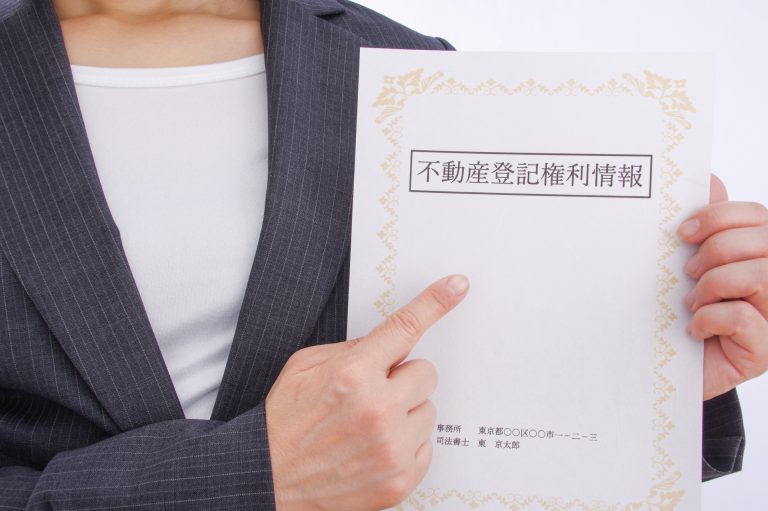
目次
共有名義不動産を勝手に単独名義で登記されたとしても、その登記は無効であり、本来の所有権(共有持分)が失われるわけではありません。
しかし、そのままにしておくと様々なトラブルに発展する可能性が高いため、速やかに対策する必要があります。
勝手に登記された場合の所有権はどうなる?
勝手に登記がされたとしても、所有権がただちに失われるわけではありません。
これは、日本の不動産登記制度の根本に関わる重要な原則に基づいています。
登記は、不動産に関する権利関係(誰が所有者か、どんな抵当権が付いているか、など)を公示(一般に公開)するためのものです。世の中の人々に「この不動産の権利はこうなっていますよ」と示すことで、取引の安全を確保する役割があります。
しかし、この「公示」は、あくまで「権利の状況を外部に示す手段」であって、「権利そのものを生み出すもの」ではありません。
つまり、登記簿に記載されている内容が、必ずしも真実の権利関係(実体上の権利)と一致しているとは限らないのです。
したがって、たとえ登記簿が単独名義に書き換えられても、共有持分という所有権は、法的に何ら影響を受けることなく、依然として有効に存在しています。
勝手に単独名義で登記されるケース
共有名義不動産が勝手に単独名義で登記される主なケースは以下の通りです。
- 書類の偽造
- 相続における不正
1. 書類の偽造
登記申請には、原則として登記義務者(権利を失う側、ここでは共有持分を失うことになる本来の共有者)の意思確認と、それを証明する書類が必要です。それらを偽造されてしまうと、不正な登記ができてしまいます。
例えば、不正に単独名義にしたい者が、他の共有者(登記義務者)から登記申請の代理権を得たかのように装うため、偽造した委任状を作成したり、実際には売買も贈与もされていないにもかかわらず、共有持分を売却または贈与したかのように見せかける契約書を偽造したりするケースが考えられます。
法務局は、提出された書類が形式的に整っていれば、基本的にその書類の真否までを厳密に調査することは困難です。そのため、巧妙に偽造された書類は、そのまま登記申請が受理されてしまうリスクがあります。
2. 相続における不正(遺産分割協議書偽造など)
相続が発生し、本来共有名義となるべき不動産を、一部の相続人が他の相続人に無断で自身の単独名義で登記してしまうケースです。
具体的な手口としては、相続不動産を単独名義で取得したい相続人が、他の相続人の合意を得ずに、あたかも全員がその単独名義に同意したかのような内容の遺産分割協議書を偽造するケースです。
他にも、一部の相続人の存在を隠蔽したり、連絡を絶ったりして、その者を除外した形で遺産分割協議が行われたかのように装い、登記を申請するケースもあります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要な行為です。合意がない状態での登記は無効ですが、偽造された協議書が提出されると、法務局は真偽を確認しきれないことがあります。
勝手に登記された場合のリスク
勝手に登記された状態を放置した場合、以下のようなリスクがあります。
- 不動産を処分・担保にされてしまうリスク
- 不動産が勝手に活用されてしまうリスク
- 取得時効のリスク
不動産を処分・担保にされてしまうリスク
不正に単独名義となった者は、登記簿上はあたかも自分が不動産全体の所有者であるかのように見えます。
この登記を悪用し、「自分が正当な所有者である」と装って、第三者(買主)に不動産を売却してしまう可能性があります。
買主が、その登記を信じ、かつ、その登記が不正なものであることを知らなかった(「善意」である)場合、日本の不動産登記制度の特性上、その買主が所有権を取得してしまう(共有持分を失う)リスクが生じます。
この場合、本来の所有者は、不動産そのものの所有権を失う代わりに、不正な登記をした者に対して損害賠償を請求することになりますが、その者が資力に乏しい場合、事実上、損害を回収できない可能性も十分にあります。
また、売却と同様に、不正に単独名義となった者が、その不動産を担保にして金融機関から借金をしたり、あるいは個人的な債務の担保として利用したりする可能性があります。
この場合も、金融機関などが善意であれば、その抵当権は有効に成立してしまいます。
もし借金が返済されなければ、その金融機関は担保権を実行し、不動産が競売にかけられることになります。そうなれば、その不動産に対する共有持分を回復することが極めて困難になります。
一度、善意の第三者に売却されたり、担保に設定されたりすると、共有持分を取り戻すためには、その第三者を相手取って裁判を起こす必要が生じます。
これは非常に複雑で時間のかかる手続きであり、多額の弁護士費用や裁判費用が発生します。さらに、必ずしも望む結果(不動産そのものの回復)が得られるとは限りません。
不動産が勝手に活用されるリスク
共有名義の不動産は、原則として共有者全員の合意がなければ、その処分や変更(大規模なリフォームなど)はできません。しかし、不正に単独名義で登記された場合、本来の共有者の権利が脅かされます。
不正に単独名義とした者が、あたかも自分が単独所有者であるかのように振る舞い、無断でその不動産を占有・利用したり、第三者に賃貸したりする可能性があります。
もし、不動産が賃貸されている場合、本来共有持分に応じた賃料収入を受け取る権利がある共有者であるにもかかわらず、不正名義人がその収入を独占する可能性があります。
取得時効のリスク
「取得時効」とは、他人の物を一定期間、「自己の所有物であると信じて、平穏かつ公然と占有し続ける」ことで、その物の所有権を取得できるという民法の制度です。
時効の成立要件は以下の通りです。
- 占有の開始: 不正に単独名義とした者が、不動産を占有し始める。
- 「所有の意思」の占有: 「自分のものだ」という意思を持って占有すること。
- 平穏かつ公然の占有: 争いなく、隠さずに占有すること
時効が成立する期間は、過失の有無によって異なります。
- 占有開始時に善意無過失(所有権が自分にあると信じ、そう信じるに足る過失がなかった)の場合:10年間
- 占有開始時に悪意または過失があった場合:20年間
不正に単独名義で登記した者は、通常、その登記が不正であることを知っているはずなので、「悪意」であると判断される可能性が高いです。
そのため、20年の期間が問題となります。 この20年間、その不正名義人が不動産を占有し続け、何の権利主張もせず、異議を唱えなかった場合、理論上は取得時効が成立し、共有持分が失われてしまうリスクもゼロではありません。
ただし、共有者の場合は、原則として取得時効は成立しにくいとされています。なぜなら、共有者は互いに協力して共有物を管理する義務があり、その占有は「共有者としての占有」と見なされやすいからです。
しかし、他の共有者に対して明確に「自己の単独所有」を主張し、占有を継続したと認められる場合は、時効取得が成立する可能性も否定できません
勝手に登記された場合の対処法
勝手に登記された場合は、速やかに以下の対処法を検討しましょう。
- 登記簿謄本を取得して詳細を確認する
- 弁護士や警察などの専門家に相談する
- 法的措置を検討する
①登記簿謄本を取得して詳細を確認する
まず、現状を把握するため、最新の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。登記簿謄本は、管轄の法務局の窓口、またはオンライン(「登記情報提供サービス」や法務局のオンライン申請システム)で取得できます。
登記簿謄本で、確認すべき事項は以下の点です。
- 現在の名義人
勝手に単独名義になったのは誰か。 - 登記の原因
「売買」「贈与」「相続」「時効取得」など、どのような原因で登記がなされたことになっているか。 - 登記年月日
いつ単独名義になったのか。 - 権利部(甲区・乙区)
甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が記載されています。ここに身に覚えのない記載がないか確認します。
②弁護士や警察などの専門家に相談する
現状確認ができたら、次にすべきは、法的な知識と経験を持つ専門家への相談です。
自己判断で行動することは、かえって事態を悪化させるリスクがあるため、必ず専門家を介してください。
弁護士は、登記の抹消請求訴訟、損害賠償請求、不正を行った者に対する刑事告訴(詐欺罪、公正証書原本不実記載罪など)など、幅広い法的戦略を立案し、実行してくれます。
相手方との交渉が困難、訴訟に発展する可能性が高い、損害賠償も請求したい、刑事告訴も視野に入れている、といった複雑な事案の場合に、中心となって解決を依頼すべき専門家です。
明らかな詐欺、有印私文書偽造、公正証書原本不実記載などの犯罪行為が疑われる場合は、警察に被害届を提出したり、刑事告訴を行ったりすることも検討しましょう。
刑事事件として立件されれば、不正の証拠収集が進み、民事上の権利回復にも有利に働く可能性があります。
まずは弁護士に相談し、法的根拠を明確にした上で、必要に応じて警察に情報提供を行うという連携が有効です。
③法的措置の検討と実行
専門家と相談し、不正登記の状況や証拠の有無、相手方の態度などを踏まえて、法的措置も検討しましょう。
抹消登記請求訴訟は、不正にされた登記を抹消するための、最も強力かつ一般的な法的手段です。
訴訟の流れとしては、裁判官が双方の主張を聞き、証拠を調べます。
偽造された書類の有無や、本来の所有者の意思表示がなかったことなどを立証する必要があります。主張が認められれば、裁判所は登記の抹消を命じる判決を下します。
判決が確定すれば、その判決書を法務局に提出し、不正な単独名義の登記を抹消し、元の共有名義の状態に戻すことができます。
所有権移転登記請求訴訟は、登記が錯誤(間違い)などにより無効な場合や、不正に持分が相手に移転された場合に、真の権利者への所有権移転登記を請求する訴訟です。
例えば、遺産分割協議が成立していないのに、特定の相続人に単独で相続登記がされたケースで、その相続人があなたの持分を単独名義にした形になっている場合などに有効です。
この訴訟で勝訴すれば、判決に基づいてあなたの共有持分が正しく登記され、真の所有権関係が回復します。
【実例】共有名義不動産を勝手に単独名義で登記された事例
A、B、Cが三人で甲土地をそれぞれ持分は3分の1ずつで共同所有(共同名義で登記)していましたが、Cが勝手に甲土地全部を自分名義に登記してしまいました。A、BとしてはCさんに何か主張できないのでしょうか?
A:結論から言いますと、AとBは自己の持ち分を超える分についても「単独で」登記の抹消を請求することが出来ます。
事例はA・B・Cが甲土地を共同名義で所有していましたが、Cが単独でA・Bの持分まで登記をしてしまった場合です。CはABの分を勝手に登記(共同名義から単独名義に)してしまい本来の持ち分を超えて自分の(Cの)土地として登記をしています。
実態とは異なっているため、当然A、Bは抹消登記(共同名義に戻すように)を請求することが可能です。またその際、A、Bは自己の持分を超える分についても抹消登記の請求をすることが出来ます。
また、共有者ではなく全く関係のない第三者であるDが不実の登記(無断で登記)をしてしまった場合についても、持分移転登記の抹消が可能です。【最高判平15年7月11日】
「不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。」

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
よくある質問
勝手に登記されても、所有権は失われない?
A:はい、所有権は失われません。不正な登記は無効であり、実体上の権利はあなたに残ります。ただし、放置すると権利行使が難しくなるリスクがあるため、早急な対応が必要です。
警察に相談すれば解決するのか?
A:警察は犯罪捜査が目的で、登記の抹消は行いません。詐欺や文書偽造など犯罪行為が疑われる場合に相談は有効ですが、直接的な解決には弁護士や司法書士への相談が必要です。
登記を抹消できれば、全て元通りになるのか?
A:原則として、登記が抹消されれば所有権は元通りになります。しかし、その間に第三者に売却されるなど、さらなる問題が発生している場合は、別途複雑な法的対応が必要になることもあります。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
司法書士
司法書士ALBA総合事務所 代表
東京司法書士会新宿支部所属。平成16年に司法書士試験合格以来、一貫して司法書士業界で研鑽を積む。
相続に関する手続き・対策(遺言書作成、相続手続き、成年後見など)、不動産登記(共有持分、権利変更など)、そして債務整理(自己破産、個人再生、過払い金請求など)において、豊富な実績と深い知見を持つ。
会社設立などの商業(法人)登記や、各種裁判手続きにも精通し、多岐にわたる法的ニーズに対応可能。








