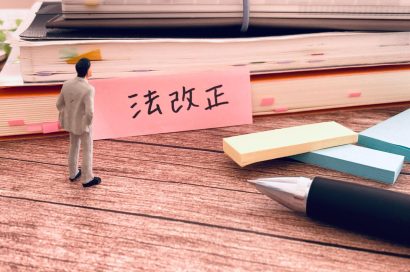共有物分割請求のメリット・デメリットとは?訴訟手続きの流れや費用

目次
共有物分割請求は、他の共有者の同意がなくても、裁判所の判断によって不動産の共有状態を解消できる強力な手段です。
本記事では、2023年の民法改正を踏まえて、共有物分割請求とは何か、手続きの流れや分割方法、メリット・デメリット、そして訴訟にかかる費用まで、網羅的に解説します。
共有不動産の問題を抱えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
共有物分割請求とは
共有物分割請求とは、不動産などを複数人で共有している状態(=共有関係)を解消するために、共有者の一人が他の共有者に対して、その分割を求めることを指します。
不動産は、利用方法や管理、売却などについて共有者全員の合意がなければ進められないことが多く、意見が対立すると身動きが取れなくなるものです。
このような状態を解消し、各共有者の権利を実現するために、共有物分割請求という制度が法律で認められています。
共有物分割請求は、最終的には訴訟によって裁判所に判断を委ねることができるため、共有者間のトラブル解決における最終手段ともいえるでしょう。
また、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」と定められています。( 民法第256条1項)
そのため、他の共有者が分割に反対していたとしても、共有者の一人から分割請求があれば、協議を開始しなければなりません。
協議で話がまとまらなければ、調停や訴訟といった法的な手続きに進むことになります。
ただし、契約によって「5年を超えない期間内は分割しない」という特約(不分割特約)を結んでいる場合は、その期間内は分割請求ができません。
共有物分割請求訴訟を検討するべきケース

共有物分割請求を検討すべきケースは、次の3つです。
- 共有名義不動産の活用を巡って共有者同士の意見がまとまらない
- 共有名義不動産を占有する特定の共有者を追い出したい
- 他の共有者が不動産の分割を巡る話し合いに応じてくれない・または話がまとまらない
ケース①:共有名義不動産の活用を巡って共有者同士の意見がまとまらない
共有名義不動産は、売却や大規模な増改築などの処分・変更行為を行う際に共有者全員の同意が必要になります。
つまり、誰か一人でも反対すればそのような行為を行うことはできないのです。
その上で、「このまま住み続けたい」「土地と合わせて売ってしまいたい」「増改築をして貸し出したい」など、共有者それぞれが全く異なる意見を主張するパターンも非常に多く見られます。
このような意見の対立は、長い期間を経てもまとまらないことが多いのが実情です。
そのため、こうした場合は法的な強制力で共有状態を解消できる共有物分割請求を検討する代表的なケースといえます。
ケース②:共有名義不動産を占有する特定の共有者を追い出したい
共有者の一人が不動産を無断で占有し、他の共有者に家賃などを支払わないケースも少なくありません。
とはいえ、他の共有者は不法に占有されているわけではないため、法的に「明け渡し」を求めることが困難です。
このような場合、共有物分割請求によって不動産全体を売却するなどの判断が下されれば、結果的に占有状態を解消できます。
ケース③:他の共有者が不動産の分割を巡る話し合いに応じてくれない・または話がまとまらない
そもそも共有者の一部が不動産分割に関する話し合いのテーブルについてくれない、あるいは連絡が取れないといったケースも存在します。
また、苦心してなんとか話し合いの場を設けても、感情的な対立から全く合意に至らない場合もしばしば見られるパターンです。
このように当事者間での解決が絶望的な状況では、裁判所に判断を委ねる共有物分割請求が唯一の解決策となることがあります。
【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫
共有物分割請求の流れ

共有物分割請求は、以下の4つのステップで行います。
- 共有者同士での協議
- 共有物分割調停の申し立て
- 共有物分割請求訴訟の提起
- 裁判による和解または判決
Step1.共有者同士での協議
最初のステップは、共有者全員での「協議(話し合い)」です。
分割したいと考える共有者が、他の共有者に対して分割を提案し、どのような方法で分割するのかを話し合います。
全員が合意すれば、最も円満かつ迅速に共有関係を解消できます。
分割方法(後述する現物分割、代金分割、代償分割)や、それぞれの取り分、具体的な手続きなどを決め、合意内容を「共有物分割協議書」として書面に残しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。
Step2.共有物分割調停の申し立て
協議で話がまとまらない場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所(※対象不動産が遺産の場合は家庭裁判所、そうでない場合は地方裁判所)に「共有物分割調停」を申し立てます。
調停は、裁判官と調停委員が中立的な立場で間に入り、当事者双方の意見を聞きながら、合意形成を目指す手続きです。
あくまで話し合いがベースなので、訴訟に比べて柔軟な解決が期待でき、費用も比較的安価で済みます。
ここで合意に至れば「調停調書」が作成され、その内容は判決と同じ効力を持ちます。
Step3.共有物分割請求訴訟の提起
調停でも解決しない(不成立となった)場合、いよいよ地方裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起します。
訴訟では、当事者それぞれが自身の主張とそれを裏付ける証拠を提出し、最終的には裁判官が分割方法を判断します。
訴訟は、共有者間の対立が深刻で、話し合いによる解決が不可能な場合の最終手段です。 弁護士への依頼が事実上必須となり、手続きも複雑化します。
Step4.裁判による和解または判決
訴訟を提起した後でも、裁判官から和解を勧められることがあります。
裁判上の和解が成立すれば、その内容で解決となります。
和解も成立しない場合は、最終的に裁判官が「判決」を下し、共有物の分割方法を決定します。
この判決には強制力があるため、共有者はその内容に従わなければなりません。
【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫
共有物分割の3つの方法
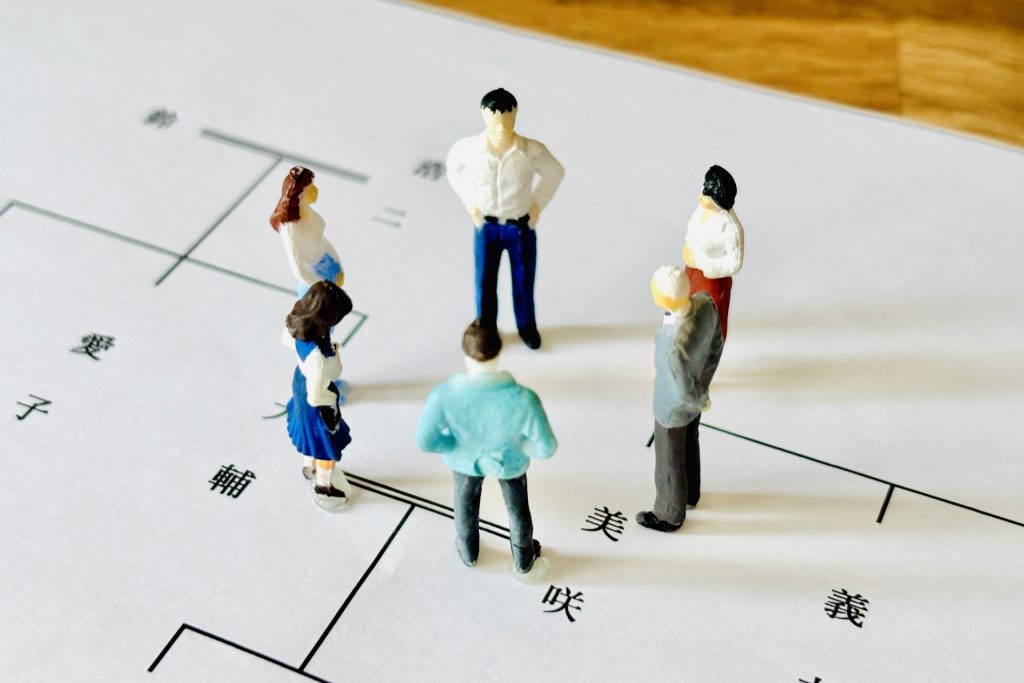
裁判所が分割方法を判断する際、主に以下の3つの方法が検討されます。
- 現物分割
- 代金分割(換価分割)
- 代償分割(価格賠償)
どの方法が選択されるかは、不動産の性質や共有者間の関係性、希望などによって異なります。
①現物分割:共有物を物理的に切り分ける
現物分割は、共有している不動産そのものを物理的に分ける方法です。
例えば、一つの広大な土地を、持分割合に応じて複数の土地に分筆(登記上で分けること)するケースが典型例です。
分けた土地はそれぞれの共有者が単独で所有することになります。
ただし、建物のように物理的に分けることが困難な不動産には適用しにくい方法です。
②代金分割(換価分割):売却したお金を共有者で分ける
代金分割は、共有不動産を第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。
換価分割とも呼ばれます。
物理的に分割できない建物やマンションなどでよく用いられる方法で、金銭で分配するため、公平な解決が図りやすいというメリットがあります。
ただし、共有者全員が不動産を手放すことになります。
③代償分割(価格賠償):共有者の1人が他の共有者の持分を買い取る
特定の共有者がその不動産に住み続けたい場合などに有効な方法です。
代償分割は、共有者の一人が不動産全体を取得する代わりに、他の共有者に対してその持分に相当する金銭(代償金)を支払う方法です。
価格賠償とも呼ばれます。
ただし、不動産を取得する側に、他の共有者の持分を買い取るだけの十分な資力が必要となります。
センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫
共有物分割請求訴訟のメリット

共有物分割請求訴訟の主なメリットは、以下の通りです。
- 裁判所の判断によって最終的に解決できる
- 適正価格で公平に分割できる
- 他の共有者の同意がなくても手続きを進められる
メリット①:裁判所の判断によって最終的に解決できる
最大のメリットは、当事者間の話し合いが平行線でも、裁判所の判決によって強制的に共有関係を解消できる点です。
協議や調停は相手の合意がなければ成立しませんが、訴訟の判決には法的拘束力があるため、相手が反対していても問題を最終的に解決できます。
長年膠着状態にあった不動産問題を終わらせるための、確実な手段といえます。
メリット②:適正価格で公平に分割できる
訴訟では、不動産の価値を客観的に評価するために、不動産鑑定士による鑑定が行われることが一般的です。
当事者間の主張に左右されず、専門家による適正な評価額に基づいて分割が行われるため、公平性が保たれます。
不当に安い価格で買い叩かれたり、逆に高すぎる代償金を請求されたりするリスクを避けることができます。
メリット③:他の共有者の同意がなくても手続きを進められる
共有物分割請求は、共有者の一人の意思だけで開始できる手続きです。
他の共有者が協議を拒否したり、非協力的であったり、あるいは行方不明であったりしても、訴訟を提起して手続きを進めることが可能です。
「話し合いにならないから」と諦める必要はありません。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
共有物分割請求訴訟のデメリットとリスク

共有物分割請求訴訟のデメリット・リスクは以下の通りです。
- 解決までに時間と手間がかかる
- 費用がかかる
- 共有者同士で感情的な対立が生じやすい
- 必ずしも希望通りの結果になるとは限らない
- 競売になると市場価格より安くなる可能性がある
デメリット①:解決までに時間と手間がかかる
訴訟は、提訴から判決まで一般的に1年以上の期間がかかるとされています。
事案が複雑な場合は、さらに長期化することもあります。
また、裁判所に提出する書類の準備や、期日に出廷するなど、多大な手間と労力も必要です。
デメリット②:費用がかかる
訴訟には、弁護士費用をはじめ、裁判所に納める印紙代や、不動産鑑定費用など、さまざまな費用が発生します。
特に弁護士費用は高額になる可能性があり、経済的な負担は小さくありません。
費用の詳細は後ほど解説します。
デメリット③:共有者同士で感情的な対立が生じやすい
訴訟は、お互いの主張を戦わせる場であるため、共有者間の人間関係が悪化しやすいという大きなデメリットがあります。
特に親族間で共有している場合、訴訟をきっかけに関係に修復不可能な亀裂が入ってしまうことも少なくありません。
円満な解決を望むのであれば、できる限り協議や調停の段階で解決することが望ましいでしょう。
デメリット④:必ずしも希望通りの結果になるとは限らない
訴訟では、最終的な分割方法を決定するのは裁判官です。
自分が望んでいた分割方法(例えば「代償分割で自分が買い取りたい」)が認められるとは限りません。
裁判所は、不動産の状況や当事者の事情などを総合的に考慮して、最も妥当と判断した方法を選択します。
デメリット⑤:競売になると市場価格より安くなる可能性がある
裁判所の判決で代金分割が命じられた場合、共有者間で売却方法の合意ができないと、最終的に「競売」にかけられることがあります。
競売での売却価格は、通常の市場価格の5~7割程度になることが多く、共有者全員にとって経済的な損失が大きくなるリスクがあります。
この「競売リスク」は、代金分割における最大のデメリットといえるでしょう。
センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫
共有物分割請求訴訟にかかる費用

共有物分割請求訴訟にかかる費用の目安は、以下の通りです。
| 費用の目安 | 備考 | |
| ①弁護士費用 | 着手金:20~50万円報酬金:経済的利益の10~20%程度 | 法律事務所の料金体系や事案の難易度により変動。(センチュリー21中央プロパティーは完全無料) |
| ②訴訟費用(印紙代など) | 数万円~数十万円 | 不動産の固定資産税評価額に応じて算出される印紙代や、裁判所からの郵送費(郵便切手代)。 |
| ③不動産鑑定費用 | 30万~50万円程度 | 裁判所が不動産の適正な価値を判断するために、鑑定が必要とした場合に発生する費用。 |
費用①:弁護士費用
訴訟を専門家である弁護士に依頼する場合にかかる費用です。
一般的には、依頼時に支払う「着手金」と、事件解決時に成功の度合いに応じて支払う「報酬金」で構成されています。
法律事務所によって料金体系は異なりますが、着手金で数十万円、報酬金で経済的利益の10%~20%程度が相場です。
センチュリー21中央プロパティーには共有持分に強い社内弁護士が常駐しており、初回の面談時から同席いたします。
ご相談から契約に至るまで、諸費用は全て無料となっておりますので、共有持分のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
費用②:訴訟費用(印紙代など)
訴訟を提起する際に、裁判所に納める手数料です。
訴状に貼る収入印紙の代金で、訴額(対象となる不動産の固定資産税評価額を基準に計算)に応じて金額が決まります。
この他に、裁判所からの郵便物を送るための郵便切手代なども必要になります。
費用③:不動産鑑定費用
訴訟において、不動産の適正な価格を評価するために不動産鑑定士による鑑定が必要となった場合にかかる費用です。
費用は数十万円になることが多く、原則として訴訟を提起した側(原告)が一旦立て替えることになりますが、最終的な負担割合は判決で決まります。
センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫
共有物分割請求をせずに共有状態を解消する方法3選
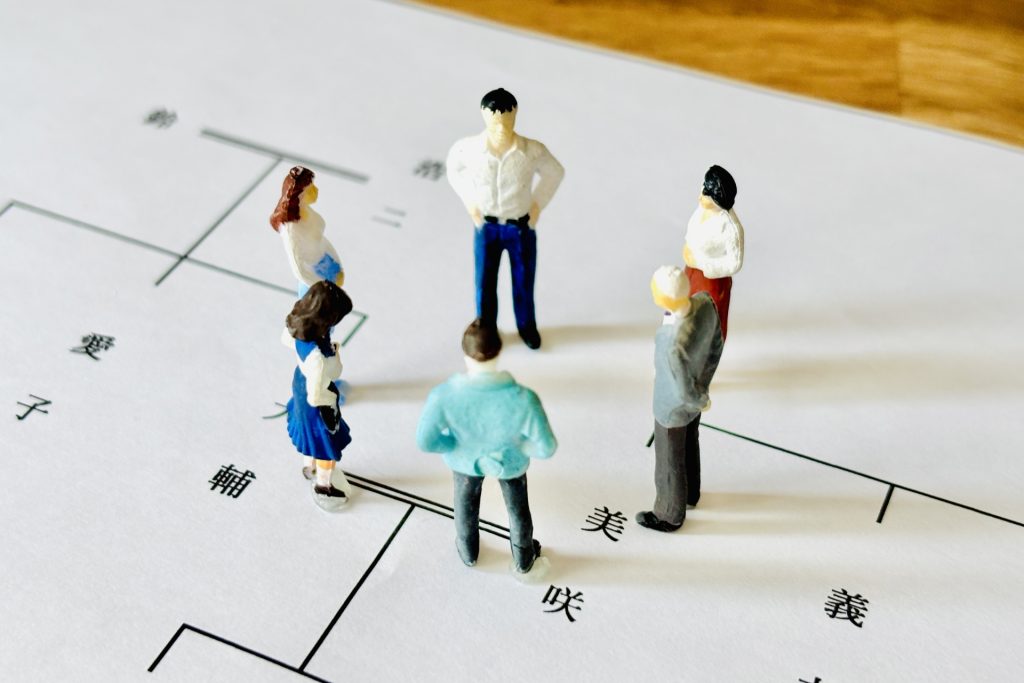
訴訟は時間も費用もかかるため、できれば避けたいと考える方も多いでしょう。
共有物分割請求をせずに共有状態から抜け出すための方法としては、以下の3つが代表的です。
- 自分の共有持分を放棄する
- 他の共有者へ自分の持分を売却または贈与する
- 第三者へ自分の持分を売却する
方法①:自分の共有持分を放棄する
自分の共有持分を放棄するという方法があります。
民法上、共有者の一人がその持分を放棄したとき、その持分は他の共有者に帰属すると定められています(民法第255条)。
手続きは比較的簡単ですが、見返り(金銭など)は一切なく、純粋に権利を手放すだけである点に注意が必要です。
また、持分を放棄しても、固定資産税の納税義務などからすぐに解放されるわけではないケースもあります。
方法②:他の共有者へ自分の持分を売却または贈与する
他の共有者の中に、あなたの持分を買い取りたい、あるいは譲り受けたいという人がいれば、その人に売却または贈与することで共有関係から抜けられます。
共有者間の合意があればスムーズに進められる方法です。
ただし、売却価格や贈与の条件などで折り合いがつかないことも少なくありません。
方法③:第三者へ自分の持分を売却する
自分の共有持分は、他の共有者の同意がなくても、第三者に自由に売却することができます。
これが、訴訟を避けつつ、かつ金銭的なメリットも得られる最も現実的な方法の一つです。
ただし、売却先は専門会社に限られ、主に「買取業者」と「仲介会社」の2択となりますす。
どちらを選ぶかで、最終的な売却額が大きく変わる点に注意しましょう。
| ◆買取業者 自社の利益が目的のため、あなたの持分を市場価格より大幅に安く直接買い取ります。早く現金化できますが、資産価値は大きく目減りします。 |
| ◆仲介会社 あなたの代理人として、最も高く買ってくれる買主を探します。仲介会社の利益はあなたの利益と連動するため、市場価格に即した高値売却を目指せるのが最大のメリットです。 |
大切な資産を安売りしてしまう前に、まずはセンチュリー21中央プロパティーのような共有持分専門の仲介会社に相談し、ご自身の持分の本当の価値を把握することをおすすめします。
共有物分割請求がおすすめなのはこんな人
共有物分割請求が特に有効なケースは、以下の通りです。
- 協議による解決が困難な場合
- 共有状態の維持が著しく不利益となる場合
- 共有不動産をできるだけ早く売却・現金化したい場合
ケース①:協議による解決が困難な場合
共有者の中に、話し合いに一切応じない人や、連絡が取れない人がいる場合は、協議での解決は不可能です。
このような状況では、訴訟によって法的に解決を図るしかありません。
ケース②:共有状態の維持が著しく不利益となる場合
例えば、固定資産税や管理費の負担だけが続き、不動産から何の収益も得られていないようなケースです。
共有状態を維持することが経済的な負担にしかなっていない場合、分割請求によってその不利益な状況を解消する必要があります。
ケース③:共有不動産をできるだけ早く売却・現金化したい場合
他の共有者が売却に反対しているが、自分は早く不動産を現金化したいという場合にも、共有物分割請求は有効です。
訴訟で代金分割(換価分割)の判決を得ることで、最終的に不動産全体の売却を実現できます。
2023年民法改正のポイント
2023年4月1日に施行された改正民法により、共有物分割に関するルールが一部変更・明確化されました。
特に重要なのは、代償分割(価格賠償)が法律に明記されたことです。
これまで実務上は認められていましたが、明文化されたことで、裁判所がより積極的にこの方法を選択しやすくなったと考えられます。
また、共有者が所在不明の場合に、残りの共有者の同意で不動産の変更や管理ができるようになるなど、共有不動産に関するトラブルを解決しやすくするための改正が行われています。
これにより、これまで以上に共有物分割請求が活用しやすくなったといえるでしょう。
まとめ:共有不動産のトラブルは「共有物分割請求」で解決できる可能性がある
共有物分割請求は、共有不動産をめぐるトラブルを最終的に解決するための強力な法的手段です。
他の共有者の協力が得られなくても、裁判所の判断によって共有状態を解消できるという大きなメリットがあります。
一方で、訴訟に発展した場合は時間や費用がかかるというデメリットも存在します。
もし、手間や費用をかけずに問題を解決したいのであれば、訴訟を起こす前に、まずはご自身の「共有持分のみ」を専門の不動産会社に売却するという選択肢もご検討ください。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分を専門とする不動産仲介会社です。
経験豊富な共有持分の専門家のみが在籍しており、トラブルに発展しやすい他の共有者との交渉もスムーズに代行可能。
社内弁護士が常駐しているため、法的に複雑な手続きも安全・確実に遂行してまいります。
ご相談から売却に至るまで、諸費用はすべて無料となっておりますので、共有持分のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
共有物分割請求に関してよくあるご質問
共有物分割請求に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.調停や裁判をするよりも持分を売却した方が良いのでしょうか?
A.一概には言えませんが、時間や費用、精神的負担をかけずに現金化したい場合は、持分の売却が有力な選択肢となります。
訴訟は解決までに1年以上かかることも珍しくなく、弁護士費用も高額になりがちです。
また、親族間での争いは避けたいと考える方も多いでしょう。
センチュリー21中央プロパティーのような共有持分専門の仲介会社にご依頼いただければ、こうした問題をすべて回避できます。
不動産仲介会社はあなたの代理人として、持分を適正価格で購入してくれる買主を探します。
売却にかかる期間も数週間から数ヶ月程度であり、訴訟に比べて圧倒的にスピーディーです。
訴訟に踏み切って多大なコストをかける前に、まずはご自身の持分が「いくらで」「どのくらいの期間で」売却できる可能性があるのか、専門の仲介会社に相談してみてはいかがでしょうか。
【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫
Q2.共有物分割請求を禁止することはできますか?
A.共有者全員の合意があれば、5年を超えない期間で「分割しない」という特約(不分割特約)を結ぶことができます。
この特約は登記することも可能で、登記すれば第三者にも対抗できます。
ただし、この特約がない限り、共有者の一人から分割請求があれば、他の共有者は拒否できません。
Q3.共有物分割請求に強い弁護士に相談したいのですが…
A.不動産問題、特に共有物分割請求の取り扱い実績が豊富な弁護士を探すことが重要です。
弁護士にもそれぞれ得意分野があります。
インターネットで「共有物分割請求 弁護士 地域名」などで検索したり、不動産専門の弁護士を紹介してくれるサービスを利用したりする方法があります。
また、当社センチュリー21中央プロパティーのように、提携弁護士や社内弁護士が在籍し、持分売却から法的手続きまでワンストップで相談できる不動産会社もあります。
Q4.自分の持分割合が少なくても共有物分割請求は可能ですか?
A.はい、可能です。
共有物分割請求権は、持分割合の大小にかかわらず、すべての共有者に認められた正当な権利です。
たとえご自身の持分がわずかであっても、他の共有者全員に対して分割を請求することができます。
持分割合が少ないからといって、諦める必要は一切ありません。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。