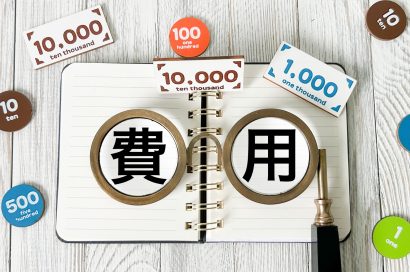【共有持分の相続放棄】共有名義人が亡くなったら持分はどうなる?

目次
不動産の共有名義人である親族が亡くなり、突然相続人になってしまったものの、借金があるかもしれない、他の共有者と関わりたくないなどの理由で「相続放棄」を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、共有持分の相続放棄には「3ヶ月」という厳しい期限があり、手続きも複雑です。
安易に手続きを進めると、本来受け取れるはずだった資産まで手放すことになり、後悔する可能性もあります。
本記事では、共有持分の相続放棄に関する基本的な知識から、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、そして相続放棄以外のより良い解決策まで、わかりやすく解説します。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切相続しないという意思表示のことです。
遺産には、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。(民法第939条)
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄は、特にマイナスの財産が多い場合に有効な手段ですが、デメリットも存在します。
安易に決めず、メリットとデメリットを正しく理解したうえで慎重に判断しましょう。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、主に以下の通りです。
- マイナスの遺産を承継しなくて済む
- 相続争いから解放される
メリット①:マイナスの遺産を承継しなくて済む
最大のメリットは、被相続人が遺した借金やローン、滞納した税金などのマイナスの遺産を一切引き継がなくて済むことです。
明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を選択することで経済的な負担を回避できます。
メリット②:相続争いから解放される
相続放棄をすれば、他の相続人との遺産分割協議に参加する必要がなくなります。 不動産の分け方や管理方法などで揉めるケースは少なくありません。
他の共有者との関係性が良くない、話し合いがストレスになるといった場合に、相続争いそのものから距離を置けるという精神的なメリットがあります。
【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、主に以下の通りです。
- プラスの遺産も一切承継できなくなる
- 手続きに手間と費用がかかる
デメリット①:プラスの遺産も一切承継できなくなる
相続放棄は、プラスの財産も含めて「すべての遺産」を放棄する制度です。
そのため、「借金は放棄したいが、価値のある実家の共有持分は相続したい」といった選択はできません。
後から価値の高い財産が見つかったとしても、一度相続放棄をすると撤回はできないため、慎重な判断が求められます。
デメリット②:手続きに手間と費用がかかる
相続放棄は、家庭裁判所への申述という法的な手続きが必要です。
戸籍謄本などの必要書類を集めたり、申述書を作成したりする手間がかかります。
また、手続き自体に収入印紙代や郵券代などの実費がかかるほか、司法書士や弁護士に依頼する場合には別途報酬が発生します。
相続放棄できる期間は3カ月以内!
相続放棄の手続きには、厳格な期限が定められています。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、民法第915条で定められています。 この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、すべての遺産を相続する「単純承認」をしたとみなされてしまいます。
被相続人に多額の借金があった場合でも、それを支払う義務を負うことになるため、期限にはくれぐれも注意が必要です。
【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫
共有持分と相続放棄の関連性
共有持分と相続放棄の関係を正しく理解することは、適切な判断を下すために不可欠です。
共有持分とは
共有持分とは、一つの不動産を複数の人で一緒に所有している場合の「所有権の割合」を指します。
たとえば、夫婦でマイホームを買うときに、夫と妻でそれぞれが「半分ずつ所有する」というような状況が、共有名義であり、その「半分」がそれぞれの共有持分にあたります。
この共有持分を持っていると、自分の持分だけを自由に売ったり、建物全体を勝手にリフォームしたりすることはできません。
何かをするときには、原則として他の共有者全員の同意が必要になります。
このため、もし共有者同士で意見が合わないと、不動産の管理や売却を進めるのが難しくなり、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
共有持分”だけ”を相続放棄することはできない
「他の財産は相続したいけど、面倒な共有持分だけは手放したい」と考える人もいるかもしれません。
しかし、残念ながら不動産の共有持分だけを相続放棄することはできません。
相続放棄は、「故人の財産をすべて受け取らない」という意思表示です。
良い財産も悪い財産もひっくるめて、「相続する」か「相続しない」かの二択しかありません。
そのため、もし共有持分をどうしても相続したくない場合は、他の預貯金や不動産など、すべての相続財産を放棄する必要があります。
もし不要な共有持分だけを手放したいのであれば、一度相続したうえで、後述する「持分の売却」などの別の方法を検討する必要があります。
センチュリー21中央プロパティーなら【諸費用0円】で持分売却 ≫
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似た制度に「限定承認」があります。
これは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
借金がいくらあるか不明な場合に有効ですが、手続きが非常に複雑で、相続人全員で申述しなければならないなどの制約があり、実際にはほとんど利用されていません。
| 相続放棄 | 限定承認 | 単純承認 | |
| 相続財産の範囲 | すべての財産を相続しない | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する | すべての財産を無条件に相続する |
| 手続きの期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内 | 手続きは不要(熟慮期間の経過で自動的に成立) |
| 手続きの方法 | 家庭裁判所に申述 | 相続人全員で家庭裁判所に申述 | 特になし |
| メリット | ・借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む ・手続きが比較的簡単 | ・プラスの財産が残る可能性がある ・家宝など特定の財産を手元に残せる可能性がある | ・手続きが不要で最も簡単 |
| デメリット | ・プラスの財産もすべて手放すことになる ・一度手続きをすると原則撤回できない | ・手続きが非常に複雑で費用もかかる ・相続人全員の同意が必要 ・時間がかかる | ・借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐことになる |
共有持分を相続放棄したらどうなる?
共有持分を持つ人が相続放棄した場合、その持分は他の共有者に直接移るわけではありません。法律上、相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。そのため、その持分は、下記の相続順位に従って次の順位の相続人に引き継がれることになります。
相続順位と法定相続割合
法律で定められた相続人(法定相続人)には順位があり、先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
相続順位は以下の通りです。
- 常に相続人:配偶者
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
そして、誰が相続人になるかの組み合わせによって、法律で定められた遺産の取り分(法定相続分)が、以下のように変わります。
| 法定相続分 | |
| 配偶者 と 子(第1順位) | 配偶者:1/2 子:1/2(全員分を合算) |
| 配偶者 と 直系尊属(第2順位) | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3(全員分を合算) |
| 配偶者 と 兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(全員分を合算) |
| 子(第1順位)のみ | 全て |
| 直系尊属(第2順位)のみ | 全て |
| 兄弟姉妹(第3順位)のみ | 全て |
| 配偶者 のみ | 全て |
先順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の人に移ります。
例えば、亡くなった方に配偶者と子(第1順位)がいて、全員が相続放棄した場合、相続権は第2順位である父母に移ることになります。
このことを知らないと、自分たちが放棄したことで、意図せず親族に迷惑をかけてしまう可能性があるので注意が必要です。
相続人が複数いる中で一部の人が相続放棄した場合の共有持分の行方
相続人が複数いる中で、一部の人だけが相続放棄をした場合、放棄された持分は他の相続人に引き継がれます。
その際の持分割合の決まり方には、主に以下の2つのケースがあります。
- 遺産分割協議で持分を取得する人を決める
- 法定相続分で持分を取得する
ケース①:遺産分割協議で持分を取得する人を決める
被相続人の共有持分を相続する権利を持つ人が複数いる場合、遺産分割協議によって、誰がその持分を取得するかを話し合いで決めることになります。
相続放棄をした人はこの協議に参加する権利を失います。
例えば、夫と妻、長男、長女がいて不動産は夫と妻の共有(2分の1ずつ)、夫が死亡した事例(長男が相続放棄)を考えてみましょう。
この場合、長男は相続放棄したことから、相続人としての地位が無くなり、夫の持分は残りの相続人である妻と長女で相続します。
妻が夫の共有持分の2分の1、長女が夫の共有持分の2分の1を相続するという形が一般的です。
ケース②:法定相続分で持分を取得する
遺産分割協議がまとまらない場合や、特に協議を行わない場合は、法定相続分に従って共有持分が相続されます。
具体例として、夫婦が不動産を2分の1ずつの持分割合で共有しており、夫が死亡した事例(一人の子が相続放棄、夫の父親存命)を見てみましょう。
このケースでは、まず配偶者である妻が相続人となります。
夫の子が一人相続放棄したため、子に代わって次順位の相続人である夫の父親が相続人となります。
したがって、夫の持分は妻と夫の父親で相続することになり、法定相続分に従うと、妻は夫の共有持分を3分の2、夫の父親は共有持分を3分の1取得します。
唯一の相続人が相続放棄した場合の共有持分の行方
相続人が一人しかいない状況で、その唯一の相続人が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。
相続権が次順位の相続人に移る
前述の相続順位に従い、相続権は自動的に次順位の法定相続人に移ります。
例えば、亡くなった方の相続人が子一人のみで、その子が相続放棄した場合、相続権は第2順位の父母へ、父母もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと移っていきます。
次順位の相続人がいる場合は、その方に相続放棄をした旨を伝え、今後の対応を相談する必要があるでしょう。
【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫
相続人全員が相続放棄した場合の共有持分の行方
第1順位から第3順位までの相続人全員が相続放棄をした場合、その共有持分は最終的にどうなるのでしょうか。
相続財産清算人による手続きで、財産を国庫に帰属させる
相続人全員が相続放棄し、相続人が誰もいなくなった場合、利害関係者(被相続人にお金を貸していた債権者や、物件の他の共有者など)の申立てにより、家庭裁判所は「相続財産清算人」を選任します。
相続財産清算人は、弁護士などの専門家が選ばれ、被相続人の財産を管理・調査し、債権者への支払いなどを行った後、最終的に残った財産を国庫(国)に帰属させます。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
最終的に共有者に持分が移るまでの流れ
相続人全員が相続放棄をした場合、その共有持分の行方はどうなるのでしょうか。
この点について、2023年4月1日に施行された改正民法でルールが大きく変更されたため、特に注意が必要です。
| 以前のルール(2023年3月31日まで) 法改正の前は、相続人が誰もいなくなった共有持分は、最終的に他の共有者に帰属すると解釈されていました。 |
| 現在のルール(2023年4月1日から) 現在のルールでは、相続人不存在となった共有持分は、原則として国のもの(国庫に帰属)となります。 具体的には、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、その清算人が財産を管理・換価します。 債務などを支払った後に残った財産が国庫に納められる、という流れです。 |
この変更により、他の共有者は「相続人が放棄すれば、いずれ自分の持分が増える」と期待することはできなくなりました。
もし他の共有者がその持分を取得したい場合は、相続財産清算人から買い取るなど、別途法的な手続きを踏む必要があります。
このように、法改正によって手続きがより明確化されると同時に、専門的な対応が求められるようになったため、専門家への相談がますます重要になっています。
相続放棄の申述に必要な書類
相続放棄を家庭裁判所に申述する際には、主に以下の書類が必要です。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 【申述人が被相続人の配偶者または子の場合】被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 【申述人が被相続人の孫の場合】子の死亡の記載のある戸籍謄本
- 【申述人が被相続人の父母・祖父母の場合】被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本など
- 収入印紙(1人につき800円分)
- 連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なる)
必要書類は、誰が相続放棄するかによって異なります。
自分で集めるのが難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
相続放棄の流れ
相続放棄の手続きは、概ね以下の流れで進みます。
- 必要書類の収集: 上記の戸籍謄本などを役所で取得します。
- 相続放棄申述書の作成: 裁判所のウェブサイトなどから書式を入手し、必要事項を記入します。
- 家庭裁判所への申述: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、書類一式を提出します。
- 裁判所からの照会: 申述後、裁判所から意思確認のための「照会書」が送られてくるので、回答して返送します。
- 相続放棄申述受理通知書の受領: 裁判所に申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送付され、手続きは完了です。
【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫
相続放棄の注意点・トラブルポイント
相続放棄の注意点・トラブルポイントは、主に以下の通りです。
- マイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も相続できない
- 一度相続放棄すると、撤回はできない
- 相続放棄できないケースもある
- 金銭的な利益は得られないため、勿体ない
- 遺言書の有無の確認
- 団体信用生命保険(団信)への加入状況の確認
- 【共有名義不動産の場合】遺産分割協議の難航
- 【共有名義不動産の場合】管理や売却における共有者間の意見の相違
- 【共有名義不動産の場合】共有名義特有の税金問題
注意点①:マイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も相続できない
繰り返しになりますが、相続放棄は「すべてを捨てる」手続きです。
後から価値のある財産が見つかっても、相続する権利を主張することはできません。
熟慮期間内に、弁護士などに依頼して財産調査をしっかりと行うことが重要です。
注意点②:一度相続放棄すると、撤回はできない
家庭裁判所に相続放棄が受理された後は、「やはり相続したい」と思っても、原則として撤回(取り消し)はできません。
詐欺や脅迫によって無理やり相続放棄させられたなど、特別な事情がない限り覆すことは困難です。
注意点③:相続放棄できないケースもある
被相続人の財産を一部でも使ってしまったり、売却してしまったりすると、「相続の意思がある(単純承認した)」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
これを「法定単純承認」といいます。
例えば、被相続人の預金を引き出して自分のために使ったり、不動産を勝手に売却したりする行為は絶対に避けてください。
【センチュリー21中央プロパティー】共有持分の放棄・売却の無料相談はこちら ≫
注意点④:金銭的な利益は得られないため、勿体ない
共有持分は、れっきとした財産権です。
たとえ活用が難しい不動産であっても、専門業者に売却すれば現金化できる可能性があります。
安易に相続放棄をすると、本来得られたはずの金銭的な利益を失うことになり、非常にもったいないケースも少なくありません。
センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫
注意点⑤:遺言書の有無の確認
もし被相続人が遺言書を遺していた場合、相続の仕方が遺言の内容によって左右されることがあります。
相続放棄を検討する前に、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
注意点⑥:団体信用生命保険(団信)への加入状況の確認
被相続人が住宅ローンを組んでいた場合、団体信用生命保険(団信)に加入している可能性があります。
団信に加入していれば、被相続人の死亡によってローンは完済されるため、マイナスの財産はなくなります。
この場合、相続放棄をする必要はなく、プラスの財産である不動産だけを相続できる可能性があります。
注意点⑦:【共有名義不動産の場合】遺産分割協議の難航
相続放棄をせず共有持分を相続した場合、他の共有者との間で遺産分割協議が必要になります。
しかし、共有者同士の関係性が悪い、意見がまとまらないなどの理由で、協議が難航するケースは非常に多いです。
注意点⑧:【共有名義不動産の場合】管理や売却における共有者間の意見の相違
共有不動産の管理方法や、売却するかどうかで共有者間の意見が対立し、トラブルに発展することがあります。
特に、固定資産税や修繕費などの費用負担で揉めるケースは後を絶ちません。
注意点⑨:【共有名義不動産の場合】共有名義特有の税金問題
共有不動産を売却して利益が出た場合や、賃貸して家賃収入がある場合、確定申告が必要になります。
また、持分を他の共有者に贈与する際には贈与税がかかるなど、共有名義特有の税金問題も発生します。
【相続放棄する前に】共有名義のトラブルを未然に防ぐための選択肢
ここまでお読みいただいたうえで、相続放棄をためらっている方もいるかもしれません。
特に、「マイナスの財産はないが、他の共有者と関わりたくないから放棄したい」と考えている場合、相続放棄以外の方法で、より有利に問題を解決できる可能性があります。
共有名義のトラブルを未然に防ぐための選択肢としては、以下のようなものがあります。
- 共有持分の専門業者への売却
- 他の共有者への売却(持分売買)
- 遺言書や家族信託の活用
選択肢①:共有持分の専門業者への売却
最もおすすめしたい選択肢が、あなた自身の共有持分のみを専門の買取業者に売却することです。
専門業者は、共有持分を買い取った後に他の共有者と交渉するため、あなたは面倒な話し合いから一切解放されます。
他の共有者の同意は不要で、スピーディーに現金化できるのが最大のメリットです。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
選択肢②:他の共有者への売却(持分売買)
もし他の共有者との関係が良好であれば、あなたの持分を買い取ってもらえないか交渉する方法もあります。
他の共有者にとっては、単独名義に近づけるメリットがあります。
ただし、価格交渉が難航したり、そもそも買い取る資金がなかったりする可能性も考慮しなければなりません。
センチュリー21中央プロパティーの【無料】共有持分査定サービスはこちら ≫
選択肢③:遺言書や家族信託の活用
これは将来的な対策になりますが、共有名義の不動産をお持ちの方は、遺言書を作成して相続人を一人に指定したり、家族信託を活用して管理や処分の権限を一人に集約したりすることで、将来の相続トラブルを防ぐことができます。
まとめ
相続はいつ自分に降りかかってくるかわかりません。日ごろから準備をしていたとしても想定外のことが起こりがちです。
相続のトラブルは親族間のトラブルに発展し、修復不可能な絶縁状態になってしまう場合もありますので、不安がある方はまず専門家に相談してみるとよいでしょう。
センチュリー21 中央プロパティーは、共有持分を専門とする不動産会社です。
共有持分のトラブルでお悩みの方は、ぜひご相談ください。
【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫
CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。
相続放棄に関してよくある質問
相続放棄に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.相続放棄の手続きは誰が行う?
A.相続放棄の手続きは、原則として相続放棄をする本人(申述人)が行います。
ただし、本人が未成年者や成年被後見人である場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)が手続きを行います。
また、司法書士や弁護士に依頼して、書類作成や裁判所への提出を代行してもらうことも可能です。
Q2.相続放棄の手続きはどこで行う?
A.相続放棄の申述は、「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申述人自身の住所地を管轄する家庭裁判所ではないので、注意が必要です。
管轄の裁判所がどこかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。
【仲介手数料0円】共有不動産・共有持分専門のセンチュリー21中央プロパティー ≫
CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。