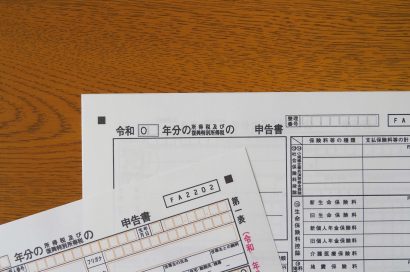準共有とは|共有との違い
準共有とは|共有との違い

1.準共有とは
準共有とは、所有権以外の権利を複数人で持っている状態を指します。(民法264条)
共有との違いは、物質として存在するか否かです。
例えば、不動産は物質として存在するので、共有名義不動産になります。
一方で、借地権のような権利は、物質ではないため、準共有という言葉を使います。
他にも、準共有の具体例として、以下のようなものがあります。
- 用益物権(地上権・地役権)
- 担保物件(抵当権)
- 賃借権
- 著作権
- 特許権
2.共有と準共有の法律上のルール
共有も準共有も法律上のルールは、同じになります。
代表的なルールとして、以下があげられますが、このルールは準共有にも同様に適用されるということです。
| 行為 | 具体例 | 行為の制限 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 共有物の修繕 不法占拠者への明渡請求 共有物侵害への妨害排除請求 | 各共有者が 一人で対応可能 |
| 管理行為 | 賃貸借契約の締結 短期間の賃貸借 | 共有者の持分価格の 過半数で決定 |
| 変更行為(軽微なもの) | 外壁や屋根の修繕 植樹伐採 | 共有者の持分価格の 過半数で決定 |
| 変更行為(軽微以外) | 共有物全体の売却 増改築・建て替え | 共有者の全員の同意が必要 |

この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。