共有名義人が認知症になると不動産を売却できない!?対処法や事前の対策を解説
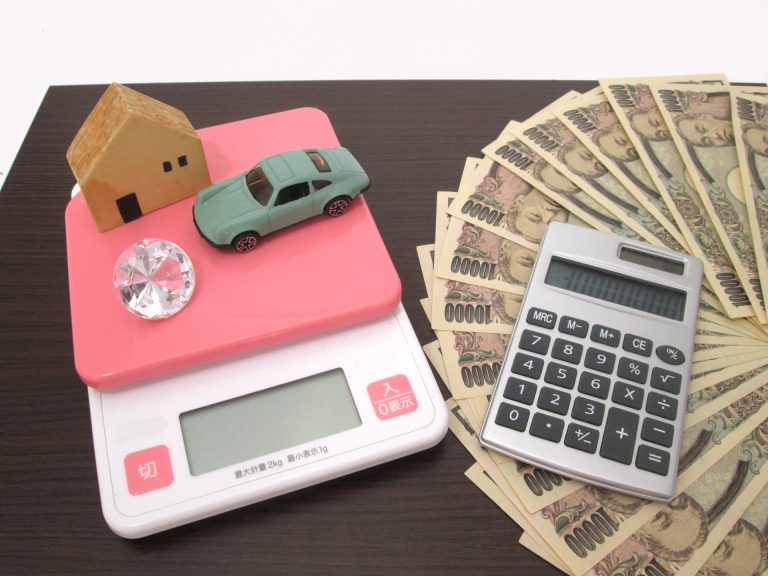
目次
親が認知症になってしまったら、どのようなトラブルが発生し、どう対処していけばいいのか不安になりますよね。
さらに、親と一緒に共有名義の不動産を持っている場合は、より深刻な問題に発展する可能性があります。
例えば、不動産を売却したくても手続きが進められない、相続や資産管理が滞るなど、法的な制約が生じるリスクがあります。
この記事では、不動産の共有者に認知症の人がいる場合の対処法や事前の対策について解説します。
共有者が認知症になると不動産の売却は難しくなる
まず結論から言うと、親など共有者の一人が認知症になることで、共有名義の不動産全体の売却は極めて難しくなります。
これは、認知症の共有者は「法律上の判断能力・意思能力がない」ものとみなされてしまうことが原因です。
たとえ認知症を患った本人が委任状を作成したとしても、その委任状を作成した時点で意思能力がなければ、委任自体が無効と判断されます。
共有名義不動産の売却は、「共有者全員の同意」が条件です。
しかし、認知症が進行している共有者が「共有名義不動産を売ることに同意する」と言っても、上記の理由からその同意は買主や不動産会社・また司法書士などから認められないケースが多くなります。
結果として、不動産全体の売却手続きに進めなくなってしまうのです。
| ◆認知症の共有者の同意が認められない理由 ▼買主や不動産会社 売買成立後に、他の共有者や親族などから「契約当時は意思能力がなかった」と主張されるリスクを未然に防ぐため。 ▼司法書士 不動産売買に伴う所有権移転登記の際に行う売主全員の本人確認と意思確認において「意思能力に疑いあり」と判断した場合、士業の職責上、登記手続きを進めることができない。 |
このような背景から、例えば「親が介護施設へ入所することになり、その費用を捻出するために実家を売りたい」と考えても、簡単には売却手続きを進められないのです。
共有者の中に認知症の人がいる場合の不動産売却について、どのような手続きが必要になるかは、以下の章で詳しく解説します。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
認知症になった親と自分との共有名義不動産を売却する方法と事前対策
不動産の共有者である親が認知症になった際、その不動産を売却、または将来の売却に備えて管理する方法として、主に以下の4つがあります。
- 【認知症後の売却方法】法定後見人制度を利用する
- 【事前対策】任意後見人制度を利用する
- 【事前対策】家族信託(民事信託)を利用する
- 【事前対策】生前贈与を利用する
方法①:【認知症後の売却方法】法定後見人制度を利用する
共有者が認知症になった後、不動産売却のために唯一選べる手段が「法定後見人」制度を利用することです。
法定後見人制度は、親族などが家庭裁判所に申し立てて審理を経ることで、本人を法的に支援しその代理を務める「成年後見人」を選任し、判断能力を失った本人の財産を維持管理する制度です。
多くの場合、法定後見人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
この法定後見人は、「本人の生活に必要不可欠な財産か否か」を第一に考えて財産管理を行うため、他の共有者が共有名義不動産の売却による利益を得ることだけを目的とする場合や、認知症の共有者本人がその不動産に現在も居住している場合などには売却の同意が得られないこともあります。
しかし、「介護費用や医療費を支払うために、自宅を売却する以外に方法がない」といったやむを得ない事情があり、後見人も「本人の利益になる」と判断した場合は、本人に代わって売買契約に同意し、売却手続きを進めることが可能です。
このような、ある意味での「融通の効かなさ」に加え、申し立ててから後見人の選任まで数カ月かかることや、後見人への報酬が発生することなどにも注意が必要です。
センチュリー21中央プロパティーなら共有持分の売却を無料でサポート ≫
方法②:【事前対策】任意後見人制度を利用する
ここからは、親などの共有者が認知症になる前に、不動産の売却をスムーズに行えるよう打っておくべき対策となります。
最初にご紹介する事前対策は、「任意後見人」制度を利用することです。
こちらは、裁判所によって選任される法定後見人とは異なり、共有者本人の判断能力が十分なうちに自分で後見人を選任できることが大きな特徴といえます。
任意後見人は、選任した本人と代理権についての契約書を結びます。
この契約書の効力は、親の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てをし、任意後見人を監督する役割の「任意後見監督人」が選任されることで生じるものです。
契約時に定めた代理権の範囲内であれば、不動産の売却やそれに伴う登記手続きを行うことができるため、本人が認知症になっても任意後見人の同意によって共有名義不動産の売却手続きを進めることが可能になります。
センチュリー21中央プロパティーなら共有持分の売却を無料でサポート ≫
方法③:【事前対策】家族信託(民事信託)を利用する
2つ目の事前対策として、「家族信託(民事信託)」の利用を解説します。
家族信託(民事信託)とは、本人の存命中に「信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる契約を結んでおく」制度のことで、親の認知症対策として近年注目を浴びている生前対策です。
不動産の場合、認知症の事前対策をしたい親が「委託者」となり、信頼できる子どもなどの家族の1人を「受託者」として、財産の管理権限を移します。
その後、受託者自身やその配偶者を「受益者」と定め、不動産から生じる利益(自分の持分による賃料収入など)があればそれを受け取れるようにします。
この利益を受け取る権利は、親の死後には親が指定した人物(受託者を含む子どもなど)に引き継がれていきます。
しかし、不動産そのものは管理権限を移した時点で受託者の単独名義となるので、親は共有者ではなくなります。そのため、家族信託を結んでおけば親が認知症になった後も問題なく不動産を売却できるのです。
このように非常に自由度が高く便利な家族信託ですが、実際に行うためには多くの専門知識が必要です。
弁護士や司法書士などに依頼する場合は数十万~100万円以上の費用がかかるケースもあるため、この点は注意しましょう。
センチュリー21中央プロパティーなら共有持分の売却を無料でサポート ≫
方法④:【事前対策】生前贈与を利用する
3つ目の事前対策として、「生前贈与」の利用を解説します。
これは、家族信託よりもシンプルに「存命中に持分を子どもなどの他の共有者に無償で譲渡する」という方法です。
こうした生前贈与が成立すれば親は不動産の共有者でなくなるため、親が認知症になったり死亡した際にも不動産売却の同意を巡る手間は発生しません。
しかし、贈与された不動産の評価額によっては高額な贈与税がかかる可能性があり、その他にも不動産取得税や登録免許税などもかかるため、税金の負担が大きくなる点には注意が必要です。
なお、贈与税の納税義務は、贈与を受けた側(受贈者)が負うことになります。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
親が認知症になる前に共有名義不動産の売却を急ぐべき理由
ここからは、特に注意が必要な「共有名義の不動産」について深掘りしていきます。
共有名義の不動産は、共有者全員の同意を得ないと管理や処分を行えないことが多いため、もし親が認知症になってしまうと様々な問題が発生します。
そのため、認知症になる前に共有名義を解消しておくことが極めて重要なのです。
共有名義の不動産を事前に対処すべき理由は、以下の通りです。
- 共有名義全体を売却するには全員の合意が必要なため
- 認知症になるとその共有者の同意が得られなくなるため
理由①:共有名義全体を売却するには全員の合意が必要なため
共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員の合意が必要です。
これは民法第251条第1項で定められている重要なルールです。
もし共有者の間で意見が割れると、不動産全体の活用や処分は自由にできません。
不動産全体の売却だけでなく、建て替えのような大きな変更(法律上「変更行為」と呼ばれます)を加える際にも、共有者全員の同意が必要です。
このように、共有状態では不動産の利用に制限がかかるリスクがあります。
理由②:認知症になるとその共有者の同意が得られなくなるため
もし共有者の一人である親が認知症になると、問題がさらに深刻になります。
冒頭でお伝えした通り、認知症が進行するとその人は法律上「意思能力がない」とみなされ、有効な法律行為(契約など)ができなくなるためです。
つまり、認知症になった共有者から法的に有効な同意を得ることができず、結果として不動産全体の売却や活用が不可能になってしまうのです。
例えば、子供たちが空き家となった実家を売却しようとしても、親が認知症になっていて同意が得られないようなら、実家の処分は極めて困難になります。
このような事態にならないためにも、親が認知症になる前に共有名義不動産の対策を講じておくことが極めて重要です。
仲介手数料無料&初回相談から社内弁護士が同席!持分の売却なら中央プロパティー ≫
認知症が進行する前に共有名義の不動産でしておきたいこと
共有名義の不動産に関する将来の問題を回避するには、親の判断能力がはっきりしているうちの対策が不可欠です。
認知症が進行する前に検討すべき、共有名義不動産の対処法としては以下のものがあります。
- 共有名義から単独名義に変更する
- 親自身の共有持分を手放すように促す
対処法①:共有名義から単独名義に変更する
共有名義の不動産に関するリスクを軽減する効果的な方法は、共有名義から単独名義に変更することです。
単独名義に変更すれば、他の共有者の合意を得なくても不動産全体の売却や活用が可能となります。
したがって、将来的に不動産を手放したいと考えているなら、単独名義にしておく方が圧倒的に処分しやすくなります。
また、相続時のトラブルを防ぐためにも、単独名義化は有効な対策といえるでしょう。
親の不動産を共有名義から単独名義に変更する具体的な方法としては、以下のものがあります。
- 親に持分を贈与してもらい単独名義にする
- 親の共有持分を子が買い取り単独名義にする
◆親に持分を贈与してもらい単独名義にする
親の持分を子に贈与して、子が単独で所有する状態にする方法です。
ただし、この場合は「暦年贈与」にあたるため、年間110万円の基礎控除額を超える部分に対して贈与税がかかる点に注意が必要です。
なお、一定の要件を満たす場合(贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫)、より大きな非課税枠が利用できる「相続時精算課税制度」を選択することも可能です。
相続時精算課税制度とは、生前贈与と相続を一体として課税する制度で、累計2,500万円までの贈与については特別控除として贈与税が非課税となります。
特に、2024年1月1日以降の贈与からは、この2,500万円の特別控除とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。
この基礎控除の範囲内であれば、贈与税の申告は不要で、将来の相続財産に加算されることもありません。
なお、2,500万円を超えた分の額には一律20%の贈与税がかかります。
センチュリー21中央プロパティーなら共有持分の売却を無料でサポート ≫
◆親の共有持分を子が買い取り単独名義にする
もう一つは、子と親2人の共有名義であれば、子が親の共有持分を買い取る形で単独名義にする方法です。
この場合、親子間の取引であっても契約書を作成しておくことが重要になります。
なぜなら、口約束はトラブルのもとになるためです。
売買価格や条件などで揉めないためにも、契約書を必ず作成しておきましょう。
また、買い取りの際に極端に安い価格で取引をすると、差額分が贈与とみなされ(みなし贈与)、思わぬ贈与税が課される可能性があるため注意しましょう。
もし共有部分を買い取って単独名義にしたい場合は、不動産の評価額や取引相場を考慮しつつ、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
共有名義の不動産を単独名義する詳しい方法は、以下の記事で解説しています。
共有名義から単独名義に変更する際の費用とは?手続きの流れや注意点
対処法②:親自身の共有持分を手放すように促す
もし単独名義化が難しい場合、親自身の共有持分のみを売却して、共有関係から抜け出す方法もあります。
重要なのは、自分が所有する共有持分のみの売却であれば、他の共有者の同意は不要であるという点です。
したがって、他の共有者の反対にあうこともなく、共有持分を手放せます。
共有持分の売却には主に二つの方法があります。
一つは買取業者に直接買い取ってもらう方法、もう一つは不動産の仲介業者を利用して第三者に売却する方法です。
一般的に買取業者よりも仲介業者、特に共有持分専門の仲介業者を選ぶ方が、より高値での売却が期待できます。
これは、買取業者が自社の利益のために安く仕入れることを目的とするのに対し、仲介業者は売却価格に応じて手数料(仲介手数料)が決まるため、より高く売却しようという売主の目的と一致しやすいためです。
センチュリー21中央プロパティーなら共有持分の売却を無料でサポート ≫
もし共有名義の不動産があったら親が認知症になる前に解消しよう
本記事では、不動産を所有する親が認知症になった場合の様々な問題と対策を解説しました。
共有名義の不動産は、所有者全員の合意が必要な場面が多く、共有者の一人である親が認知症になると完全に身動きが取れなくなってしまいます。
これは、単独名義の不動産よりもはるかに深刻なリスクです。
だからこそ、親の判断能力がはっきりしているうちに、将来の介護や医療費をどうするかを含め、不動産の取り扱いについて家族で話し合うことが何よりも大切です。
当社、センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。
一般市場での売却が難しいとされる共有持分も、不動産鑑定士による厳密な査定と、独自の”買い手ネットワーク”を活用することで、お客様にとってより良い条件での売却を目指しています。
もちろん、将来のトラブルを避けるために共有名義を解消したいと考えているお客様の相談も受け付けています。
また、共有者の中に認知症の方がいらっしゃる場合でも、ご相談に応じてさまざまなご提案が可能です。
共有名義不動産や共有持分の現金化・売却に関するお悩みやご不明な点がある人は、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
センチュリー21中央プロパティーなら共有持分の売却を無料でサポート ≫
CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。








