離婚前に共有持分の売却はできるのか?弁護士が解説
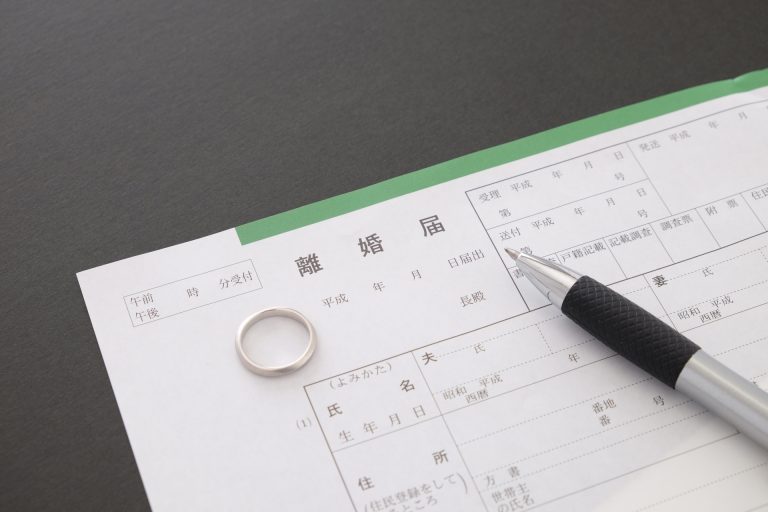
目次
離婚が決まった際、夫婦共有名義の自宅をどうするかは大きな問題です。
「早く自分の持分だけ売って現金化したい」「元配偶者と関わらずに手放したい」と考える方は少なくありません。
結論から言うと、離婚前でも共有持分の単独売却は可能です。
しかし、実行する際には、後の財産分与や他の共有者(配偶者)との深刻な法的トラブルにつながるリスクを理解しておく必要があります。
この記事では、離婚前の共有持分売却における法的な可否と、売却を進める際の最大の注意点、そして財産分与を有利に進めるための具体的な戦略を弁護士が詳しく解説します。
【完全無料】共有不動産のトラブルならセンチュリー21中央プロパティー ≫
離婚前でも共有持分の売却はできる

離婚協議中であっても、夫婦共有名義の不動産における自己の持分を第三者に売却することは、法律上は可能です。
民法では、各共有者が自分の持分を自由に処分できるとされており、原則として他の共有者(元配偶者)の同意は不要とされています。
しかし、離婚を前提とした協議中や訴訟中の場合、話は単純ではありません。
不動産が婚姻期間中に取得されたものであれば、それは「夫婦の共有財産(共同財産)」とみなされ、持分の登記割合だけで財産分与の判断がされるとは限りません。
例えば、夫Aが7割、妻Bが3割の持分で自宅を購入したケースでも、妻が家事・育児などで家庭に貢献していたと認められれば、妻は不動産全体の2分の1を財産分与として請求できる可能性があります。
そのため、離婚前に自分の持分を売却してお金を得ても、その売却益は「夫婦で築いた共有財産の一部」と見なされ、最終的に財産分与の対象となる(折半される)可能性が高いのです。
つまり、離婚前に持分を急いで売却しても、金銭的なメリットはほとんど得られません。
場合によっては、後の協議や裁判で不利になることもあるため、売却を検討する前に弁護士など専門家への相談を強くおすすめします。
離婚後の共有持分売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
財産分与の確定前に「共有物分割請求訴訟」はできない

離婚前や離婚協議中でも、夫婦共有名義の不動産について共有物分割請求訴訟を起こすこと自体は、法的に可能です。
共有物分割請求とは、不動産などの共有財産について、共有者のうちの一人が他の共有者に対し、共有状態の解消(分割)を求めることを指します。
民法第256条
「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」
しかし、夫婦間の共有財産――特に自宅のような重要な資産については、単純に「持分を分け合う」だけでなく、離婚時の財産分与の一環として包括的に解決されるべきという考え方が裁判実務では強く支持されています。
そのため、財産分与の協議・調停・離婚訴訟が進行中にもかかわらず、一方的に共有物分割訴訟を起こすと、「権利の濫用」と判断されて請求が認められない可能性が高いのです。
裁判所が「権利の濫用」と判断する主な理由
財産分与の趣旨との矛盾
離婚時の財産は、登記上の名義や持分割合だけでなく、夫婦の協力・貢献を踏まえて分けられるべきという制度趣旨があるため、個別に分割請求をするのは原則に反します。
相手方への不利益が大きい
たとえば、妻が子どもと一緒に住み続けたいと希望している家を、夫が競売を目的に分割請求するような場合、住居を失うなど相手に過大な不利益が生じるため、裁判所は認めにくくなります。
手続きの重複による非効率
財産分与の場で不動産の処理も含めて解決できるのに、別途分割訴訟を起こすことは無駄が多く、裁判の効率性を損ないます。
請求者の意図が不適切
分割請求が相手への嫌がらせや、財産分与を不利に進めるための手段とみなされる場合、権利行使そのものが不当と判断される可能性があります。
参考判例
いくつかの判例では、「形式的には請求できても、実際に認められるかは別問題」として、共有物分割請求が認められないケースが多数あります。
東京高裁(平成26年8月21日判決)では、「共有物分割請求が著しく不合理で、相手にとって非常に酷な結果になる場合は、権利の濫用として却下すべき」としています。
♦参考判例(2):東京高裁平成26年8月21日判決
「民法258条に基づく共有者の他の共有者に対する共有物分割権の行使が権利の濫用に当たるか否かは、当該共有関係の目的、性質、当該共有者間の身分関係及び権利義務関係等を考察した上、共有物分割権の行使が実現されることによって行使者が受ける利益と行使される者が受ける不利益等の客観的事情のほか、共有物分割を求める者の意図とこれを拒む者の意図等の主観的事情をも考慮して判断するのが相当であり(最高裁判所平成7年3月28日第三小法廷判決・裁判集民事174号903頁参照)、これらの諸事情を総合考慮して、その共有物分割権の行使の実現が著しく不合理であり、行使される者にとって甚だ酷であると認められる場合には権利濫用として許されないと解するのが相当である」
離婚後の共有持分売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
離婚後は自身の持分を自由に売却できる

離婚が成立し、財産分与も完了していれば、各自の不動産持分(共有持分)は確定した個人の財産となります。
この状態であれば、自分の共有持分を第三者に売却したり、共有関係を解消するために共有物分割請求を行ったりすることが法的に問題なく可能です。
これは民法206条に基づく基本的な権利であり、売却にあたって元配偶者(他の共有者)の同意は必要ありません。
また、売却によって得た代金は個人の資産となり、元配偶者に分配する必要もありません。
【完全無料】共有不動産のトラブルならセンチュリー21中央プロパティー ≫
離婚後、財産分与が終了すれば共有物分割請求もできる

離婚後、財産分与が完了していれば、民法256条に基づいて共有物分割請求訴訟を起こすことも可能です。
離婚前と異なり、すでに夫婦関係が終了しているため、「権利の濫用」として却下される可能性は非常に低く、通常の共有不動産と同じように法的手続きを進めることができます。
共有物分割請求訴訟が提起された場合、裁判所は以下のいずれかの方法で共有状態の解消を命じることが一般的です。
- 現物分割
土地を物理的に分けるなど。建物には適用が難しい。 - 代償分割
共有者の一方が不動産を単独で取得し、他の共有者にその持分に応じた金銭(代償金)を支払う。 - 換価分割(競売)
不動産を売却して代金を分配する方法。
特に、円満な合意が難しい場合や、特定の共有者が金銭的余裕がない場合は、最終的に不動産が競売にかけられる「換価分割」となる可能性もあります。
競売では市場価格より安く売却されるケースが多いため、結果的に損となることもあります。
離婚後の共有持分売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
離婚後は単独名義への変更がおすすめ

離婚が成立した後は、夫婦で共同購入した自宅を速やかに単独名義へ変更することを強くお勧めします。
共有名義のままでは、将来的な売却や大規模修繕に際して元配偶者の同意が常に必要となり、意見の対立や連絡の煩雑さからトラブルに発展しやすいためです。
単独名義への切り替えで最大のハードルとなるのが、住宅ローンの残債です。
ローンが残っている場合、金融機関の承諾が不可欠であり、住み続ける側の単独での返済能力が厳しく審査されます。
しかし、煩雑な共同名義状態を解消し、財産の処分・管理権を明確にするために、ローン借り換えや連帯保証人の設定といった対策を講じてでも単独名義への変更を目指すことが、後のトラブル回避に繋がります。
離婚後の共有持分売却ならセンチュリー21中央プロパティー
離婚協議中に、共有名義不動産の自分の持分を売却することは、法的には可能です。
しかし、これが賢明な選択肢とは限りません。
確かに、自身の持分は自由に処分できますが、買い手は非常に限られ、市場価格より大幅に安くなるのが一般的です。
さらに、売却益は最終的に財産分与の対象となり、夫婦関係や離婚交渉がさらにこじれる大きなリスクも伴います。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産会社です。
社内弁護士が在籍しているため、元配偶者とのトラブルを防ぎながら売却をサポートします。離婚後に共有持分のご売却を検討されている方は、センチュリー21中央プロパティーへご相談ください。
離婚後の共有持分売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。







