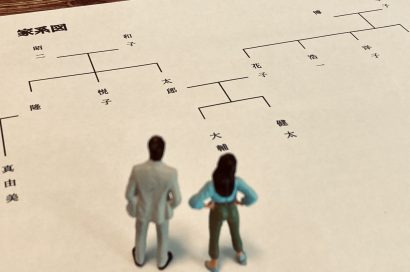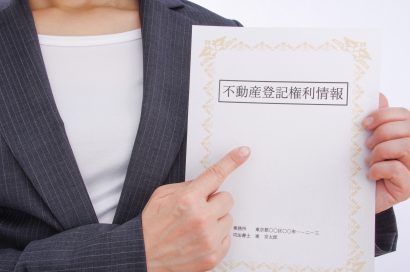「制限行為能力者」がいる場合の遺産分割の進め方・手続きを解説

目次
「父が亡くなり実家の土地を3人で相続したけれど、一番下の弟がまだ未成年だ…」
「相続人の一人である母が認知症で、遺産分割の話ができる状態ではない…」
このように、相続人の中に未成年者や、病気や高齢で判断能力に不安がある方がいる場合、遺産分割協議をどのように進めればよいのでしょうか。
実は、判断能力が不十分な方がいる相続手続きは、通常通りには進められません。
ご自身の判断で安易に進めてしまうと、後からその遺産分割協議自体が無効になってしまう可能性があります。
この記事では、相続人に「制限行為能力者」が含まれる場合の遺産分割について、法的なルールや正しい手続きの進め方を分かりやすく解説します。

「制限行為能力者制度」とは、判断能力が不十分な人を保護する制度のこと
制限行為能力者制度とは、未成年者や、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により物事を判断する能力(事理を弁識する能力)が不十分な方々を、法的に保護するための制度です。
不動産の売買や遺産分割協議といった重要な法律行為を、本人が不利な内容だと気づかないまま契約してしまうといった事態を防ぐことを目的としています。
この制度により、制限行為能力者が単独で行った契約などの法律行為は、後から取り消すことが可能になります。
【社内弁護士が常駐】共有不動産の相続トラブルはセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫
制限行為能力者の4類型と遺産分割の進め方
制限行為能力者は、判断能力の程度に応じて、以下の4つの類型に分けられます。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
遺産分割を進めるには、相続人がどの類型に当てはまるかを確認し、それぞれに定められた手続きに則って対応しなければなりません。
類型①:未成年者
相続人が18歳未満の未成年者である場合、法律行為を単独で行うことができません。
そのため、法定代理人が本人に代わって手続きを行う必要があります。
保護者の役割と必要な手続き
相続人が18歳未満の未成年者である場合、原則として親権者(父母など)が法定代理人として、本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
しかし、親権者自身も同じ遺産分割の相続人である場合、状況は変わります。
なぜなら、親権者が自身の相続分を多くするために、子の利益を犠牲にする可能性があるからです。
このように、親と子の利益が対立する状況を「利益相反」と呼びます。
遺産分割協議は、客観的に利益相反行為に該当するため、親権者が未成年者の代理人として協議を進めることはできません。
この場合、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任してもらう必要があります(民法第826条)。
特別代理人には、利害関係のない親族や、弁護士・司法書士などの専門家が選ばれます。
特別代理人の選任をせずに親権者が勝手に行った遺産分割協議は無効になりますので、注意が必要です。
【社内弁護士が常駐】共有不動産の相続トラブルはセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫
類型②:成年被後見人
精神上の障害により、常に物事を判断する能力がない状態にある方が対象です。
家庭裁判所による後見開始の審判を受けることで「成年被後見人」となります。
保護者の役割と必要な手続き
「成年被後見人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者として、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた方を指します(民法第7条)。
具体的には、重度の認知症の方などが該当します。
成年被後見人が相続人にいる場合、遺産分割協議はその内容を理解できないため、本人に署名捺印をさせて協議を成立させることはできません。
勝手に署名押印するような行為は、無効になるだけでなく、場合によっては犯罪行為とされる恐れもあります。
この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
選任された成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加し、法律行為を行います。
【社内弁護士が常駐】共有不動産のトラブル・売却はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫
類型③:被保佐人
精神上の障害により、物事を判断する能力が著しく不十分な方が対象です。
家庭裁判所による保佐開始の審判を受けることで「被保佐人」となります。
保護者の役割と必要な手続き
「被保佐人」とは、精神上の障害により!事理を弁識する能力が著しく不十分である者!として、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた方を指します(民法第11条)。
日常の買い物程度は一人でできますが、不動産の売買や遺産分割といった重要な財産行為を単独で行うには不安がある、という方が該当します。
被保佐人が遺産分割協議を行うには、「保佐人」の同意が必要です。
本人が協議に参加することは可能ですが、保佐人の同意を得ずに成立させた遺産分割協議は、後から取り消される可能性があります。
【社内弁護士に無料で相談】共有不動産の相続トラブルはセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫
類型④:被補助人
精神上の障害により、物事を判断する能力が不十分な方が対象です。
4類型の中では最も症状が軽く、家庭裁判所による補助開始の審判を受けることで「被補助人」となります。
保護者の役割と必要な手続き
「被補助人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者として、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた方を指します(民法第15条)。
4類型の中では最も判断能力の程度が高い状態です。
被補助人の場合、原則として単独で法律行為ができますが、家庭裁判所の審判によって、遺産分割などの特定の法律行為について「補助人」の同意が必要と定められている場合があります。
その場合は、補助人の同意を得なければ有効な遺産分割協議とはなりません。
【センチュリー21中央プロパティー】共有名義の解消に関する無料相談はこちら ≫

成年後見人・保佐人・補助人の権限比較
成年後見人、保佐人、補助人は、本人の判断能力のレベルに応じて、与えられる権限の範囲が異なります。
その違いを理解することで、ご自身のケースでどのようなサポートが必要になるのかを把握しやすくなります。
| 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
| 対象となる方 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 (重度の認知症など) | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者 (4類型の中で最も症状が軽い) |
| 申立てができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官 | 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官 | 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官 |
| 同意権の有無 | なし (本人が法律行為を行えないため) | あり (重要な法律行為には保佐人の同意が必要) | あり (特定の法律行為について補助人の同意が必要な場合がある) |
| 取消権の範囲 | 成年被後見人が単独で行った法律行為は原則すべて取り消し可能 | 同意を得ずに行った重要な法律行為は取り消し可能 | 同意を得ずに行った特定の法律行為は取り消し可能 (審判で定められた範囲) |
| 代理権の有無 | あり (成年後見人が本人の代わりに法律行為を行う) | 原則なし (審判により特定の法律行為について代理権が付与される場合あり) | 原則なし (審判により特定の法律行為について代理権が付与される場合あり) |
このように、成年後見制度を利用した遺産分割は手続きが複雑です。
特に、遺産に共有名義の不動産が含まれている場合、権利関係がさらに複雑になり、当事者だけでの解決は困難を極めます。
センチュリー21中央プロパティーは、これまで4万件以上の共有持分トラブルを解決してきた豊富なノウハウがあります。
社内弁護士が常駐しているほか、司法書士や税理士といった専門家とも連携し、お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提供しますので、安心してご相談ください。

制限行為能力者が行った契約の効力
では、もし保護者の同意なく、制限行為能力者本人が勝手に契約などを結んでしまった場合、その契約はどうなるのでしょうか。
法律で定められたルールを知っておきましょう。
原則:取り消しができる(取消権)
制限行為能力者が、保護者の同意を得ずに単独で行った契約などの法律行為は、原則として後から取り消すことができます。
これは、判断能力の不十分な人を不利益な契約から守るための、強力な権利です。
例外①:有効だと認める(追認)
取り消すことができる行為を、後から有効なものとして確定させることを「追認」といいます。
保護者(法定代理人、保佐人、補助人など)が追認した場合、その契約は取り消せなくなります。
例外②:追認したとみなされる(法定追認)
保護者が明確に「追認する」と言わなくても、特定の行動をとった場合には法律上、追認したとみなされることがあります。
これを「法定追認」といいます。
例えば、契約後に相手方から代金を受け取るなどの行為が該当します。
例外③:相手を騙した場合(詐術)
制限行為能力者が、「自分は能力者である」と偽ったり、保護者の同意を得ているように見せかけたりして相手を信用させた場合、その契約は取り消すことができません。
このような行為を「詐術」といい、不誠実な制限行為能力者まで保護する必要はないという考えに基づいています。
【社内弁護士が常駐】共有不動産のトラブル・売却はセンチュリー21中央プロパティーにお任せください ≫
まとめ
本記事で解説した、制限行為能力者が相続人にいる場合の遺産分割の重要ポイントを改めて確認しましょう。
- 相続人に制限行為能力者がいる場合、遺産分割協議は通常の手順では進められない。
- 未成年者との利益相反が生じる際は、家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要になる。
- 判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任し、法的な手続きを踏む必要がある。
- 正しい手続きを経ないと、遺産分割協議そのものが後から「無効」となる重大なリスクがある。
このように、制限行為能力者が関わる相続は法的な専門知識が不可欠です。
特に遺産に不動産が含まれる場合、手続きはさらに複雑化し、「共有持分」を巡るトラブルにも発展しやすくなります。
当社センチュリー21中央プロパティーは、まさにそのような複雑な相続から生じる「共有持分」のトラブル解決・売却を専門としています。
共有持分の問題に精通した社内弁護士が初回相談から同席し、お客様の状況に合わせた的確な法的アドバイスをご提供。
煩雑な相続手続きのお悩みから、その後の不動産の最適な活用・売却戦略まで、ワンストップで力強くサポートいたします。
ご相談は無料です。
複雑な共有持分の相続でお困りの方は、一人で悩まず、まずは私たち専門家にご相談ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。