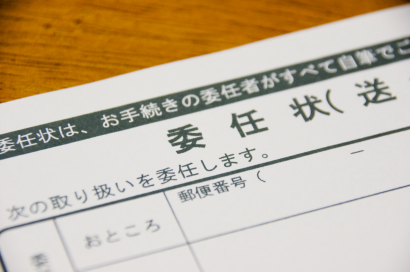共有者が行方不明でも大丈夫!共有不動産を売却する方法4選
共有者行方不明でも大丈夫!不動産を売却・活用する方法とリスク対策

共有名義不動産の、共有者が行方不明で売却を諦めていませんか?実は、適切な法的な手続きを活用することで、共有者不在でも不動産を売却できる選択肢があります。
この記事では、共有者が行方不明の場合に有効な最新の4つの方法を分かりやすく解説します。

共有者が行方不明の場合に起こる問題点
共有者の中に行方不明者がいる場合、以下のような問題が発生します。
- 不動産の活用制限
- 管理費用の負担増
- 「特定空き家」に指定される恐れ
- 相続による権利関係の複雑化
- 他の共有者同士のトラブル
不動産の活用制限
共有不動産を売却、増改築、長期間賃貸に出すなどの場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。しかし、共有者が行方不明の場合、この同意を得ることができず、不動産を活用することが困難になります。
管理費用の負担増
共有不動産の管理費用(固定資産税、修繕費など)は、共有者全員で負担する必要があります(民法第253条)。 しかし、共有者が行方不明の場合、その負担分を他の共有者が肩代わりしなければならず、経済的な負担が増加します。
「特定空き家」に指定される恐れ
共有不動産が空き家になっている場合、老朽化の進行や適切な管理がなされないことにより、自治体から「特定空き家」に指定されるリスクがあります。 特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除されて増額されたり、行政による助言・指導、勧告を経て強制解体の対象となる可能性もあります(空家等対策の推進に関する特別措置法)。
また、倒壊のリスクや治安の悪化などで、近隣に迷惑をかけるリスクもあります。
相続による権利関係の複雑化
共有者に相続が発生すると、共有者が更に増え、権利関係が複雑になります。例えば、行方不明の共有者に子どもがいる場合、その子どもたちが新たな共有者となり、連絡を取るべき相手がさらに増えてしまいます。 共有者が多くなることで、全員の所在特定や意思統一ができず、不動産の活用がさらに難しくなります。
他の共有者同士のトラブル
行方不明の共有者がいることで、他の共有者間での意見対立や訴訟問題が発生するリスクもあります。 例えば、他の共有者が不動産を売却したいと考えていても、一部の共有者の同意が得られない場合(行方不明のため)、その負担を巡って訴訟に発展する可能性があります。

行方不明の共有者を探す方法
行方不明の共有者を探す方法は、主に以下の方法があります。
1. 親族・知人への聞き込み
まずは、行方不明の共有者の親族や知人に連絡を取り、手がかりを求めて情報収集を試みましょう。意外な場所で連絡が取れる可能性があります。
2. 共有不動産の登記簿での確認
共有不動産の登記簿謄本には、共有者の氏名と住所が記載されています。 ここに記載されている住所が最新の住所ではない可能性もありますが、まずは手がかりとして確認すべき情報です。
3. 弁護士を通じた住民票・戸籍の調査
共有者の所在を法的に調査したい場合は、弁護士に依頼するのが効果的です。 弁護士は、職務上請求権に基づき、住民票や戸籍謄本を役所から取得できます。 これにより、共有者の現在の住所や、すでに死亡している場合はその事実を確認できる可能性があります。
4. 探偵調査の検討
上記の方法でも所在が判明しない場合、探偵に調査を依頼することも一つの選択肢です。 探偵は専門的なノウハウとネットワークを使い、行方不明者の所在を突き止める調査を行います。 ただし、費用が高額になる傾向があるため、他の方法を試した上での最終手段として検討しましょう。
【補足】不在者財産管理人制度の利用
不在者財産管理人制度の利用は、厳密には「行方不明者を探す方法」というよりは「行方不明者の財産を管理・処分する方法」の一部です。そのため、ここではあくまで制度の存在に触れるに留め、詳細は後述します。
とは言え、行方不明の共有者がいることによって、不動産の活用や処分の制限がかかるのでは、他の共有者は困ってしまいます。
そこで、次の章では、行方不明の共有者がいる場合でも、共有不動産の活用や処分が実現する専門的な方法を紹介します。
【2023年民法改正対応】共有者が行方不明でも不動産を処分・活用する方法
共有者が行方不明の場合に、共有不動産を活用・処分する方法は以下の通りです。
- 不在者財産管理人制度
- 失踪宣告
- 所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度
- 自己持分のみを売却する
1. 不在者財産管理人制度
不在者財産管理人制度とは、不在者(行方不明者)の財産を管理・処分するために、家庭裁判所が選任した管理人によって、その財産を保全・管理する制度です。
つまり、不在者財産管理人が、行方不明者に代わって共有不動産の活用や処分の意思決定ができるようになります。
不在者財産管理人制度の手続きの流れ
不在者財産管理人制度の手続きは以下の通りです。
- 手順1:家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立て
- 申立て:不在者の利害関係者(他の共有者など)が、不在者の最後の住所地または不動産の所在地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
- 申立書、戸籍謄本、不在者の財産目録などの書類が必要です。
- 手順2:家庭裁判所での審理・審判
- 家庭裁判所が提出書類の審査や必要な調査を行い、不在者財産管理人を選任します。
- 選任された管理人は、不在者の財産状況を調査し、財産目録を作成します。
- 手順3:不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て
- 不在者財産管理人が不動産の売却など、財産を処分する場合は、別途、家庭裁判所の許可を得る必要があります。これは、管理人が不在者の利益を不当に損なわないための重要な手続きです。
申立ては、不在者の利害関係者なら誰でも行えます。
ただし、裁判所が選任する管理人は、申立人が希望する候補者とは限りません。また、財産の処分には、別途裁判所の許可が必要です。管理費用は不在者の財産から賄われますが、財産が少ない場合は申立人が一時的に負担するケースもあります。
2. 失踪宣告
失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間継続した場合に、法律上死亡したものとみなす制度です。失踪宣告を受けると、不在者は死亡したものとして扱われるため、共有持分は相続人に引き継がれます。相続人が同意すれば、共有不動産の活用や処分ができるようになります。
失踪宣告の種類
失踪宣告には、以下の2つの種類があります。
- 普通失踪: 行方不明の期間が7年間生死不明の場合に適用されます。
- 特別失踪: 戦争・災害など特別な危険に遭遇し、その危険が去った後1年間生死不明の場合に適用されます。
失踪宣告の手続きの流れ
失踪宣告の手続きは、以下の通りです。
- 手順1.家庭裁判所に失踪宣告の申立て
- 申立て:行方不明者の利害関係人(他の共有者や相続人など)が、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
- 申立書、戸籍謄本、失踪事実を証明する資料(警察への捜索願など)などが必要です。
- 手順2.家庭裁判所での審理・失踪宣告
- 家庭裁判所が調査を行い、官報などで行方不明者に異議があれば申し出るよう届出を催告します(公示催告)。
- 一定期間内に届出がなければ、失踪宣告がなされます。
- 手順3.市区町村役場への届出
- 失踪宣告後、市区町村役場に届出を行い、戸籍に記載されます。これにより、死亡したものとして扱われ、相続が開始されます。
失踪宣告は、手続き完了までに手間と時間がかかる点がデメリットです。特に普通失踪の場合は7年間の期間が必要となるため、緊急性の高い問題解決には不向きな場合があります。
3. 所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度(2023年民法改正)
所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度とは、2023年4月1日に施行された改正民法により導入された新しい制度です。他の共有者が、裁判所を通じて所在不明の共有者の持分を取得(買い取る)または共有不動産全体を第三者に売却できる制度です。
共有者が行方不明の場合、その持分を扱う方法として、主に所在等不明共有者持分取得制度と所在等不明共有者持分譲渡制度の2つがあります。
①所在等不明共有者持分取得制度とは?
所在等不明共有者持分取得制度は、他の共有者が、裁判所を通じて所在不明者の持分を買い取る制度です。
持分の取得費用は、裁判所が決定した時価相当額を国(供託所)に供託します。これにより、所在不明者が現れた際に、いつでも供託金を受け取れるようになります。
②所在等不明共有者持分譲渡制度とは?
所在等不明共有者持分譲渡制度とは、他の共有者が、裁判所を通じて所在不明者の持分も含めて共有不動産全体を第三者に売却する制度です。
ただし、この制度は、相続開始から10年以内の不動産には原則として利用できません。また、不動産全体を売却するため、共有者全員の同意(所在不明者については裁判所の決定)が必要です。
どちらの制度を利用するかは、不動産をどのように活用したいかによって異なります。
- 不動産を所有し続けたい場合:持分取得制度
- 不動産を売却して現金化したい場合:持分譲渡制度
新制度の利用が難しいケース
これらの新制度は非常に有効ですが、以下のようなケースでは利用が難しい場合があります。
- 共有者が行方不明ではない場合: 制度の対象外となります。
- 共有者の所在は不明でも、連絡手段がある場合: 電話やメールなどでの連絡が可能な場合は、行方不明とはみなされません。
- 共有者が未成年者の場合: 親権者の同意が必要となり、複雑な手続きが生じます。
新制度を利用する手続きの流れ
所在等不明共有者の持分取得・譲渡制度を利用する裁判手続きの一般的な流れは以下の通りです。
- 不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てる:
- 申立書、不動産の登記簿謄本、共有者の住民票などの必要書類を提出します。
- 裁判所による公告が行われる:
- 裁判所は、行方不明の共有者に対し、申立ての内容を官報などで公告し、意見申述の機会を与えます。
- 供託金を納付する(持分取得の場合):
- 裁判所が決定した持分の対価を供託所に納めます。
- 登記手続きを行う:
- 裁判所の決定に基づき、共有持分の移転登記(取得の場合)または共有不動産全体の売却登記(譲渡の場合)を行います。
4. 自己持分のみを売却する
共有名義不動産を全体売却する場合、共有者全員の同意が必要になりますが、自己持分のみを売却する場合、他の共有者の同意は不要です(民法第206条)。
共有者が行方不明、共有者が多すぎて意思確認や意思統一が難しい、今後の不動産活用予定がない、などの状況の場合、自分の持分のみを第三者に売却する方法が最も容易に現金化および問題解決できる手段となります。
ただし、共有持分のみの売却は一般市場では、中々買い手が見つかりにくいのが現状です。なぜなら、共有持分だけを購入しても、他の共有者の同意がなければ不動産の活用が制限されるため、購入後のリスクが高いと判断されやすいからです。 そのため、共有持分を専門に扱う不動産会社や買取業者に依頼するのが一般的です。

共有者が行方不明の問題は放置せずに早めの解決を
共有者が行方不明のまま、問題を放置することは、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。共有関係を解消し、安心して不動産を所有するためにも、早めの解決を目指しましょう。
センチュリー21中央プロパティーでは、特に4つ目にご紹介した「共有持分の売却」を専門にサポートしています。
共有者が行方不明でも、あなたの持分のみを売却することが可能です。
仲介手数料や弁護士相談費用など、売却に伴う費用は一切無料ですので、共有持分の売却をご検討の方はぜひ当社にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。