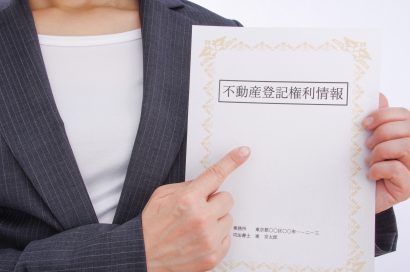相続土地国庫帰属制度とは?申請~審査の流れや負担金を解説
相続土地国庫帰属制度とは?申請~審査の流れや負担金を解説

目次
相続で土地を取得したものの、遠方のため使えずに放置するケースは少なくありません。 使用していなくても固定資産税は納めねばならず、所有者の悩みの種でもあるでしょう。
一方で、令和5年4月27日に開始した相続土地国庫帰属制度を活用すれば、相続で得た土地が処分できる可能性が出てきました。
まず、相続土地国庫制度がどのような制度なのかを確認していきましょう。

相続土地国庫帰属制度の目的と背景
相続土地国庫帰属制度は、相続、または相続人に対する遺贈によって土地を得た所有者が、土地所有権の国庫への帰属を申請できる制度です。
国庫に帰属すると、国有地になります。 つまり、相続土地国庫帰属制度は「相続(遺贈)で得た土地について、承認を得れば国が引き取り国有化する」制度です。
この制度の施行で、相続した土地が管理不全に陥って荒廃し、周辺環境に悪影響を及ぼす状況の改善を目指しています。 相続を重ねるうちに所有者不明となった土地は、管理も利活用も行えなくなります。 そのため、所有者不明土地発生の抑制が第一の目的といえるでしょう。
近年、大都市への人口集中により過疎化地域での土地利用の需要が減り、土地を手放したい人が増えました。 また、相続により本人の意志と無関係に土地を得ることで、所有者の負担感が増加することもわかってきています。 負担に感じると土地の管理にも消極的になり、管理不全におちいってしまいます。
そこで、相続によって得た土地を国に引き渡し、手放せる仕組みが制度化されたのです。
相続土地国庫帰属制度の概要
令和5年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続(遺贈)により土地の所有者となった者が希望すれば、その土地を国庫に帰属できる制度です。
施行日以降に発生する相続に加え、すでに相続している土地(過去の相続)も対象です。
所有者の申請をトリガーに、法務局で書類や現場調査などを実施し、受け入れ判断をします。 法務大臣の承認を受けた所有者は、土地管理費用の一部を負担金として納め、所有権と管理義務を国に渡すことになるのです。 国有地となった土地は、財産として国が管理や処分を行います。
相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット
この制度は、相続による土地の所有者にとってどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
相続土地国庫帰属制度のメリット
土地所有者にとってのメリットは、特に以下の3点があげられます。
- 不要な土地を手放せる
- 引き取り手を自分で探す必要がない
- 引き取り後の管理も安心できる
最大のメリットは、相続した土地が不要の場合、手放せることです。
相続では「遺産すべてを相続する」か「すべて相続しない(相続放棄)」しか選択肢がなく、一部のみ受け取ることができませんでした。 相続国庫帰属制度の創設によって、一定の条件下ではあるものの、実質的に「一部の相続」が可能になります。
農地や山林も売却しにくく処分が難しいですが、承認を得れば宅地と同様、国庫に帰属が可能です。
手放した土地の使われかたによっては、地域住民の反感を買ってしまうおそれもあります。 例えば、太陽光パネルを敷設した結果、土砂崩れなどを起こし近隣に被害が出た場合など、どうしても元の所有者を責める論調は出てしまいます。
しかし、引き取り先が国であれば、問題が生じた際も国が責任をもって対応するため、安心感があるといえるでしょう。
相続土地国庫帰属制度のデメリット
次に、デメリットとしてあげられるのは以下3点です。
- 帰属できる土地は一定の要件を満たしているものに限られる
- 国による審査を受ける必要がある
- 費用や時間、手間がかかる
国庫に帰属できる土地は、一定の要件を満たすものに限られます。 また、所定の手続きをとり国の審査を受けなくてはならず、申請にかかる費用は所有者が負担します。 承認された際には、負担金も納めなくてはなりません。
審査は書類審査だけでなく、現地調査の実施など煩雑なため、期間が長くなることが想定されます。 法務局のQAでは、当面は半年~1年かかるとされています。
さらに、土地の所有者は資料の収集をおこなったり、法務局の求めに応じて調査に協力したりせねばならないため、労力も必要です。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人
この制度を利用できるのは「相続または遺贈によって土地を取得した人」です。 売買など、相続以外の方法で取得した場合や、法人は基本的には対象外となります。
- Q.制度の開始前に土地を相続した人も申請可能か?
はい、制度開始前に相続した土地でも申請可能です。 相続土地国庫帰属制度は、過去に相続した土地も対象となるため、施行日より前に相続した土地であっても申請できます。
- Q.土地が共有の場合も申請可能か?
共有名義不動産の場合も、共有者全員で申請を行うことができます。 法人の申請は原則認められていませんが、共有者が個人の場合、共同申請することが可能です。
相続土地国庫帰属制度の申請方法と必要書類
相続土地国庫帰属制度の申請方法と必要書類を確認していきましょう。 以下の順で解説していきます。
申請の流れ
同制度の承認申請は、大きく以下の流れで処理されます。
- 法務局に相談・申請
- 法務局にて書類・実地審査
- 負担金の納付
- 国庫に帰属
承認申請書などの書類一式を準備し、土地の管轄の各都道府県の法務局、または地方法務局(本局)の不動産登記部門の窓口に提出しましょう。 同時に審査手数料も納付します。
必要書類の記入は所有者や共有者がおこないますが、申請自体は、所有者本人でなくてもかまいません。 また、窓口は混み合う場合があるため、事前連絡が推奨されています。 承認申請は郵送でも行えます。
承認申請の提出先法務局は、以下で調べることができます。 参考:管轄のご案内
審査の結果、申請が承認されると、その旨が通知されます。 同時に、負担金の納付のお知らせも届きます。 通知がきてから30日以内に、負担金を納めましょう。
納付することで、土地の所有権が国に移転し、国庫への帰属が完了します。
申請・事前相談に必要な書類
同制度の申請には、所定のフォーマットの申請書および、下図の添付書類が必要です。
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書
申請書には、単独申請(所有者向け)と、共同申請(共有者向け)の2種類があります。 申請書のフォーマットはこちらから取得してください。
実際の書類の作成方法の際は、以下のサイトの具体例を参考にしてください。 参考:貼付書面の記載例
法務局での事前相談に必要な書類
事前相談時には、以下の書類を準備しましょう。
- 記入済みの相続土地国庫帰属制度相談票
- 相談したい土地の状況について(チェックシート)
- 土地の状況がわかる資料(登記事項証明書、地図の写しなど)
相続土地国庫帰属制度の相談について、くわしくは以下をご確認ください。 参考:令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始しました
申請にかかる費用
申請には、「審査手数料」の支払いが必要です。
審査手数料は土地一筆につき14,000円です。 申請時に相当額の収入印紙を貼って納付します。 申請後に取り下げや、申請時の却下や不承諾となった場合でも手数料は返還されませんので注意が必要です。
また、審査が通り申請が承認されると、負担金の支払いが生じます。
申請に関する相談窓口
相続土地国庫帰属制度に関する相談は、全国の法務局や地方法務局で受け付けています。
「土地が制度の対象になるか」「申請に必要な書類がそろっているか」など、承認申請を提出する前に確認できるので、少しでも不明な点があれば相談してみましょう。
承認申請は手放したい土地の管轄の法務局で行う必要がありますが、遠方にお住まいの場合などは、お近くの法務局でも相談が可能です。
相談は対面もしくは電話でおこないます。
相続土地国庫帰属制度の審査の流れ
それでは、相続土地国庫帰属制度の法務局でおこなわれる審査について、流れや審査基準を確認しましょう。 以下について、順番に解説します。
審査の流れ
承認申請後の審査の流れは、以下の通りです。
- 承認申請
- 要件審査・承認
- 負担金の納付
- 国庫帰属
審査の基準
相続土地国庫帰属制度では、国が引き取ることができない土地の要件が定義されています。
一つは「却下要件」で、該当する土地は承認申請を受け付けてもらえません。 二つめは「不承諾要件」で、承認申請を行うことはできますが、調査の結果該当すると判断されると不承諾となります。
引き取ることができない土地(却下要件)
以下の要件に該当する土地は、原則として却下されます。
- 建物がある土地
- 担保権などが設定されている土地
- 通路として使用されている土地や、墓地、社寺境内地など、国の管理が適切ではない土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 所有権の争いがある土地
引き取ることができない土地(不承諾要件)
以下の要件に該当する土地は、申請はできますが、原則として承認されません。
- 崖がある土地
- 樹木や車両、工作物がある土地
- 地下に除去が必要な有体物がある土地
- 隣人とトラブルを抱えている土地
- 管理や処分に多大な労力がかかる土地
- 通常の管理または処分を阻害する有体物が地上にある土地(例:大量の廃棄物が放置されている土地)
- 通常の管理または処分に過大な費用を要する土地(例:地盤沈下や土砂崩れの危険がある土地)
審査結果の通知方法
承認申請の審査結果は、郵便で届きます。 申請が承認された場合、以下の書類が同封されています。
- 承認した旨と負担金の額を記載した通知書
- 負担金を納付するための納入告知書
通知に従い、30日以内に負担金を納めましょう。
相続土地国庫帰属制度の負担金(管理費)とは
相続土地国庫帰属制度では、所有者に負担金を納める必要が生じます。 負担金の概要と納め方、金額について解説します。
負担金とは
この制度では、国に帰属させる土地の管理費用の一部について所有者に負担を求めており、これが負担金です。 負担金の額は、土地の種目(宅地、田・畑、森林など)によって異なります。
法務局で種目ごとに10年分の標準的な管理費に該当する額を算定し、申請が承認され、通知を受けた所有者は負担金を納付します。
負担金の納め方
負担金は以下のいずれかの方法で納めます。
- 銀行の窓口
- インターネットバンキングやATM
負担金は、承認通知が届いた日から30日以内に納付しなくてはなりません。 30日を過ぎると、承認の決定が失効してしまいます。 土地を国庫に帰属させるためには、承認申請からやりなおすことになるので注意が必要です。
負担金はいくらかかる?
負担金は、宅地、田・畑、森林、その他(雑種地、原野など)の4種目ごとに金額が設定されています。 宅地は基本的には20万円ですが、市街化区域などに指定されている一部の地域については、算定式で算出します。
また、複数の土地をまとめて申請する場合、審査手数料は土地の筆数に応じてかかりますが、負担金は土地ごとの金額を合算します。
負担金の算出方法
具体的な負担金の算出方法は、法務省のウェブサイトで公表されている基準に基づいて行われます。 負担金は、土地の種目(宅地、田、畑、森林、その他)によって基準が異なります。
- 宅地:原則として20万円。ただし、市街化区域内の宅地など、一部の宅地については面積に応じた算定式が適用されます。
- 田、畑、森林、その他:それぞれの種目に応じて、面積に応じた算定式が適用されます。
以下に、算定式(1)~(3)の具体的な内容を記載します。
算定式(1) 市街化区域内の宅地などのうち、負担金が高額になる可能性のある土地に適用されます。
| 面積区分 | 負担金額 |
| 50㎡以下 | 国庫帰属地の面積に4,070(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 |
| 50㎡超100㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,720(円/㎡)を乗じ、276,000円を加えた額 |
| 100㎡超200㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,450(円/㎡)を乗じ、303,000円を加えた額 |
| 200㎡超400㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,250(円/㎡)を乗じ、343,000円を加えた額 |
| 400㎡超800㎡以下 | 国庫帰属地の面積に2,110(円/㎡)を乗じ、399,000円を加えた額 |
| 800㎡超 | 国庫帰属地の面積に2,010(円/㎡)を乗じ、479,000円を加えた額 |
算定式(2) 通常の宅地や農地(田・畑)の一部に適用されます。
| 面積区分 | 負担金額 |
| 250㎡以下 | 国庫帰属地の面積に1,210(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 |
| 250㎡超500㎡以下 | 国庫帰属地の面積に850(円/㎡)を乗じ、298,000円を加えた額 |
| 500㎡超1,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に810(円/㎡)を乗じ、318,000円を加えた額 |
| 1,000㎡超2,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に740(円/㎡)を乗じ、388,000円を加えた額 |
| 2,000㎡超4,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に650(円/㎡)を乗じ、568,000円を加えた額 |
| 4,000㎡超 | 国庫帰属地の面積に640(円/㎡)を乗じ、608,000円を加えた額 |
算定式(3) 森林や原野など、管理費用が比較的低い土地に適用されます。
| 面積区分 | 負担金額 |
| 750㎡以下 | 国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を乗じ、210,000円を加えた額 |
| 750㎡超1,500㎡以下 | 国庫帰属地の面積に24(円/㎡)を乗じ、237,000円を加えた額 |
| 1,500㎡超3,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に17(円/㎡)を乗じ、248,000円を加えた額 |
| 3,000㎡超6,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に12(円/㎡)を乗じ、263,000円を加えた額 |
| 6,000㎡超12,000㎡以下 | 国庫帰属地の面積に8(円/㎡)を乗じ、287,000円を加えた額 |
| 12,000㎡超 | 国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗じ、311,000円を加えた額 |
相続土地国庫帰属制度以外で相続した土地を処分する方法
相続土地国庫帰属制度以外で相続した土地を処分する方法は、以下の通りです。
相続自体を放棄する
土地の所有権は、基本的には一度得てしまうと不要であっても放棄できません。 相続の際に相続放棄すれば土地の所有権を得ずにすみますが、その場合、ほかの財産もすべて放棄することになります。
また、たとえ相続放棄しても、次の相続人が管理できる状態になるまでは土地の管理義務は残ります。 相続財産管理人を立て管理義務を免れるには、家庭裁判所に申し立てと数十万円の費用負担が必要です。
無償で譲渡する(寄付など)
個人、法人、自治体に無償で譲渡(寄付)するのも一案です。
個人への無償譲渡は寄付になりますが、受け取る側に税負担が生じます。 公益法人(学校や社団法人など)への寄付は、場所によっては受け入れられる場合もありますが、所有権移転登記の費用として10万円程度の負担が発生します。 また、寄付した側に所得税、寄付を受けた側に贈与税が課せられるケースもあり、注意が必要です。
最後に自治体への寄付ですが、自治体は使う当てのない土地を受け入れることはほぼありません。 自治体にとって固定資産税は税収となるためです。 不要な土地の受け取りで税収を減らすことは考えにくいため、過度な期待は避けておきましょう。
第三者へ売却する
売却も再検討してみましょう。 売地に古い建物が残っている場合、解体したほうが売却しやすくなります。 自治体に空き家バンクが設置されている場合は、登録してみるのもよいでしょう。
ただし価格を下げると仲介手数料が減るため不動産会社が営業活動に消極的になる可能性があります。 別途手数料を払う交渉をしてみるのもよいでしょう。
相続土地国庫帰属制度と他の処分方法の比較
相続した不要な土地を処分する方法はいくつかありますが、それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。 相続土地国庫帰属制度を含め、主な処分方法を比較してみましょう。
| 処分方法 | メリット | デメリット |
| 相続土地国庫帰属制度 | ・不要な土地だけを手放せる ・引き取り手を探す手間がない ・引き渡し後の管理も安心 | ・利用できる土地が限定される(要件が厳しい) ・審査に時間と手間がかかる ・審査手数料と負担金が発生する |
| 相続放棄 | ・相続財産すべてを放棄できるため、負の遺産を引き継がなくて済む | ・プラスの財産もすべて放棄することになる ・次の相続人が管理できる状態になるまで管理責任が残る ・相続放棄の期限がある(原則、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内) |
| 遺産分割協議 | ・特定の相続人に土地を引き継いでもらえる | ・相続人全員の同意が必要 ・土地を引き取る相続人の負担が増える可能性がある |
| 売却 | ・金銭を得られる可能性がある ・土地の管理から解放される | ・買い手を見つけるのが難しい場合がある ・売却費用(仲介手数料、測量費、解体費など)がかかる ・売却できないリスクがある |
| 贈与・寄付 | ・税制上の優遇措置を受けられる場合がある(寄付の場合) ・土地の管理から解放される | ・贈与税や不動産取得税など、受贈者に税負担が発生する可能性がある ・寄付の場合は、受け入れ先が見つからないことが多い ・寄付の場合でも、所有権移転登記費用などが発生することがある ・法務局は無償で土地を引き取らないため、贈与や寄付ではない点に注意 |
相続土地国庫帰属制度の利用を検討すべきケース
- 相続した土地が、特定の要件を満たす見込みがある場合。
- 他の相続人が土地の引き取りを希望しない場合。
- 売却が困難な土地や、管理負担が大きい土地を手放したい場合。
- 他の財産を相続しつつ、不要な土地だけを手放したい場合。
他の方法を検討すべきケース
- 相続財産全体を放棄したい場合:相続放棄
- 土地を有効活用してくれる親族や知人がいる場合:遺産分割協議や贈与
- 土地の買い手が見つかりそうな場合:売却

まとめ:土地の相続準備は早めに行うのがポイント
この記事では、相続土地国庫帰属制度について、制度概要や目的・背景、申請手順や審査の流れについてご説明しました。
相続した土地について、国庫への帰属を検討される方は、まずは法務局で相談してみるとよいでしょう。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分専門の不動産仲介会社です。
共有名義不動産に詳しい弁護士が常駐しているため、共有者とトラブルを抱えている場合や売却後のトラブルが不安な方にも、ご安心いただける体制が整備されております。
弁護士相談費用や仲介手数料など、売却にかかる諸費用は0円です。
- 共有者と不仲で関係を解消したい
- 不動産の活用ができていない
- 共有者が多すぎる
- 固定資産税を負担したくない
共有名義不動産でお悩みの方は、一度当社へご相談ください。

この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。