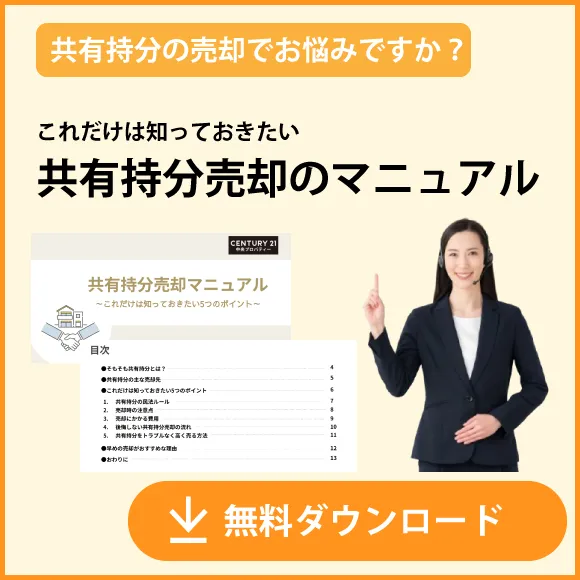【2023年4月民法改正】共有物の管理ルールの変更ポイント
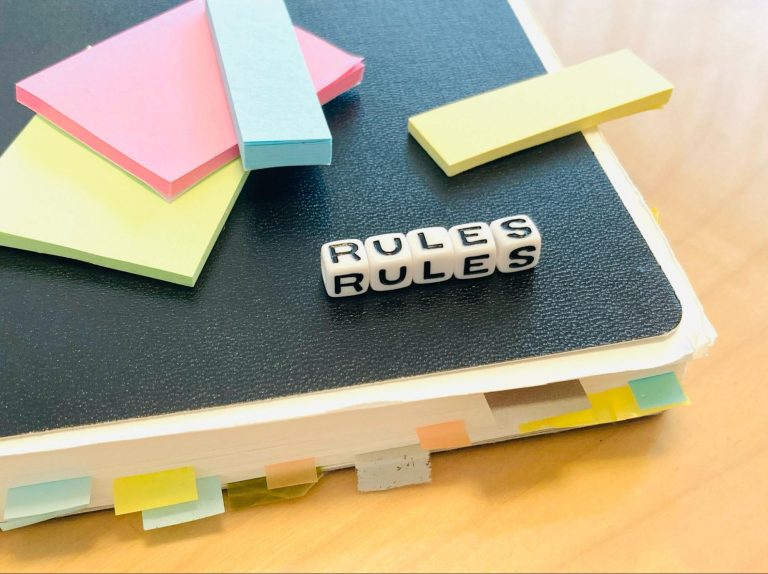
目次
不動産を複数人で共有している場合、その管理には民法で定められたルールが適用されます。特に2023年4月1日からは、民法改正によって共有物の管理ルールが大きく見直され、より柔軟な対応が可能になりました。
これまでのルールでは、共有者全員の同意が必要となる場面が多く、所有者不明の土地問題や、共有者間の意見の相違から不動産の有効活用が進まないケースが多発していました。今回の改正は、こうした課題を解決し、不動産の円滑な利用や流通を促進することを目的としています。
この記事では、改正民法における共有物の管理ルールが具体的にどう変わったのか、その変更点やメリット、そして実際に起こりうるトラブルへの対応策について、わかりやすく解説します。共有名義の不動産をお持ちの方や、今後不動産を相続する予定のある方は、ぜひご一読ください。
共有持分の専門仲介
センチュリー21中央プロパティー
あなたの持分だけを高額売却!
\ 売却・トラブルの相談はこちら /
共有物とは?
共有物とは、一つのものを複数人で共同して所有している状態の「もの」そのものや、その所有形態を指します。民法では、共有者それぞれがそのものの持分(もちぶん)を持っていると定義されています。
ここでは、不動産における共有物を具体例を挙げて解説します。不動産が共有物となる典型的なケースは以下の通りです。
- 相続によって取得した不動産
親が亡くなり、その所有していた自宅や土地を複数の子供たちが相続した場合、遺産分割協議がまとまらなければ、その不動産は相続人全員の共有状態となります。
例えば、父親が亡くなり、長男と次男が相続人である場合、遺言がなければ自宅は長男と次男の共有財産となり、それぞれが2分の1ずつの持分を持つことになります。 - 夫婦で共同購入した不動産
夫婦がペアローンを組んでマイホームを購入した場合など、夫婦二人の名義で不動産の登記を行うと、その不動産は夫婦の共有物となります。
例えば、夫が持分「4分の3」、妻が持分「4分の1」といった形で、出資比率に応じて持分を設定するのが一般的です。
【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫
共有物管理における「3つの行為」と民法改正の背景
共有物の管理とは、共有者同士で共有している物(不動産・動産)を維持・利用・改良・処分することです。これらの行為は、その性質に応じて「保存行為」「管理行為」「変更行為」の3つに分類され、それぞれ異なる同意の要件が民法で定められています。
共有物管理の具体的な行為と同意の要件(旧民法と改正民法の比較)
| 行為の種類 | 内容と具体例 | 同意の要件(旧民法) | 同意の要件(改正民法) |
| 保存行為 | 共有物の現状を維持し、価値の減少を防ぐための緊急性が高い行為。 例: 雨漏りの修繕、建物の破損箇所の修理、不法占拠者に対する明渡し請求、固定資産税の支払い。 | 各共有者が単独で可能 | 各共有者が単独で可能 |
| 管理行為 | 共有物の利用や改良を目的とした行為で、その性質を根本的に変えない範囲の行為。収益を図る行為も含む。 例: 賃貸借契約の締結(旧法で短期、改正民法で短期(土地5年、建物3年、山林10年、動産6ヶ月を超えない期間))、利用方法の変更、共有物の管理者の選任・解任。 | 持分価格の過半数 | 持分価格の過半数 |
| 変更行為 | 共有物の物理的な形状や性質を根本的に変える行為。処分行為も含む。 例: 【軽微ではない変更】 建物の大規模な増改築、用途変更、共有物全体の売却、抵当権の設定、建物の取り壊し。 【軽微な変更(改正民法で追加)】 建物の軽微なリフォーム(間取り変更なしの壁紙張り替えなど)、駐車場の舗装、庭木の伐採(大規模な景観変更なし)。 | 共有者全員の同意 | 原則として共有者全員の同意。 ただし、軽微な変更は持分価格の過半数で決定可能(民法第251条1項)。 |
民法改正の背景と目的
旧民法では、不動産の売却や大規模な増改築といった「変更行為」を行うには、共有者全員の同意が必要でした。この「全員同意」の原則が、以下のような問題を引き起こしていました。
- 所在不明共有者の存在:
相続登記が義務ではなかったため、相続が発生しても登記されず、所有者が分からない「所有者不明土地」が多数発生していました。こうした土地では、共有者の一部が所在不明であるため、全員の同意を得ることが不可能となり、不動産の売却や活用が進められない状況でした。 - 意見対立:
共有者全員が判明していても、一人でも同意しない共有者がいる場合、重要な変更行為が行えず、不動産が放置されるケースが多く見られました。 - 空き家問題の深刻化:
上記のような問題が、管理不十分な空き家を増加させ、周辺環境への悪影響や地域の活性化阻害要因となっていました。
このような背景から、所有者不明土地問題の解消や不動産の円滑な活用を促進するため、民法の共有に関する規定が改正されるに至りました。
【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫
民法改正で共有不動産の管理はどう変わる?具体的な変更点とメリット
今回の民法改正(2023年4月1日施行)により、共有不動産の管理は大きく変わりました。主な変更点と、それによって得られるメリットを解説します。
共有物の管理ルールの変更ポイント
- 軽微な変更は過半数で決定可能に:
- 改正民法第251条1項により、共有物の「形状または効用の著しい変更を伴わないもの」、すなわち「軽微な変更」については、共有者全員の同意ではなく、持分価格の過半数で決定できるようになりました。
- これにより、これまで全員同意が必要で進まなかった小規模な改良や修繕が、より迅速に行えるようになります。
- 不明共有者がいても裁判所手続きで対応可能に:
- 改正民法第252条の2により、共有者の一部が不明(所在不明、または生死不明)な場合でも、裁判所の決定(公示による意思表示制度の活用など)があれば、その共有者以外の者で変更行為や管理行為が可能になりました。
- これは、共有者の連絡が取れない場合でも、裁判所の手続きを経ることで、不動産の売却や大規模修繕といった変更行為(軽微な変更を除く)も進められるようになったことを意味します。
- 短期賃貸借の同意要件の明確化:
- 改正民法第252条4項により、一定期間を超えない賃借権の設定(短期賃貸借)は、持分価格の過半数で決定できる「管理行為」であることが明確になりました。
- これにより、共有不動産を賃貸に出しやすくなり、活用が進むことが期待されます。
変更によるメリット
- 不動産の活用・売却が円滑に:
共有者全員の同意が不要になるケースが増えたため、これまで滞っていた不動産の売却やリフォーム、賃貸などの活用がよりスムーズに進められるようになります。 - 所有者不明土地問題の解消:
不明な共有者がいる場合でも法的な手続きを通じて対応できるようになったため、長期間放置されてきた所有者不明土地の解消に繋がります。これにより、土地の有効活用が進み、地域の開発やインフラ整備が促進されます。 - 空き家問題の緩和:
管理不十分な空き家は、隣地への悪影響や景観の悪化を招きます。改正によって管理や処分が容易になることで、空き家問題の緩和に貢献します。 - 共有者間のトラブル軽減:
一部の共有者の意見によって不動産の管理が進まない状況が緩和されることで、共有者間のトラブルを未然に防ぎ、解決しやすくなります。 - 将来的な相続対策:
今後、相続によって共有不動産を取得する予定の人にとっても、管理や処分がしやすくなるため、相続後の負担軽減が期待できます。
この度の民法改正は、複数人で所有する土地・建物を相続したものの、対応が取れていなかった人にとって、問題解決の糸口になる大きな一歩と言えるでしょう。
【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫
2023年民法改正により解決できる事案
共有不動産の管理においては、共有者間の意見の相違や連絡不通など、様々なトラブルが発生しがちです。ここでは、よくあるトラブル事例と、改正民法がそれらにどう対応するかを解説します。
①共有物の管理方針が共有者間で割れているケース
共有している不動産の管理方針が共有者間で意見が割れている場合に、トラブルになるケースがよくみられます。
旧民法での課題:
旧民法では、共有物の「変更行為」に関しては共有者全員の同意が必要でした。そのため、共有者間で意見が割れている場合は、リフォームや利用方法の変更といった行為もできず、共有物の円滑な利用や管理の阻害につながっていました。
改正民法での対応:
改正民法第251条1項では、形状や効用の著しい変更を伴わない「軽微な変更」については、全員の同意ではなく持分価格の過半数で決定できるように要件が緩和されました。これにより、例えば外壁の塗り替えや間取り変更を伴わない内装リフォームなど、比較的小規模な改修であれば、意見が分かれていても過半数の賛成で進めることが可能になりました。
また、民法第252条4項では、短期間の賃借権の設定(土地5年、建物3年、山林10年、動産6ヶ月を超えない期間)であれば、持分価格の過半数で決定できると定められました。これにより、共有不動産を賃貸に出す際のハードルが下がり、収益化がしやすくなっています。
②共有者の賛否が不明なケース
共有者自身が共有不動産から遠く離れて暮らしている場合や、所有権があることを忘れている場合には、連絡をとっても明確な返答が得られない可能性があります。
旧民法での課題:
旧民法の場合、このような共有者の賛否が不明なケースでは、不動産の「変更行為」(売却など)が行えず、不動産が宙に浮いた状態となり問題となっていました。
改正民法での対応:
改正民法第252条2項2号により、賛否が分からない共有者がいる場合でも、裁判所の決定(催告を経て一定期間内に意思表示がない場合に承認したものとみなす決定)があれば、その共有者以外の共有者の過半数によって管理に関する事項を決定可能になりました。
ただし、この制度は、賛否を明らかにしない共有者が持分を失う行為(例えば、抵当権の設定や売却などの処分行為)に対しては利用できません。抵当権が設定され、万が一ローンの支払いが滞ると不動産は差し押さえられ競売にかけられるため、所有者は持分を失うリスクがあるためです。
賛否を明らかにしない共有者の持分がほかの共有者よりも多い場合や、複数の共有者が賛否を明らかにしない場合も、この規定は利用できないため注意が必要です。
また、裁判所に申し立ててから許可が降りるまで通常2週間程度かかります。裁判所は、共有者に対して決定しようとしている管理事項を伝え、期間内に賛否を明確にするように催告します。
③共有者が行方不明のケース
共有者の一部が長期間連絡が取れず、生死も不明な「行方不明者」である場合も、共有不動産の管理に大きな支障をきたしていました。
旧民法での課題:
改正前の民法では、行方不明の共有者がいる場合は、裁判所で「不在者財産管理制度」という手続きを行う必要がありました。この制度は、行方不明者ごとに予納金(数十万円~)を納める必要があり、行方不明者が複数人いる場合は費用が高額になったり、手続きも複雑になったりするため、実際に利用する人が少ないという問題がありました。
また、相続登記の義務がなかったため、相続時に行方不明者がいる場合は、売却などせずにそのまま放置される問題も起こっていました。
改正民法での対応:
改正民法第251条2項により、共有者のなかに行方不明の人がいる場合は、裁判所の決定を得て、行方不明者以外の共有者全員の同意を得て共有物に変更を加えられるようになりました。これは、売却や抵当権設定といった「軽微ではない変更行為(処分行為)」についても、裁判所の関与のもとで進められるようになったことを意味します。
さらに、民法第252条2項1号により、所在が分からない共有者以外の共有者の持分の過半数によって、管理に関する事項を決定することも可能です。
このように、民法改正によって共有者のなかに所在不明者がいる場合でも、裁判所で手続きするだけで共有物の変更や管理ができるようになり、不動産の有効活用が進むことが期待されます。
【共有者とトラブル中でもOK】共有持分の売却相談はこちら ≫
まとめ
この記事では、2023年4月1日に施行された民法改正によって変わった共有物の管理に関して詳しく解説しました。
旧民法では、不動産の売却などの変更行為に関しては、共有者全員の同意が必要でしたが、改正民法では軽微な変更に関しては、持分価格の過半数の同意でも問題ないと制度が緩和されています。
また、一部の共有者の所在が不明の場合に、全員の同意が取れないため、長期的に放置され円滑な土地活用や管理ができていなかった問題に関しても、裁判所を通すことで、所在不明の共有者以外で共有物の管理や変更が可能になりました。
所有者不明の不動産を相続して管理や対応に困っていた人も、この度の民法改正によって、円滑な土地活用が進められるのではないでしょうか。
本記事が、共有不動産を所有している人の悩みを解決できたら幸いです。
共有持分のお悩み別に解決!
専門家監修の『お役立ち資料』を
プレゼント
4万件以上の共有持分トラブル・売却をサポートしてきた『センチュリー21中央プロパティー』が、お客様の状況に合わせて選べる3つの専門資料をご用意しました。
情報収集だけでも大歓迎です。
ぜひ、あなたの問題解決にお役立てください。
資料①:共有持分売却の業者選びガイドブック
ご自身に合った”共有持分の専門家”を見極めるコツを徹底解説。
数ある業者の中から、本当に信頼できる一社を見つけるための必読ガイドです。
資料②:これだけは知っておきたい!共有持分売却マニュアル
共有持分の売却は、通常の不動産売却とは異なる点が多々あります。
あなたの大切な資産である共有持分を、後悔なく売却するために必要なポイントをまとめました。
資料③:不動産の相続登記完全解説マニュアル
2024年4月から義務化された相続登記。
必要な書類から費用、手続きの流れまで、「世界一わかりやすい」をコンセプトに完全解説します。
資料のダウンロード後も、無理な勧誘はございませんのでご安心ください
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。