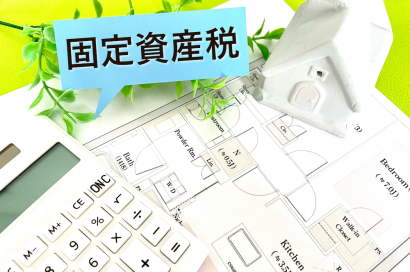共有名義不動産の家賃請求は可能?他の共有者が独り占めしている場合の対処法

目次
共有名義不動産で起こり得るトラブルの一つが、家賃の請求です。
「他の共有者に家賃を請求できるのか」「他の共有者が占有している場合はどうすればいいのか」といった疑問を抱える人もいるでしょう。
この記事では、共有名義不動産における家賃請求の可否や対処法について、専門的な観点から解説していきます。
他の共有者に家賃請求できるケース
共有名義の不動産を、共有者間の合意なく特定の共有者のみが使用収益している以下のような場合、侵害された共有者は原則として家賃請求が可能です。
- 他の共有者が不動産を独占している場合
- 他の共有者が共有名義不動産の家賃収入を独占している場合
他の共有者が共有名義不動産を独占している場合
共有名義不動産において、特定の共有者だけが自身の持分割合を超えて使用している場合、他の共有者は家賃を請求できます。
この場合、共有者間で賃貸借契約を結んでいなくても請求が可能です(民法第703条)。
例えば、AさんとBさんがそれぞれ50%の持分を持つ共有不動産があるとして、Aさんがその不動産全体を占有・使用している場合、Bさんは自身の持分割合に応じた賃料相当額をAさんに請求することができます。
他の共有者が共有名義不動産の家賃収入を独占している場合
第三者に共有名義不動産を貸し出している場合、共有者間で持分割合に応じて家賃の分配を行う必要があります。
もし家賃の分配が行われておらず、他の共有者に家賃収入を独占されているときは、家賃請求が可能です。
この場合、共有者に独占されている賃料収入を取り返すことができます。
家賃請求は家賃を独占している共有者に対して行います。
重要なのは、共有者全員が賃借人と賃貸借契約を結んでいなくても請求できるという点です。
ただし、家賃を独占している共有者に対して「賃料請求」は可能ですが、「明渡請求」はできません。
共有者に家賃請求できないケース
共有名義不動産において、以下のような状況下では家賃請求ができない場合があります。
- 共有名義不動産の占有に関して、共有者間で合意している場合
- 被相続人と同居していた相続人が住み続けている場合
- 死亡した共有者の内縁のパートナーが住み続けている場合
共有名義不動産の占有に関して共有者間で合意している場合
共有者間での「使用貸借契約」に基づいて共有不動産を使用している場合、家賃請求はできません。
使用貸借契約とは、当事者の一方がある物を無償で使用・収益させ、契約終了後にその物を返還することを約する契約です(民法第593条)。
例えば、兄弟で相続した実家を、一方が無償で使用することを両者で合意している状況が該当します。
使用貸借契約は、無償で不動産を使用することを合意した契約であるため、そもそも家賃が生じません。
したがって使用貸借契約を合意している場合、家賃請求はできないということになります。
被相続人と同居していた相続人が住み続けている場合
被相続人(亡くなった親など)と同居していた相続人は、遺産分割が確定するまで共有状態のまま住み続けることが可能です。
この場合、相続財産の管理義務があるため、単独で住んでいてもただちに家賃を請求できるとは限りません。
ただし、家賃請求が難しくても、遺産分割協議で「住み続ける代わりに相応の負担をする」などの取り決めを行うことで、経済的な不公平を解消する方法があります。
死亡した共有者の内縁のパートナーが住み続けている場合
内縁関係のパートナーには相続権がありませんが、居住権を主張するケースもあります。
内縁のパートナーが故人から生前に使用を許可されている、故人との同居期間が長い、家計への貢献度が高いといった理由で、一定期間の占有を認められる可能性があります。
裁判所の判断によっては立ち退きを求めることができますが、建物明渡請求には法的手続きが必要です。
したがって、このようなケースでは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
共有者への賃料請求方法「不当利得返還請求」
共有者が家賃を支払わないトラブルへの対処方法として、「不当利益返還請求」が存在します。
不当利得返還請求とは?
不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由なく他人の財産や労務によって利益を得て、そのために他人に損失を与えた者に対して、その利益の返還を求める請求です(民法第703条)。
不当利得返還請求は、他の共有者が不公平に負担を強いられる状態を解消するために行います。
不当利得返還請求を行うには、まず相手方に内容証明郵便で支払いを求める通知を送ります。
通知に応じなかったり、話し合いで解決しなかったりした場合は、地方裁判所や簡易裁判所に民事訴訟を提起できます。
裁判所は、当事者の主張や証拠を検討しながら、不当利得の有無や返還額を公平な目で判断し、最終的な結論を出します。
不当利得返還請求の手順
不当利得返還請求を行う手順は以下の通りです。
- まずは話し合いによる解決を試みる
- 内容証明郵便での正式通知
- 調停手続きの申し立て
- 訴訟提起による法的な解決
①まずは話し合いによる解決を試みる
まずは、相手方である共有者と直接話し合い、支払いを求めることが第一歩です。 感情的にならず、冷静に状況を説明し、解決策を探るようにしましょう。
②内容証明郵便での正式通知
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便で支払いを求める通知を送ります。 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に差し出したかを郵便局が証明してくれるため、後々の証拠として有効です。
③調停手続きの申し立て
内容証明郵便を送っても相手が応じない、または話し合いでの解決が見込めない場合は、簡易裁判所または地方裁判所に民事調停を申し立てることができます。 調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら解決を目指します。
④訴訟提起による法的な解決
調停でも解決しない場合は、最終的に地方裁判所や簡易裁判所に民事訴訟を提起します。 裁判所は、当事者の主張や提出された証拠を検討し、不当利得の有無や返還額を公平な目で判断し、最終的な結論を出します。
共有者への家賃請求額の目安
他の共有者に家賃を請求する場合、その金額はどのように決まるのでしょうか。
家賃相場と持分割合に基づいた算出方法
共有者へ請求できる家賃は、「家賃相場」に「自己の持分割合」を掛け合わせることで算出できます。
例えば、家賃相場が20万円で自身の持分割合が50%の場合、請求できる家賃は20万円 × 0.5 = 10万円となります。
合意に基づく請求額の設定
共有者間で話し合い、合意した金額を家賃として請求することも可能です。
この場合、家賃相場に縛られず、双方納得のいく金額を設定できます。 ただし、合意に至らない場合は、上記のように家賃相場と持分割合に基づいて算出するのが一般的です。
家賃請求を巡るトラブルを避けるために共有状態を解消する方法5選
不当利益返還請求の他、共有者が家賃を支払わないことへの対処法として、以下の5つを解説していきます。
- 共有者全員の合意に基づき不動産全体を売却する
- 他の共有者の持分を全て買い取って自分の単独所有にする
- 他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう
- 自己の持分を第三者(買取業者・仲介業者)に売却する
- 共有物分割請求訴訟を起こす
対処法①:共有者全員の合意に基づき不動産全体を売却する
最も円満かつ公平な解決方法が、共有者全員で合意して不動産全体を売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。
不動産を現金化することで、公平に資産を分割できます。
この方法は、家賃を払わない共有者を含めて共有者全員の同意がなければ進められないため、難易度は高くなることが一般的です。
しかし、持分を単独で売却するよりも高額で売却できるため、実現すればメリットは大きい方法です。
対処法②:他の共有者の持分を全て買い取って自分の単独所有にする
他の共有者が持つ持分を全て買い取り、自分一人の単独名義にする方法も存在します。
これにより、以降は誰にも干渉されずに不動産を自由に活用できますが、他の共有者の持分を買い取るためのまとまった資金が必要になります。
また、家賃を払わずに共有名義の不動産を利用している共有者との交渉も必要になるため、こちらも難易度は高めです。
対処法③:他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう
対処法②とは逆に、他の共有者にあなたの持分を買い取ってもらう方法です。
これにより、家賃請求などの面倒ごとのきっかけとなる不動産の共有関係から抜け出し、まとまった現金を得ることができます。
ただし、他の共有者に持分を買い取る意思と資金力があることが前提となるため、その点の確認は必須となります。
対処法④:自己の持分を第三者(買取業者・専門仲介業者)に売却する
共有者同士ではなく、業者を利用して第三者に持分を売却する方法です。
この場合は、次の2つの業者のうち自分に合った方を選ぶことになります。
| 買取業者 | 専門仲介業者 | |
| ビジネスモデル | 共有持分を売主から直接買取し、最終的に不動産全体を取得したうえでの高額転売を目指す。 | 共有持分の売主と買主を仲介し、売買契約成立時の仲介手数料で利益を得る。 |
| 売主との関係性 | 売主と買取業者の直接取引のため、価格交渉がしにくい。 | 売主と買主の間に仲介業者が入るため、価格交渉がしやすい。 |
| 目的 | できるだけ安く仕入れること(売主とは利益が相反する)。 | できるだけ高く売ること(売主と利益が一致)。 |
| メリット | ・現金化までのスピードが早い。 | ・買取業者より高額かつ好条件で売却できるケースが多い。 ・他の共有者とトラブルになりにくい。 |
| デメリット | ・売却金額が市場価格よりも安い傾向にある。 | ・契約までに2~4週間ほどの期間が必要になることが多い。 |
上記の比較から、スピーディーに持分を現金化したい方は買取業者を、スピード感よりも売却価格やトラブル回避を重視したい方は仲介業者を選ぶとよいでしょう。
対処法⑤:共有物分割請求訴訟を起こす
共有者同士での話がまとまらない場合の最終手段として、法的手段である「共有物分割請求」により共有名義不動産を分割するという方法もあります。
共有物分割請求には「協議」「調停」「訴訟」の3段階があり、まずは協議を行って話し合いによる解決を目指します。
話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所や地方裁判所に調停を申し立て、さらに調停でも解決しない場合は最終的に裁判所の判断で分割方法が決定されます。
共有物分割の方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」があります。
現物分割は土地や建物を物理的に分割し、それぞれ単独所有とする方法ですが、不動産をきれいに区切るのは難しく、実際には実現困難なケースが一般的です。
換価分割は不動産を売却し、売却代金を共有者で分ける方法です。分割しやすい現金に変えてから分けるので不公平感は出にくいですが、どれくらいの金額を受け取れるかは市場価格に左右されます。
代償分割は一方の共有者が不動産を取得し、他の共有者に対価を支払う方法です。不動産を取得する側は支払う対価のために資金を用意する必要があります。
他の共有者が家賃を払ってくれない!共有名義不動産のお悩みなら中央プロパティーにご相談ください
共有名義不動産における家賃請求は、状況によって可能かどうかが異なります。
他の共有者が共有名義不動産を独占して使用している、あるいは家賃収入を独り占めしているときは、家賃を請求できます。
一方、共有者同士で使用について合意があるときや、相続に関する特別な事情がある場合は、請求が認められないこともあります。
トラブルが生じた際には、不当利得返還請求や共有物分割請求、共有持分の売却など、さまざまな対処法があります。
共有名義不動産の管理や利用に関する問題は複雑なため、法的知識が必要不可欠です。
したがって、専門家へのご相談をおすすめします。法律に詳しい弁護士や、不動産に関する権利問題に精通している不動産会社などの専門家のアドバイスを得られれば、より適切な解決策を見つけられるでしょう。
センチュリー21中央プロパティーでは、共有持分に精通したスタッフと弁護士がお客様のお悩みを解決する方法を提案いたします。
弁護士相談料や売却時の仲介手数料等は無料ですので、共有名義不動産でお悩みの方はぜひご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
家賃請求トラブルに関するQ&A
共有名義不動産の家賃請求に関するよくある疑問とその回答をまとめました。
過去にさかのぼって家賃を請求できますか?
家賃請求権には消滅時効があり、原則として5年間とされています(民法第166条1項1号)。
これは、賃料請求権が「債権」にあたるためです。 したがって、過去の未払い家賃は最大で5年分までさかのぼって請求することが可能です。
家賃トラブルがあると共有持分を売却するのは難しいですか?
家賃トラブルがあっても、共有持分の売却は可能です。
しかし、トラブルがある状態の持分は、一般的な不動産と比べて買い手が見つかりにくい傾向があります。 これは、購入後にトラブルに巻き込まれるリスクを懸念する買い手が多いためです。
そのため、専門の買取業者に依頼するか、価格を調整するなどの工夫が必要になる場合があります。
トラブルの内容や深刻度によって売却の難易度は変わるため、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。