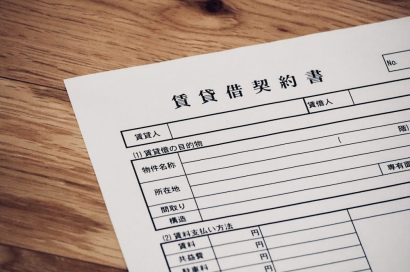共有名義不動産を担保に借り入れできる?不動産担保ローンを利用したい方向け

目次
「共有名義の不動産でも不動産担保ローンは利用できるの?」
「他の共有者に内緒で自分の持分だけを担保に借り入れしたい」
といった疑問を抱えていませんか? 共有名義不動産を担保にした借り入れは可能ですが、単独名義の不動産とは異なる複雑な注意点が存在します。
この記事では、共有名義不動産や共有持分を担保に不動産担保ローンを利用する際の具体的な方法、必要な書類、そして共有持分特有のリスクについて詳しく解説します。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
不動産を共有で所有しているケース
不動産が共有名義となる代表的なケースは、主に以下の二つです。
1. 不動産を相続したケース
一つの不動産を複数の相続人が共同で引き継ぐことで発生します。
遺言がない場合や、不動産を物理的に分けるのが困難な場合、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で、不動産をそのまま共同で所有し続けると決定されたケースです。
2. 不動産を共同購入したケース
主に夫婦や親子が、資金を出し合ってマイホームなどを購入する際に発生します。
夫婦それぞれが自己資金を出し合った場合、出資した金額の割合に応じて持分が設定されます。
例えば、夫婦で住宅ローン(ペアローン、連帯債務など)を組み、ローン負担割合に応じて持分を設定するケースです。
これらのケースでは、各共有者は不動産全体に対してそれぞれの持分割合に応じた権利を持ちます。
不動産の共有状態を確認する方法
所有する不動産が共有名義かどうか、またその持分割合がどうなっているかを知りたい場合は、不動産の登記簿(登記事項証明書)を確認します。
所有者の情報は、登記簿の「権利部の甲区」に記録されています。
登記事項証明書は、法務局の窓口や郵送で請求できるほか、オンラインでの請求が最も手軽で便利です。
平日21時まで請求可能で、窓口よりも手数料が安く、自宅での受け取りも選べます。内容を一時的に確認するだけであれば、「登記情報提供サービス」を利用すれば、PDFファイルで手軽に確認できます。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
共有名義不動産を担保に借り入れは可能?
共有名義不動産を担保に借り入れをする方法は、大きく分けて二つのパターンがあります。
①共有名義不動産全体を担保にするケース
通常の不動産担保ローンでは、不動産全体を担保にするため、すべての共有者の同意が必要となります。
これは、もし借り入れた人が返済できなくなった場合、不動産全体が競売の対象となり、他の共有者の持分も失われるリスクがあるためです。
この場合、融資を受ける人だけでなく、他の共有者も「物上保証人」として抵当権設定契約に同意する必要があります。
物上保証人とは、他人の債務のために自身の財産を担保として提供する人のことです。
そのため、もしあなたが他の共有者に内緒で借り入れをしたいと考えていても、不動産全体を担保にする場合は事実上不可能となります。
また、共有者の中に未成年者や認知症の高齢者がいる場合、その同意が無効になったり取り消されたりするリスクがあるため、融資自体が困難になる可能性もあります。
②自身の共有持分のみを担保にするケース
ご自身の共有持分のみを担保にして借り入れを行う場合、他の共有者の同意は不要です。
これは、あなたが自身の持分を自由に処分できる権利(民法第206条)を持っているためです。
この方法であれば、他の共有者に知られることなく融資を受けることが可能です。
ただし、このタイプのローンを取り扱っている金融機関は限られているため、専門の業者を探す必要があります。
共有名義不動産全体を担保にする場合と持分のみを担保にする場合の比較表
| 項目 | 共有名義不動産全体を担保にする場合 | 自身の共有持分のみを担保にする場合 |
| 必要な同意 | 共有者全員の同意が必須 | 他の共有者の同意は不要 |
| 他の共有者への影響 | 借り入れが返済不能になった場合、不動産全体が競売の対象となり、他の共有者の持分も失われるリスクがある(物上保証人となる) | 借り入れが返済不能になった場合、自身の持分のみが競売の対象となる。他の共有者の持分には直接影響しない。 |
| 借り入れの主体 | 原則、不動産全体の所有者である共有者全員(連帯債務者または連帯保証人となることが多い) | 自身の持分所有者(借り入れをする共有者)のみ |
| 融資額の傾向 | 単独名義不動産に近い評価額で、より高額な融資が期待できる場合がある(ただし、共有者全員の信用力に依存) | 不動産全体を担保にする場合よりも、融資額は低くなる傾向がある |
| 担保評価 | 不動産全体の市場価値に基づいて評価されるため、一般的に評価は高い | 共有持分単独での市場流通性が低いため、評価は低くなる傾向がある |
| 利用できる金融機関 | 一般的な金融機関(銀行、信用金庫など)でも利用可能(ただし、共有者全員の同意が条件) | 共有持分専門の不動産担保ローン業者が主な選択肢となる。一般的な金融機関では難しい場合が多い |
| 手続きの複雑さ | 共有者全員の同意形成、連帯保証人確保など、調整に時間がかかる場合がある | 他の共有者との調整が不要なため、比較的スムーズに手続きを進められる場合がある |
| 秘密保持 | 他の共有者に借り入れの事実が知られる(同意が必要なため) | 他の共有者に知られずに手続きを進められる可能性が高い |
| 返済不能時のリスク | 不動産全体が競売対象となる。共有者全員が家を失うリスク。 | 自身の持分が競売対象となる。他の共有者は直接影響を受けないが、新たな共有者が加わる可能性あり。 |
| 共有物分割後の抵当権 | 分割後も、設定された抵当権は分割された不動産全体またはその承継部分に残る可能性がある。 | 分割後も、設定された抵当権は自身の持分が移転した先の不動産(またはその持分)に残る可能性がある。 |
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
共有持分専門の不動産担保ローンのメリット
一般的な金融機関では難しいとされる共有持分を担保にした借り入れですが、共有持分専門の不動産担保ローン業者であれば、そのメリットを享受できる可能性があります。
他の共有者に知られずに借り入れができる可能性
専門のローン業者は、あなたの共有持分のみを担保として評価するため、他の共有者の同意を必要としません。これにより、家族や親族に借り入れの事実を知られたくない場合に、内密に資金調達を進めることが可能です。
通常のローンより高い査定額が期待できる理由
一般的な金融機関は共有持分の担保評価に慎重な姿勢を示し、融資額が低くなる傾向があります。
しかし、共有持分専門の業者は、共有持分の評価に関するノウハウや独自のリスクヘッジ手法を持っているため、通常のローンよりも高い査定額で融資を受けられる可能性があります。彼らは共有持分の流動性や潜在的な価値を適切に評価できるからです。
自身の持分だけで融資を受けられる強み
最大のメリットは、不動産全体ではなく、あなた自身の持分だけで融資が受けられる点です。これにより、他の共有者に迷惑をかけることなく、必要な資金を調調達できます。万が一返済が滞った場合でも、影響が及ぶのはあなたの持分のみとなります。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
不動産担保ローンで共有名義不動産を担保にする際の注意点
専門のローン業者を利用しない場合、共有名義不動産を担保にする際にはいくつかの大きな課題とリスクが伴います。
共有名義不動産を担保に借り入れできる金融機関は少ない
一般的な金融機関が共有持分単独での融資に消極的なのは、主に以下の理由からです。
- 担保価値の評価が困難
共有持分は、不動産全体の一部であるため、単独で売却しようとしても買い手が見つかりにくく、市場価格が大幅に下がる傾向があります。これは、持分を購入しても、共有物全体の管理や処分には他の共有者の同意が必要となるため、制約が多いからです。 - 債権回収の難しさ
万が一借り入れた人が返済できなくなり、担保を処分して債権を回収しようとした場合、共有持分だけでは競売での売却が難しく、回収額が低くなるリスクが高いと判断されます。
他の共有者への影響と同意の必要性
不動産全体を担保に不動産担保ローンを組む場合、他の共有者も物上保証人となり、その同意が不可欠です。
- 物上保証人による影響と、他の共有者への通知の必要性:
融資を受けた人が返済できなくなると、物上保証人である他の共有者の持分も競売の対象になる可能性があります。そのため、他の共有者に無断で抵当権を設定することはできませんし、同意を得る過程で借り入れの事実が知られることになります。 - 連帯保証人が必要となる可能性:
金融機関によっては、共有者全員に連帯保証人となることを求めるケースもあります。この場合、借りた人が返済不能になったら、連帯保証人である共有者全員がその債務の責任を負うことになります。
通常物件より融資額が低くなる傾向とその理由
共有名義不動産を担保にする場合、単独名義の不動産と比較して、担保評価額が低くなり、結果として融資額も少なくなる傾向があります。これは、前述の通り、共有持分には以下のような制約があるためです。
- 住んでいなくても固定資産税などの費用を負担する義務がある(民法第253条第1項)。
- 一定の賃貸やリフォーム、不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要(民法第251条第1項、252条第1項)。
- 不動産を独占利用する場合は、他の共有者に持分割合に応じた家賃相当額を支払う義務がある(民法第249条第2項)。
これらの制約が、共有持分の市場価値を下げる要因となり、担保評価額にも影響を与えます。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
担保評価額の算出方法と持分割合の関係
共有持分を担保にする際の融資額は、その持分の評価額に大きく左右されます。この評価額は、不動産全体の価値と自身の持分割合に基づいて算出されます。
出資額が共有持分割合を決定する場合
不動産を自己資金のみで共同購入した場合、各共有者の持分割合は、それぞれが出資した金額の割合で決まります。例えば、4,000万円の不動産をAさんが3,000万円、Bさんが1,000万円出資した場合、Aさんの持分割合は4分の3、Bさんは4分の1となります。この持分割合が、融資額の基本的な算出根拠となります。
ローン利用時の持分割合と借り入れ可能額
住宅ローンなどを利用して不動産を購入した場合、持分割合は、単に自己資金の出資割合だけでなく、ローンの契約者とその借入額によっても影響を受けます。
例えば、夫が主債務者としてローンを組んだ場合、夫の持分割合が大きくなるのが一般的です。
担保評価額は、不動産全体の評価額に自身の持分割合を乗じて算出されるため、持分割合が低いほど、借り入れできる金額も少なくなる傾向があります。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
共有名義不動産を担保に借入する際の必要書類リスト
共有名義不動産を担保に借り入れを行う際には、一般的な不動産担保ローンと同様に多くの書類が必要です。ただし、業者によって求められる書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
- 本人確認書類:
運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書が必要です。 - 印鑑証明書と実印:
ローン契約書には実印の押印が求められることが多いため、印鑑証明書が必要です。発行から3ヶ月以内など、有効期限が設けられている場合が多いので注意しましょう。 - 収入を証明する書類:
給与所得者は源泉徴収票、個人事業主は確定申告書の控えなどが必要です。課税証明書や所得証明書が認められる場合もあります。 - 納税証明書:
固定資産税など、税金の納税証明書の提出を求められることがあります。税金の滞納がある場合、審査に影響が出る可能性があります。 - 不動産に関する権利書類:
登記事項証明書、登記済権利証(登記識別情報)、公図、地積測量図、建物図面、建築確認通知書、固定資産評価証明書など、担保不動産の評価に必要な書類を準備しましょう。 - 収入印紙:
金銭消費貸借契約書にかかる印紙税や、抵当権設定登記の登録免許税は、収入印紙で納めるのが一般的です。
登記情報と現住所・氏名が異なる場合の追加書類
もし、登記簿に記載されている住所や氏名が現在のものと異なる場合は、追加で書類の提出が必要となることがあります。例えば、住民票や戸籍謄本など、登記情報と現在の情報が一致していることを証明する公的書類を求められることがあります。これは、本人確認を確実に行い、不正な登記を防ぐための手続きです。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
共有名義不動産を担保にする際の注意点
共有名義不動産を担保に借り入れを行う際は、特に以下の点に注意が必要です。
他共有者も持分を失うリスクがある
共有名義不動産全体を担保に融資を受ける場合、あなただけでなく、他の共有者全員が担保提供者となる必要があります。もし借り入れた人が返済できなくなった場合、不動産全体に設定された抵当権が実行され、競売によって共有者全員の持分が失われるリスクがあります。この点は、他の共有者との関係性において非常に重要なため、十分な説明と合意が必要です。
借り入れ額が少なくなる可能性がある
共有持分のみを担保にした場合、融資額が低くなる傾向があるのは、主にその持分の市場価値が、不動産全体に比べて著しく低いと評価されるためです。金融機関やローン業者は、融資した資金を確実に回収できるかを最も重視します。共有持分の場合、債権回収が難しくなる複数の要因があるため、貸し倒れのリスクを考慮して融資額を抑えるのです。
共有持分に設定された抵当権は、借り入れた人が返済できなくなった場合にその持分を競売にかけることになります。しかし、競売で共有持分だけが売却されたとしても、その後の不動産の管理や利用に関して新たな共有者(落札者)と残りの共有者との間で紛争が生じやすいため、一般的な不動産の競売よりも複雑化する傾向があります。この手続きの複雑さも、金融機関がリスクと捉える要因です。
これらの理由から、共有持分のみを担保にする場合は、たとえ不動産全体の評価が高くても、融資額は低く抑えられることになるのです。
共有物分割しても抵当権は残る
たとえ自分の共有持分にだけ抵当権を設定して融資を受けたとしても、その後、共有物分割(例:兄弟で土地を分割する、一方が持分を買い取るなど)が行われた場合でも、抵当権は消滅せず、分割後の不動産(またはその取得者の所有する部分)に残ってしまいます。これは、抵当権が不動産そのものに設定される権利であるためです。
例えば、兄が自身の持分に抵当権を設定し、後に弟が兄の持分を買い取り単独所有となった場合(全面的価格賠償)、弟が取得した不動産には兄が設定した抵当権がそのまま残ってしまうことになります。これは、現物分割や換価分割の場合も同様です。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
共有名義不動産を担保にできない場合の資金調達方法
もし共有名義不動産を担保にした借り入れが難しい場合でも、資金調達の道は他にもあります。
無担保ローンの検討
不動産を担保としないフリーローンやカードローンも選択肢の一つです。これらは担保が不要なため、審査や手続きが比較的迅速に進むことが多いですが、不動産担保ローンに比べて金利が高く設定されており、借り入れできる金額も少額になる傾向があります。
国や地方自治体の公的融資制度の活用
国や地方自治体が提供している公的融資制度は、特定の条件(例:低所得者、特定の事業を行う人など)を満たすことで利用できる場合があります。これらは比較的低金利で利用できることが多く、生活資金や事業資金など、様々な目的に応じた制度が存在します。
事業資金向け融資制度(日本政策金融公庫など)
資金使途が事業に関するものであれば、日本政策金融公庫のような公的金融機関の融資制度を検討できます。これらの制度は、中小企業や個人事業主向けの低金利融資、あるいは担保・保証人なしで利用できる融資制度を提供している場合があります。事業計画の提出などが必要となりますが、条件が合えば有力な選択肢となります。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
共有名義不動産の担保借入れに関するよくある疑問Q&A
Q1: 共有名義不動産全体を担保に、他の共有者に内緒で借り入れできますか?
A: いいえ、共有名義不動産全体を担保にする場合、他の共有者に内緒で借り入れることはほぼ不可能です。 不動産全体に抵当権を設定するには、法律上、すべての共有者の同意が必須だからです。金融機関は、借り入れた人が返済できなくなった際のリスクを考慮し、他の共有者にも「物上保証人」として抵当権設定契約に同意してもらう必要があるため、必ず借り入れの事実が知られます。
Q2: 自分の共有持分だけを担保に、他の共有者に知られずに借り入れできますか?
A: はい、自身の共有持分のみを担保にする場合は、他の共有者の同意なしに借り入れできる可能性が高いです。 自己の共有持分は自由に処分できる権利があるため、他の共有者の同意は不要です。ただし、一般的な銀行では共有持分単独での融資は難しいことが多く、共有持分を専門に扱う不動産担保ローン業者(ノンバンクなど)を探す必要があります。
Q3: 共有持分のみを担保にした場合、融資額は低くなりますか?
A: はい、共有持分のみを担保にした場合、不動産全体を担保にするよりも融資額が低くなる傾向があります。 これは、共有持分が不動産全体の一部であり、単独での市場流通性が低いためです。万が一返済が滞り、抵当権を実行して競売にかけても、買い手が見つかりにくく、高値で売却できないリスクが高いと金融機関が判断するため、貸し倒れリスクを考慮して融資額を抑える傾向があります。
Q4: 共有名義不動産を担保にしたローンで、返済ができなくなったらどうなりますか?
A:
- 不動産全体を担保にしている場合:
借り入れた人が返済できなくなると、金融機関は抵当権を実行し、不動産全体が競売にかけられる可能性があります。この場合、他の共有者の持分も失われるリスクがあります。 - ご自身の共有持分のみを担保にしている場合:
返済が滞ると、あなたの共有持分のみが競売の対象となります。他の共有者の持分には直接影響はありませんが、第三者がその持分を落札することで、新たな共有者が加わり、共有関係が複雑化する可能性があります。
Q5: 共有名義不動産を担保に借り入れしたい場合、どこに相談すればよいですか?
A: 共有名義不動産を担保に借り入れを検討する場合、状況によって相談先が異なります。
- 共有者全員の同意が得られる場合で、高額な融資を希望するなら:
一般的な銀行や信用金庫の不動産担保ローンを検討できます。 - 自分の共有持分のみを担保にしたい、あるいは他の共有者に知られたくない場合:
共有持分を専門に扱う不動産担保ローン業者(ノンバンクなど)への相談が主な選択肢となります。
いずれの場合も、法的なリスクや税務上の影響を正確に把握するため、弁護士や司法書士、税理士といった専門家にも事前に相談することをおすすめします。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫
まとめ
共有名義不動産や自己の共有持分のみを担保に借り入れをすることは可能です。
ただし、通常の不動産担保ローンを取り扱っている金融機関では難しい場合が多く、共有持分専門の業者を検討する必要があるでしょう。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分に特化した専門仲介業者として、これまでの豊富な実績とノウハウを活かし、お客様の共有持分に関するお悩み解決をサポートしています。
共有名義不動産や共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
共有名義不動産・共有持分を担保にした不動産担保ローンのご相談はこちら ≫

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
中央プロパティー代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士
都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。
共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。
「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。