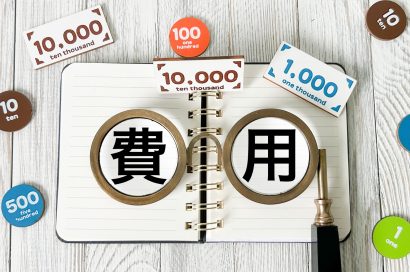持分放棄する際の贈与税に注意!みなし贈与や計算方法を税理士が解説
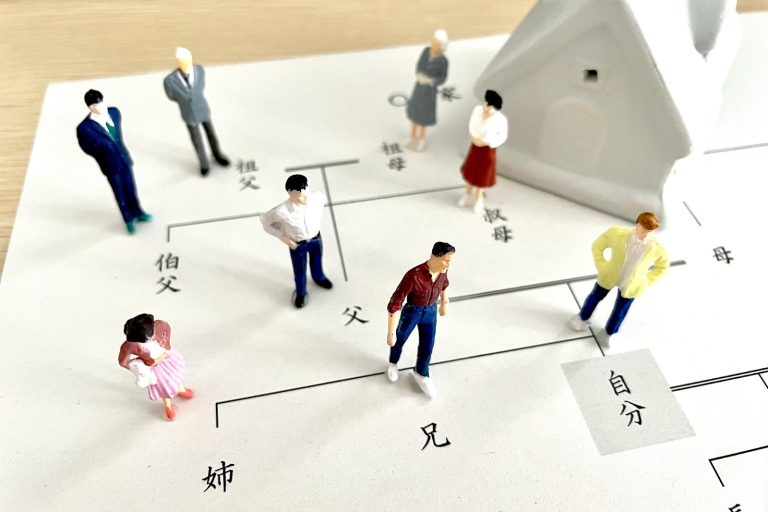
目次
「共有持分を手放したいけれど、贈与税がかかるの?」「放棄すれば税金は発生しないのでは?」と疑問に感じていませんか?
共有名義不動産の持分放棄は、一見すると無償で手放す行為ですが、実は税法上、「みなし贈与」として贈与税が課税される可能性があります。この複雑な税務上の扱いは、多くの方が誤解しやすいポイントです。
この記事では、持分放棄がどのような場合に贈与税の対象となるのか、みなし贈与とは何か、そして贈与税の計算方法まで、税理士の視点から詳しく解説します。
持分放棄を検討している方はもちろん、家族間での不動産移転を考えている方も、ぜひ参考にしてください。
「持分放棄」とは?
持分放棄とは、共有している不動産などの持分(所有権の割合)を放棄することを指します。例えば、兄弟で実家を共有している場合、一方が自分の持分を放棄することで、残りの共有者へその持分が帰属することになります。
持分放棄は、以下の2つのケースでよく行われます。
- 共有状態の解消: 共有名義の不動産を単独名義にしたい場合。
- 相続対策: 生前のうちに特定の財産を特定の人物に集約させたい場合。
ただし、持分放棄は法的な手続きであり、その内容によっては贈与税が発生する可能性があるため、慎重な検討が必要です。
持分放棄で贈与税がかかるケース、かからないケース
持分放棄によって贈与税が発生するかどうかは、その状況によって異なります。
贈与税がかかるケース
原則として、持分放棄は、放棄された持分が他の共有者へ移転することになるため、経済的利益の移転があったとみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。特に、特定の共有者に無償で持分を移転させる意図がある場合は、贈与と判断される可能性が高いです。
贈与税がかからないケース
一方、以下のようなケースでは、贈与税がかからない場合があります。
- 法定相続人が持分放棄した場合(相続放棄):
相続が発生した際に、相続人全員が相続放棄をした場合、その不動産は相続人のものではなくなり、別の相続人に移転することになります。この場合は、相続放棄自体が財産の放棄であり、贈与ではありません。ただし、特定の相続人だけが放棄し、他の相続人が取得する場合は贈与税が発生する可能性があります。 - 共有物分割の一環として持分放棄が行われた場合:
共有物を分割する際に、他の共有者との間で金銭的な調整(代償金の支払いなど)が行われ、対価性がある場合は、贈与とはみなされないことがあります。
要注意!「みなし贈与」とは?
持分放棄において特に注意が必要なのが「みなし贈与」です。みなし贈与とは、実質的には贈与であるにもかかわらず、形式上は贈与ではないと見える取引に対して、税法が贈与とみなして課税を行う制度です。
持分放棄のケースでみなし贈与となる典型的な例は、特定の共有者のみが持分放棄を行い、他の共有者全員がその利益を得る場合です。例えば、3人で共有している不動産のうち1人が持分を放棄し、残りの2人がその放棄された持分をそれぞれの持分に応じて取得した場合、放棄した人から残りの2人への贈与とみなされる可能性があります。
この「みなし贈与」の考え方は非常に複雑で、個別の状況によって判断が分かれるため、専門家である税理士に相談することが不可欠です。
贈与税の計算方法と税率
持分放棄によって贈与税が発生する場合、その税額は以下の方法で計算されます。
贈与税の計算式 贈与税額 = (贈与された財産の価額 – 基礎控除額) × 税率 – 控除額
放棄された持分の時価が贈与された財産の価額となります。不動産の時価は、固定資産税評価額や路線価を参考に、専門家が算定するのが一般的です。
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
贈与税の税率は、贈与額によって異なります。一般贈与財産(特例贈与財産に該当しないもの)と特例贈与財産(親子間・祖父母孫間の贈与など)で税率が異なり、累進課税が適用されます。
| 贈与財産の金額 | 一般贈与財産(税率・控除額) | 特例贈与財産(税率・控除額) |
| 200万円以下 | 10%・0円 | 10%・0円 |
| 300万円以下 | 15%・10万円 | 15%・10万円 |
| 400万円以下 | 20%・25万円 | 20%・20万円 |
| 600万円以下 | 30%・65万円 | 30%・90万円 |
| 1,000万円以下 | 40%・125万円 | 40%・170万円 |
| 1,500万円以下 | 45%・175万円 | 45%・270万円 |
| 3,000万円以下 | 50%・250万円 | 50%・420万円 |
| 4,500万円以下 | 55%・400万円 | 55%・640万円 |
| 4,500万円超 | 55%・650万円 | 55%・640万円 |
※上記の税率は税制改正によって変更される可能性があります。
贈与税を抑えるための対策
1. 共有物分割協議の活用:適正な対価の授受がカギ
「共有物分割協議」とは、複数の人で共有している不動産を、単独所有にする、または共有者間で持分を変更する際に、共有者全員で話し合い、合意に基づいて分割する方法です。
この際、持分放棄という形式ではなく、金銭的な調整(代償金)を伴う「共有物分割」として処理することで、贈与税の課税リスクを軽減できる場合があります。
具体的な方法とポイント:
- 代償金(清算金)の支払い:
持分を放棄する側が、放棄する持分の価値に見合った金銭を、持分を取得する側から受け取る形を取ります。この代償金が、放棄する持分の適正な時価と釣り合っていれば、税務上は贈与ではなく「対価の授受」とみなされ、贈与税は課税されません。 - 適正な時価の算定が重要:
代償金の額が時価と比べて著しく低い場合、差額部分が贈与とみなされる可能性があります。不動産の時価は、固定資産税評価額や路線価だけでなく、周辺の取引事例なども考慮して、不動産鑑定士や税理士などの専門家が客観的に算定することが非常に重要です。 - 共有物分割登記:
協議がまとまったら、法務局で「共有物分割による所有権移転登記」を行います。この登記は、持分放棄による所有権移転登記とは異なり、登記原因が「共有物分割」となります。 - 契約書の作成:
代償金の額や支払い時期などを明記した共有物分割協議書(合意書)を必ず作成しましょう。これは、税務調査が入った際に、贈与ではないことを証明するための重要な証拠となります。
2. 負担付贈与の検討:債務の引き受けで贈与額を圧縮
「負担付贈与」とは、受贈者(財産をもらう人)が、贈与者(財産をあげる人)の一定の債務(借金など)を引き受けることを条件として行われる贈与のことです。持分放棄のケースで言えば、放棄する持分に住宅ローンなどの債務が付随している場合、その債務を持分を取得する側が引き継ぐことで、贈与税の課税対象となる金額を減らすことができます。
例えば、共有不動産に住宅ローンが残っており、持分を放棄する側もそのローンの債務者である場合、持分を取得する側がそのローンをすべて引き受けることで、引き受けたローンの額が贈与額から控除されます。
- 贈与額の計算:
負担付贈与の場合、贈与税の対象となるのは「贈与された財産の価額」から「引き受けた債務の額」を差し引いた金額となります。- 例: 時価3,000万円の持分(残債1,000万円)を負担付贈与する場合、贈与税の対象となるのは2,000万円(3,000万円 – 1,000万円)となります。
負担付贈与は、通常の贈与よりも税額の計算が複雑になります。債務の内容や金額、不動産の評価額など、様々な要素が絡むため、必ず税理士に相談して計算してもらうようにしましょう。
金融機関との間で、債務者の変更手続きなどを確実に行い、債務の引き受けを明確にしておく必要があります。
3. 専門家への相談:税理士との連携が成功の鍵
上記の対策は、税務上の判断が非常に複雑であり、個々の状況によって最適な方法や注意点が異なります。そのため、持分放棄を検討する前に、必ず税理士などの専門家に相談することが最も重要です。
税理士は、みなし贈与に該当するリスクがないかを入念にチェックし、税務調査で指摘を受けないための対策を講じます。
贈与税の計算は、特例や控除の適用など複雑なケースが多く、誤った申告は追徴課税のリスクを招きます。税理士は正確な税額計算を行い、適切な申告手続きを代行してくれます。
持分放棄の注意点
共有持分の放棄を検討する際、以下の点には特に注意が必要です。
1. 「名義預金」とみなされないか
持分放棄の対価として金銭を受け取る場合、その金銭が名義預金とみなされないよう細心の注意が必要です。名義預金とは、口座名義人と、その預金の真の所有者(実質的に財産を管理・運用している人)が異なる預金を指します。
例えば、子から親に代償金を支払う形を取ったとしても、その資金源が実は親から子に贈与されたものであった場合、税務署は実態を見て「親から子への贈与」であり、さらに「子から親への代償金の支払いは、実質的に親から子への贈与資金の還流(名義預金)」と判断し、二重に贈与税を課税する可能性があります。
このような状況は、親子間や夫婦間といった親族間の取引で発生しやすく、税務署は特に厳しくチェックします。
「名義預金」とみなされないための対策としては、以下の二つです。
- 資金の出所を明確にする:
代償金や負担付贈与の資金の出所を明確にし、受領する側がその資金を自ら管理・運用していることを証明できるようにしておく必要があります。例えば、贈与税を支払った後の預金であることや、自己の労働収入であることなどを明確にします。 - 契約書・証拠の保管:
金銭の授受に関する契約書や振込明細などの証拠を必ず保管しましょう。
2. 「時価の算定」の適正性
贈与税の計算において、放棄される持分の「時価」の算定は極めて重要です。この時価が適正でないと判断された場合、税務署から追徴課税の対象となる可能性があります。
贈与税は「贈与された財産の価額」に基づいて計算されます。この「価額」が適正でなければ、納税額も適正でなくなります。
税務署は、申告された贈与財産の価額が著しく低いと判断した場合、自ら適正な時価を算定し直し、その差額に対して追徴課税を行うことがあります。
時価の算定ミスによる過少申告は、過少申告加算税や延滞税といったペナルティの対象となります。
適正な時価を算定するためのポイントは、以下の3つです。
- 不動産鑑定士による鑑定評価:
最も信頼性が高く、客観的な時価を把握できる方法です。特に高額な不動産や、評価が難しい特殊な不動産の場合に有効です。 - 税理士による評価:
税理士は、不動産の評価方法(固定資産税評価額、路線価、取引事例など)に精通しており、税務上の評価額の算定をサポートしてくれます。 - 複数の情報源を参照:
公示地価、基準地価、周辺の類似物件の取引事例などを参考に、多角的に時価を判断することが望ましいです。
安易に固定資産税評価額や路線価をそのまま時価として使用すると、実際の時価と乖離がある場合にリスクが生じることがあります。必ず専門家と相談し、最も適切な方法で時価を算定するようにしましょう。
持分放棄の手続きと必要書類
持分放棄の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
- 放棄の意思表示:
持分を放棄する人が、他の共有者に対して放棄の意思を明確に伝えます。 - 登記申請:
放棄された持分を他の共有者に移転するために、法務局で所有権移転登記を申請します。この際、登記原因証明情報(放棄を証明する書類)や印鑑証明書などの書類が必要になります。 - 税務申告:
贈与税が発生する場合は、期限内に税務署へ贈与税の申告を行います。
必要となる主な書類は以下の通りです。
- 持分放棄に関する合意書(または放棄書)
- 持分放棄者の印鑑証明書
- 登記識別情報(権利証)
- 固定資産評価証明書
- その他、事案に応じて必要となる書類
持分放棄以外で持分を手放す方法
不動産の共有持分を手放す方法は、持分放棄以外にも主に以下の3つの選択肢があります。
- 持分の売却(譲渡)
- 共有物分割(代償分割・現物分割)
- 持分の贈与
| 方法 | メリット | デメリット | 主な税金 |
| 1. 持分の売却(譲渡) | ・金銭を得られる(最も直接的な対価) ・共有関係を完全に解消できる ・居住用財産の特例適用で税負担軽減の可能性 | ・買い手を見つけるのが難しい(特に第三者への売却) ・売却価格が低くなる傾向がある ・手続きがやや煩雑 | ・譲渡所得税(売却益が出た場合) ・印紙税 |
| 2. 共有物分割 | |||
| a. 代償分割 | ・現金を得られる(適正な対価) ・共有関係を解消できる ・適切に行えば贈与税リスクを回避しやすい | ・代償金支払い側の資金力が必要 ・不動産全体の評価が重要 ・代償金受け取り側に譲渡所得税の可能性 | ・譲渡所得税(代償金受け取り側で売却益が出た場合) |
| b. 現物分割 | ・現金が不要 ・共有関係を解消できる | ・物理的に困難な場合が多い(一つの建物など) ・分割後の評価調整が難しい ・不均等だと税金発生の可能性 | ・原則非課税(等価交換の場合) ・譲渡所得税・贈与税(不均等分割の場合) |
| 3. 持分の贈与 | ・手続きが比較的シンプル ・特定の親族に財産を集約できる | ・多額の贈与税が発生する可能性が高い(もらう側) ・不動産取得税も発生 ・税負担が受贈者に集中 | ・贈与税(もらう側) ・不動産取得税 ・登録免許税(贈与分) |
持分放棄以外のこれらの方法は、それぞれに異なる税務上の影響や手続きの複雑さがあります。
- 金銭を得たい: 売却や代償分割を検討。
- 共有関係をシンプルにしたい: 売却、代償分割、現物分割(可能な場合)を検討。
- 特定の親族に引き継ぎたい: 贈与(ただし税負担大)、または代償分割を検討。
どの方法が最も適切かは、共有持分の価値、他の共有者の意向や資金力、自身の資金ニーズ、そして最も重要な税金(譲渡所得税、贈与税、不動産取得税など)の負担を総合的に考慮して判断する必要があります。
必ず専門家(税理士、弁護士、司法書士など)に相談し、ご自身の状況に合った最適な方法を選びましょう。
まとめ:持分放棄は専門家への相談が不可欠
持分放棄は、共有不動産の整理や相続対策として有効な手段ですが、贈与税が関わる可能性が高いため、安易に手続きを進めるのは危険です。特に「みなし贈与」の判断は複雑であり、素人判断で進めると、後から多額の贈与税を請求されることになりかねません。
持分放棄を検討する際は、必ず税理士や弁護士などの専門家に相談し、事前に税務上の影響を確認することが非常に重要です。
当社センチュリー21中央プロパティーは、共有持分の放棄や売却に関するアドバイスを行っております。
共有持分の放棄やご売却をご検討の方は、ぜひご相談ください。

共有者とのトラブル、相続した不動産にお悩みの方は、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用ください!
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の無料査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
税理士
ワールド法律会計事務所 代表
東京税理士会 日本橋支部所属登録番号 117651
ワールド法律会計事務所の代表を務める、相続税のスペシャリスト。特に共有持分の相続案件で多く相談される相続税が得意分野。
生前贈与や親族間の不動産売買など、多岐にわたる相続対策にも豊富な経験と実績を持つ。税務の専門知識と実践的なアドバイスで、複雑な税金問題をサポート。