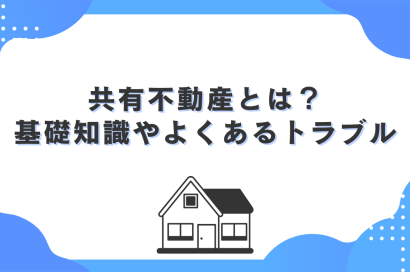共有持分の使用貸借は危険!その理由とトラブル事例を徹底解説

目次
共有者の一人が無償で不動産を使用している場合、他の共有者が黙認すると「使用貸借」が成立し、賃料請求や立ち退き要求が困難になります。
この状態を放置すると、税金や維持管理費を払い続けるだけでなく、最悪の場合、相手に取得時効で不動産を「乗っ取られる」危険性もあります。
この記事では、共有持分の使用貸借に潜む危険性と、実際に起こりうるトラブル事例、そして問題が深刻化する前にできる対策を徹底的に解説します。
共有持分の「使用貸借」とは?
共有している不動産を、特定の人に無償で使わせる契約を「使用貸借(しようたいしゃく)」と呼びます。これは、いわば“タダで貸す”契約であり、身内間や親しい関係で行われやすいものです。
たとえば、兄弟で相続した実家に兄だけが住み、弟には何の利益もない状況。この場合、兄の占有が「使用貸借」とみなされることがあります。
収益を得ることなく、税金や修繕費を負担する立場に置かれた共有者にとって、この状態は深刻な不公平となりやすく、後のトラブルへと発展しがちです。
共有持分の使用貸借が危険な理由
共有不動産における使用貸借(無償での貸し借り)は、身近な関係者同士で安易に行われがちですが、実は多くのリスクを内包しています。
以下は、共有持分の使用貸借が危険とされる主な理由です。
- 契約が「口約束」で成立してしまう
- 借り手が共有者以外でも成立してしまう
- 不法占拠とならず、正当な使用と認定される場合がある
- 一度成立すれば、賃料の請求はできない
- 維持費・税金などの費用だけがのしかかる
- 長期間の占有で「取得時効」が成立する恐れがある
契約が「口約束」で成立してしまう
使用貸借は、書面での契約がなくても口頭の合意だけで成立します。共有者の一人が黙認していたことを理由に、「合意があった」とみなされるケースもあり、後からトラブルに発展することがあります。
借り手が共有者以外でも成立してしまう
共有者の承諾なしに、他の共有者が知人などに不動産を貸している場合でも、黙示的な同意があったとされれば、法的には使用貸借が成立する余地があります。
こうなると、他の共有者が追い出すことは非常に難しくなります。
不法占拠とならず、正当な使用と認定される場合がある
他の共有者からの使用貸借が成立していれば、無償であっても借主は「正当な権利に基づいて占有している」と見なされます。そのため、不法占拠としての明け渡し請求が通らないケースもあるのです。
一度成立すれば、賃料の請求はできない
使用貸借は「無償」が前提の契約です。そのため、契約成立後に「やはり賃料を払ってほしい」と申し出ても、法律上それが認められることは基本的にありません。
維持費・税金などの費用だけがのしかかる
収入がないにもかかわらず、共有不動産には固定資産税・都市計画税・修繕費・管理費などのコストが発生します。これらは共有者全員が負担する義務があり、実際に住んでいない人にとっては極めて不利な状態です。
長期間の占有で「取得時効」が成立する恐れがある
借主が長年にわたり占有を続けると、民法上の「取得時効」が成立し、所有権を主張されるリスクがあります。(民法162条)
- 占有期間が20年以上(または、善意かつ過失なしなら10年以上)
- 「自分のものだ」とする意思を持って占有している
といった条件を満たすと、共有者が持分の一部または全部を失う事態に発展しかねません。
使用貸借が成立する2つの要件
「勝手に貸されていたのに、なぜ成立するのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。ここでは、使用貸借が共有不動産で成立する仕組みを見てみましょう。
短期の貸し出し(管理行為)
建物で3年以内、土地で5年以内といった短期の使用貸借は、民法上「管理行為」に分類されます。
これは、共有持分割合の過半数の賛成があれば実行できます。この場合、所有者の人数は関係なく、持分割合の多い共有者が単独で決定できてしまう可能性があります。
長期の貸し出し(変更行為)
建物で3年超、土地で5年超の長期にわたる貸し出しは「変更行為」とみなされます。
この場合は共有者全員の同意が必須となり、成立のハードルはぐっと上がります。
ただし、期間の定めがなくても、客観的に長期間の利用が想定される場合は変更行為として扱われることがあります。
使用貸借契約を終了させるには?
共有不動産の無償使用を終わらせるには、以下のような条件が必要です。
- 過半数の同意と解除事由の存在
- 借主の死亡で自動的に終了するケース
過半数の同意と解除事由の存在
短期の使用貸借契約であれば、共有者の持分過半数の合意があれば解除が可能です。
ただし、契約で定められた期間の終了や、目的の達成・違反など、正当な解除理由が求められます。
一方で、契約の目的や使用期間が曖昧なまま長期間使われているケースでは、解除の難易度が高まることもあります。
借主の死亡で自動的に終了するケース
民法では、借主が死亡すると原則として使用貸借契約は終了するとされています。(民法597条3項)つまり、借主の相続人が自動的にそのまま住み続けることはできません。
ただし、契約に「地位を相続人が引き継ぐ」といった特約があれば、例外として契約が続く場合もあります。
※注意:貸主が亡くなっても契約は続く
貸主側が死亡した場合、契約は終了せず、貸主の地位が相続人に引き継がれます。そのため、引き続き契約は有効となります。
共有持分の使用貸借をめぐるトラブル事例
共有名義の不動産では、「使用貸借」が予期せぬトラブルを招くことがあります。
ここでは、実際に起こりがちなケースを3つ紹介します。
事例①:知らない第三者がいつの間にか住んでいた
状況:
父親が亡くなり、地方の実家を兄弟3人で相続。ところが、数年後に確認してみると、見知らぬ男性が住んでいた。調べたところ、長男が知人に「住んでいいよ」と勝手に貸していたことが判明。
トラブル:
他の兄弟は一切知らされておらず、当然同意もしていない。
しかし、長男の黙示的な承諾があったとされ、「使用貸借契約が成立している」と判断されてしまった。結果、勝手に住んでいる第三者に対しても、明け渡し請求が難航する事態になってしまった。
事例②:共有者が賃料を払わずに居座り続ける
状況:
母の死後、兄妹で実家を相続。兄がそのまま実家に住み続け、妹は住んでいないにもかかわらず、維持費の半分を負担していた。「せめて賃料を支払ってほしい」と訴えるも、兄は「家賃なんて話はしていない」と拒否。
トラブル:
妹は長年この状態を黙認していたため、法的には「無償の使用貸借が成立していた」とみなされ、賃料の請求が通らなかった。結局、妹だけが金銭的負担を抱え続ける結果になった。
事例③:借主が亡くなったのに、遺族が退去しない
状況:
叔母の厚意で、従兄弟夫婦が叔母の持分のある家に住んでいた。叔母が亡くなった後、他の共有者が「使用貸借契約は終了したので出ていってほしい」と申し入れたが、従兄弟夫婦は「もう何年も住んでいる家。今さら出て行けない」と拒否。
トラブル:
法的には、借主の死亡により使用貸借契約は終了しているはず。しかし、遺族が居座り続けており、話し合いでは解決できず、明け渡しを求める裁判にまで発展してしまった。
まとめ:根本的な問題解決には「共有関係の解消」が最善
共有不動産における使用貸借は、当初は善意から始まったとしても、時間の経過とともに深刻なトラブルに発展するケースが少なくありません。
賃料が得られない、維持費を一方的に負担させられる、さらには所有権を失うおそれがあるなど、共有状態のまま放置することは非常にリスクの高い選択です。
そのような中で、根本的な解決策として最も有効なのが、「共有状態の解消」です。共有物の分割請求や、共有持分の売却を通じて、長引くトラブルや負担から抜け出すことができます。
センチュリー21中央プロパティーは、共有持分の売却を専門に扱う不動産会社です。
✅ 他の共有者の同意がなくても売却可能
✅ 法律・税務の専門家と連携し、スムーズな手続きをサポート
✅ 共有持分の買取に特化しているため、スピーディーかつ適正な価格での対応が可能
「共有者と話し合いができない」「早く手放したい」「相続トラブルを避けたい」など、さまざまなお悩みに対応しています。
共有持分でお悩みの方は、ぜひご相談ください。
CENTURY21中央プロパティー

共有者とのトラブルや相続不動産の売却については、当社の無料相談窓口をご利用ください。
「まずは査定額を知りたい」という方は、以下の査定フォームをご利用ください。
この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。