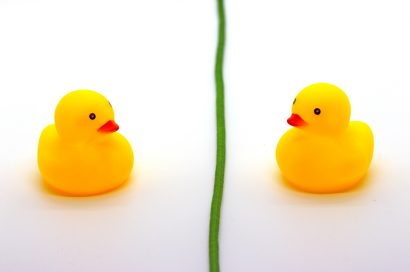【2023年4月民法改正】共有物の管理ルールの変更ポイント|共有持分の基礎知識
【2023年4月民法改正】共有物の管理ルールの変更ポイント
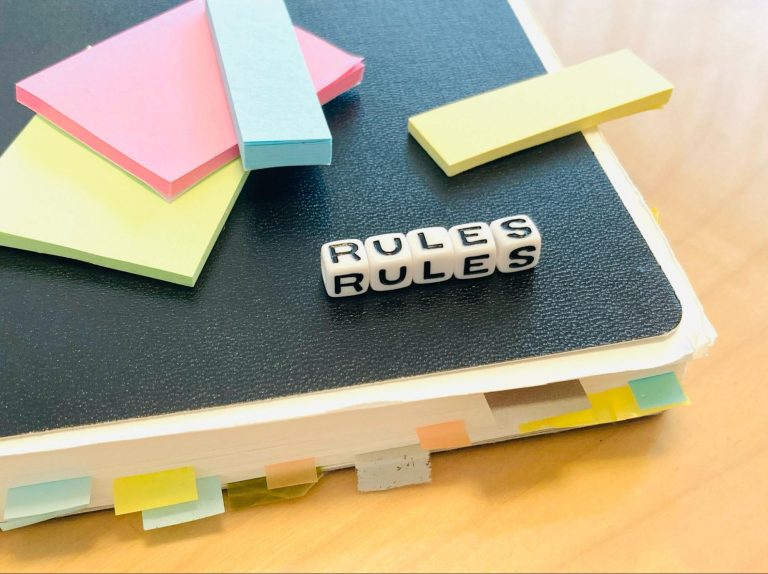
目次
この記事では、2023年の民法改正で改正された共有物の管理ルールについて詳しく解説します。共有名義不動産をお持ちの方、これから不動産相続の予定がある方はぜひご覧ください。
1.不動産における共有物の管理ルールとは
不動産を複数人で所有するのは珍しくありません。
複数人で所有する場合は共有物として扱い、管理する際のルールは民法で定められています。本章では、共有物の概要から最近の民法改正について詳しく解説します。
1-1.共有物とはどんなもの?
共有物とは、複数人で共同して所有する物のことです。
不動産をイメージされる方が多いですが、以下の図1のように車や宝石などの動産も共有物になりえます。
共有物は共有者の数によって持分(所有権の割合)が決められ、共有者は共有物のすべてを持分に応じて使用できます。
例えば、共有者3人で建物を所有する場合を考えてみます。この場合、建物を3等分して使うのは物理的にできません。そのため、一人ひとりが建物のすべてを利用できますが、使用できる日数や階数などが持分に応じて変わります。
共有物についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
1-2.共有物管理の具体的な事例
共有物の管理とは、共有者同士で共有している物(不動産・動産)を管理することです。具体的には、図2のように保存行為・管理行為・変更行為の3つの行為を指します。
各行為を行う際は、共有者の人数や持分価格によって制限がかけられています。
例えば、以下の図3のようなケースを考えてみます。
5人で持分を持つ不動産を売却するには、5人全員の同意を得る必要があります。しかし、もし共有者のなかに所在不明者がいる場合は、共有者全員の同意が取れないため売却が進められません。
また、5人全員の所在がわかっていたとしても、1人だけが同意しない可能性もあります。
そのため共有物の管理がきちんと行われず、放置された空き家を生むケースが多く見られました。
今回の民法改正により、相続後の共有物としての土地の有効活用が期待できます。
改正された民法の概要については次節で紹介します。
1-3.今回の民法改正の概要
今回の民法改正は、2023年4月1日から施行開始されました。
相続後の不動産を有効活用できるように、共有制度が見直されています。
旧民法251条では、たとえリフォームのような軽微な変更であっても変更行為に該当するため、共有者全員の同意が必要でした。全員と連絡がとれ同意が得られれば問題ありませんが、共有者の所在や連絡先がわからず、同意を得られないケースもありました。
また、旧民法では相続登記が義務化されていなかったため、相続が発生しても登記されず、結果として所有者不明の土地も発生しています。
このような背景から、民法の改正が行われました。
改正民法251条1項では、軽微な変更については持分価格の過半数で決定できるようになりました。
また、裁判所の許可があれば、共有者自体が不明な場合や共有者の所在が不明な場合でも、その共有者以外の者で変更行為が可能です。
2. 民法改正で共有不動産の管理はどう変わる?
民法改正されたことで、今までとルールが変わり不動産の管理にも影響が出ています。
そこで本章では、民法改正で共有不動産の管理がどう変わるのかを以下のポイントから解説します。
- 共有物の管理ルールの変更ポイント
- 変更によるメリット
- 変更によるデメリット
今後、相続を控えている人はそれぞれのポイントを参考にしておくとよいでしょう。
2-1.共有物の管理ルールの変更ポイント
共有物の管理ルールの変更ポイントは以下の通りです。
- 全員が同意しなくても変更行為がおこなえる
- 共有者に所在不明者がいても変更行為がおこなえる
- 共有者に所在不明者がいた場合に、その者の持分を取得しやすくなった
旧民法では共有物の変更、処分、軽微な変更の場合に共有者全員の同意が必要でした。そして旧民法の場合は、相続登記が義務ではなかったため、相続が発生しても相続登記がなされず、多くの所有者が分からない土地がありました。
相続人が何世代にも渡っていたり、相続人の一部が所在不明であったりすると共有者の全員が同意できず土地の有効活用ができませんでした。
一方改正された民法では、共有者全員ではなく持分価格の過半数でも、軽微な変更や効用の著しい変更のないものであれば決定できるようになりました。
従来は相続時に所有者の一部が所在不明の場合、売却などの変更行為を加えるのは難しい状況でした。
そこで改正された民法では、裁判所の決定があれば所有者全員の同意がなくとも、共有物に変更を加えられるようになりました。
つまり裁判所の許可を得れば、たとえ所在不明の共有者がいたとしても相続した共有の土地は売却可能と言えます。
2-2.変更によるメリット
民法改正によるメリットには、以下の内容があげられます。
- 売却や取り壊しが容易にできるようになり、土地活用が円滑に進められる
- 管理不十分な土地の放置により、隣地への悪影響がなくなる
- 所有者特定にかかる労力を削減できる
- 空き家問題が解消でき、若い世代への住宅供給不足を解消できる
- 都市開発を進められる など
民法改正により、上記のように共有物の管理・変更が容易になりました。
改正前は、共有者間で意見が食い違ったり、共有者が特定できなかったりしたことで、不動産の売却や再利用ができませんでした。
例えば相続が発生した場合を考えてみます。
相続人が複数いる場合、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産は、遺言書がない限り自動的に相続人全員の共有物になります。
しかし、土地や建物といった不動産は、現金のように簡単に分けられません。そこで相続人全員で遺産分割協議を行い財産を分けます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、相続した不動産を共有物として複数人で所有することも珍しくありません。
この場合、不動産の名義人が登記上は被相続人のままですが実際に所有するのは相続した共有者です。
このような不動産が放置されると、月日の経過で誰が所有しているのかが分からなくなり、売却などの対処ができず、さらに放置されるという悪循環が生じていました。
そこで、この度の民法改正が共有問題解消の手助けになり、さらに土地活用や空き家問題への有効な対策として期待できるでしょう。
2-3.変更によるデメリット
この度の民法改正によるデメリットは特にありません。
複数人で所有する土地・建物を相続したものの、対応が取れていなかった人にとっては民法改正が問題解決の糸口になるのではないでしょうか。
3.不動産の共有管理でよくあるトラブル
不動産の共有管理でよくあるトラブルとして、以下3つのケースがあります。
- 共有物の管理方針が共有者間で割れているケース
- 共有者の賛否が不明なケース
- 共有者が行方不明なケース
それぞれ詳しく解説します。
3-1.共有物の管理方針が共有者間で割れているケース
共有している不動産の管理方針が共有者間で割れている場合に、トラブルになるケースがよくみられます。
旧民法では、共有物の変更に関しては共有者全員の同意が必要でした。そのため、共有者間で意見が割れている場合は変更などができず、共有物の円滑な利用や管理の阻害につながっていました。
そこで改正民法では、形状や効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については、全員の同意ではなく持分価格の過半数で決定できるように要件が緩和されました。
また、賃借権の設定についてのルールも整備されています。
改正民法では、以下の賃借権において記載してある期間を超えない賃借権の設定であれば、持分の価格の過半数で決定できると定められています。
図5_賃借権の設定
3-2.共有者の賛否が不明なケース
共有者自身が共有不動産から遠く離れて暮らしている場合や、所有権があることを忘れている場合には、連絡をとっても明確な返答が得られない可能性があります。
旧民法の場合、共有者の賛否が不明なケースでは不動産の変更行為(売却など)が行えず問題となっていました。
そこで、民法改正により賛否が分からない共有者がいる場合でも、裁判所の決定があれば、その共有者以外の共有者の過半数によって管理に関する事項を決定可能になりました。
ただし、賛否が分からない共有者が共有持分を失う行為に対しては、利用できません。
具体的には抵当権の設定が挙げられます。抵当権の設定とは、住宅ローンを組む際に、金融機関が対象の不動産に対して権利を設定することです。
万が一ローンの支払いが滞った場合に、抵当権の設定で金融機関は不動産を差し押さえ競売にかけられます。
つまり、抵当権が行使されると所有者は持分を失うため利用できないのです。
また、賛否を明らかにしない共有者の持分がほかの共有者よりも多い場合や、複数の共有者が賛否を明らかにしない場合も利用できないため注意が必要です。
さらに裁判所に申し立ててから、許可が降りるまで通常2週間かかることも覚えておきましょう。
裁判所は共有者に対して決定しようとしている管理事項を伝え、期間内に賛否を明確にするように催告します。
3-3.共有者が行方不明のケース
改正前の民法では、行方不明の共有者がいる場合は、裁判所で「不在者財産管理制度」という手続きを行う必要がありました。
その際、行方不明者ごとに予納金を納める必要があり、行方不明者が複数人いる場合は、費用が高額になったり手続きも複雑になったりするため、行う者が少ないという問題がありました。
また、相続登記の決まりはなかったため、相続時に行方不明者がいる場合は、売却などせずにそのまま放置される問題も起こっていました。
そこで、民法改正により共有者のなかに行方不明の人がいる場合は、行方不明者以外の共有者全員の同意を得て共有物に変更を加えられるようになりました。
また、所在が分からない共有者以外の共有者の持分の過半数によって、管理に関する事項を決定可能です。
このように、民法改正によって共有者のなかに所在不明者がいる場合でも裁判所で手続きするだけで共有物の変更ができるようになりました。
まとめ
この記事では、民法改正によって変わった共有物の管理に関して詳しく解説しました。
旧民法では、不動産の売却などの変更行為に関しては、共有者全員の同意が必要でしたが、改正民法では軽微な変更に関しては、持分価格の過半数の同意でも問題ないと制度が緩和されています。
また、一部の共有者の所在が不明の場合に、全員の同意が取れないため、長期的に放置され円滑な土地活用や管理ができていなかった問題に関しても、裁判所を通すことで、所在不明の共有者以外で共有物の管理や変更が可能になりました。
所有者不明の不動産を相続して管理や対応に困っていた人も、この度の民法改正によって、円滑な土地活用が進められるのではないでしょうか。
本記事が、共有不動産を所有している人の悩みを解決できたら幸いです。
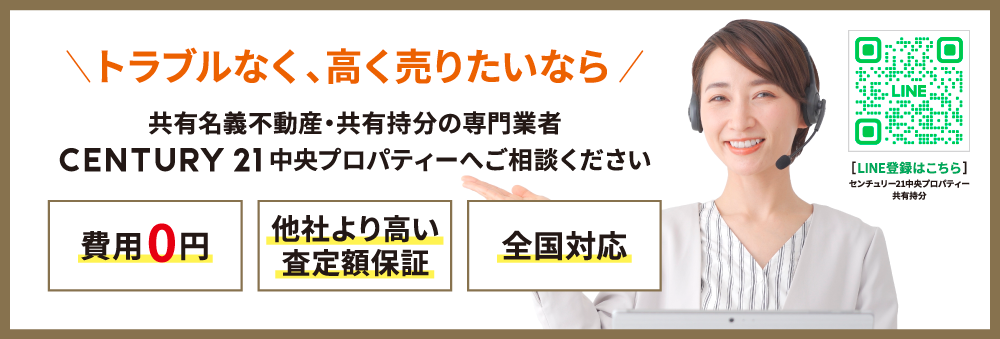
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。